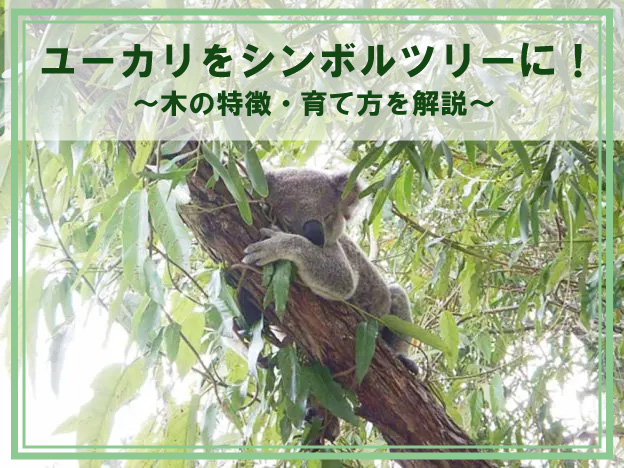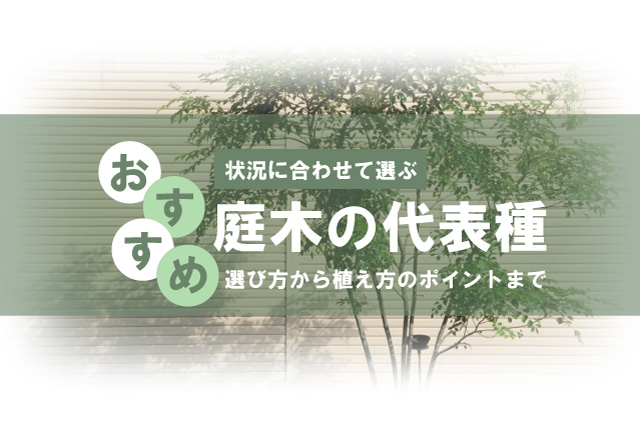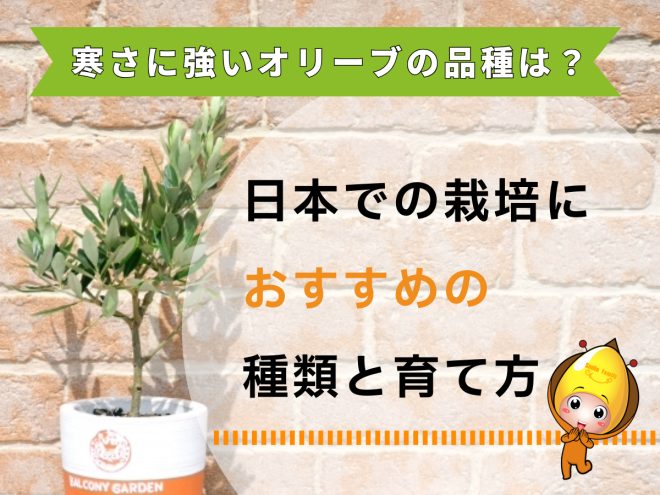コアラのイメージが強いユーカリも、実はシンボルツリーとして人気のある庭木の1つです。
「ユーカリってどんな木なの?」
「初心者でも育てられる?」
今回はそんな悩みを解決するため、ユーカリの育て方や特徴について徹底分析します。
その他のシンボルツリー関連記事はこちらから
庭のプロおすすめのシンボルツリー15選!テイストや環境に合わせてご紹介します
風水・運気が向上するとされるシンボルツリーを紹介
 目次
目次
シンボルツリーとして人気のユーカリ

ユーカリは、シンボルツリーとしても人気のある常緑高木樹です。
シルバーリーフと呼ばれる銀色がかった葉色が特徴的で、葉の形状も可愛らしい形をしています。
葉を落とさない常緑樹であることや、その涼しげな雰囲気が人気の理由です。
ユーカリとは

ユーカリはフトモ科ユーカリ属の常緑高木樹で、別名ユーカリジュと呼ばれています。
南半球のオーストラリアやタスマニアなどに自生しており、非常に大きく成長するのが特徴です。
ユーカリには数多くの種類があり、現在では800種以上が確認されています。
近年ではドライフラワーや切り花にも用いられており、生花店などでもその姿を見ることができます。
また、ユーカリといえばコアラを思い出す方も多いのではないでしょうか。
実はコアラが食べるユーカリの葉は、数百種あるうちの数種類だけです。
「コアラはどんなユーカリの葉でも食べるだろう」と思いがちなので、この事実にはビックリですよね。
ユーカリの種類
先程ユーカリには800種類以上の種類があると説明しましたが、今回はシンボルツリーとして人気な3種類についてご紹介します。
ユーカリ・グニー

ユーカリ・グニーは、葉の形状が可愛らしく密に茂るのが特徴です。
葉は小ぶりな卵型で、少し青みがかった葉色をしています。
この品種はドライフラワーや花束でも人気で、香りの良さも魅力となっています。
その香りは非常に清涼感がありつつも、ほのかな甘みを感じさせます。
ユーカリ・グニーは耐寒性が高く、非常に育てやすい品種です。
ユーカリ・ポポラス

ユーカリ・ポポラスは前述のユーカリ・グニーと異なり、葉が大きく平べったい形状をしているのが特徴です。
グニーよりも銀色が強く、より軽やかな印象を持ちます。
成長してくるとしだれたような樹形に変化し、そよぐ姿が非常に涼しげな雰囲気を演出します。
また、ユーカリ・ポポラスは大きくなると実をつけるようになります。
緑色の小粒の実が枝先に多く実り、リースやスワッグの材料としても人気です。
レモン・ユーカリ

レモン・ユーカリは、名前の通りレモンのような香りを放つ種類です。
葉は前述の2つと異なる細長い形状をしています。
その濃密な香りには防虫効果があり、虫が苦手な方にもおすすめです。
しかし、レモン・ユーカリは耐寒性が低いという弱点があります。
寒い地域で育てる場合は、室内で越冬させるなどの工夫が必要です。
ユーカリの効能
ユーカリの香りには様々な効能があります。
主な効果は、リラックス効果や交感神経の活性化を促すといったもの。
アロマオイルとしては風邪や花粉症の予防・症状緩和、ダニやノミ、ハエに対する防虫効果、集中力アップなど、非常に万能です。
加えてユーカリは風水においても良い庭木となっています。
風水では観葉植物を「姿」と「葉の形状」によって分類します。
レモン・ユーカリの尖った葉は鋭い気を発生させるため、玄関近くに置いて悪い気を遠ざけるのが良いとされています。
反対にユーカリ・ポポラスのように葉の丸い種類は、気を落ち着かせるため、リビングなど人が普段生活する場所に最適です。
ユーカリは超高木!?
ユーカリは、自生のものでは100mを超えることもある超高木です。
種類によっても異なりますが、庭が狭い場合や手入れに十分な時間を割けない場合には、ユーカリの地植えはおすすめできません。
こうした場合は鉢植えで育てましょう。
ユーカリの花
ユーカリは4~5月ごろになると、白い花を咲かせます。
まるでイソギンチャクのような姿の花が枝先集まって咲き、とてもエキゾチックな印象です。
種類によってはピンク色の花を咲かせるものや、開花時期が9~10月ごろのものもあります。
ユーカリの毒
ユーカリの葉に毒があることは、コアラの話で聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
葉には青酸配糖体と呼ばれる毒素を含んでおり、誤って口にすると食中毒や喘息の悪化といった症状を引き起こします。
小さなお子さんやペットがいるご家庭では十分注意しておきましょう。
また、この青酸配糖体は青梅にも含まれています。
ユーカリの料金相場
ユーカリは、鉢4号サイズのものであれば3,000~5,000円前後、8号ほどの大きなものになると10,000~15,000円前後で販売されています。
比較的温暖で、寒くない地域であれば、小さめのサイズを購入して育てるのも良いでしょう。
ユーカリの育て方(栽培環境)

ユーカリは、その美しいシルバーリーフが魅力の常緑樹で、庭木やシンボルツリーとして人気があります。
特にユーカリ・ポポラスは、ハート形の葉が可愛らしく、オリーブとの寄せ植えにもぴったりです。
栽培難易度も低めですが、適した栽培環境とお手入れをしっかり行うことで、元気に育てることができます。
ユーカリは日当たりが良く、水はけの良い場所を好みますが、地植えでは根っこが広がりすぎて枯れることもあるため、鉢植えでの管理もおすすめです。
特に冬には雪や冷え込みに注意し、マルチングや防寒対策が必要です。
鹿沼土やマグァンプなどを使った土づくりもポイントで、挿し木や脇芽から増やすことも可能です。
ここでは、栽培環境においてのユーカリの育て方ついて、下記4つを詳しく紹介します。
- ユーカリの苗の選び方
- ユーカリに最適な栽培環境
- ユーカリに最適な土づくり
- ユーカリの植え付け、移植
ユーカリの苗の選び方

ユーカリの苗を選ぶときには、葉っぱがたくさん展開し、鉢に強く根を張った元気で丈夫なものを選ぶことが大切です。
比較的ユーカリは生長スピードが早く、根っこがしっかりと張るため、苗選びの段階で健康な苗木を選ぶことが、その後の生育に大きく影響します。
まずは、ユーカリの苗選びのポイントについて下記3つについて、細かくチェックしてみてください。
- 葉の色とつやを確認
- 根っこの伸び具合を確認
- 育てる場所を確認する
これらのポイントを押さえて、ユーカリの苗を選べば、庭や室内で元気に育てることができますよ。
ユーカリの苗選びのポイント
①葉の色とつやを確認
ユーカリの苗を選ぶときに注意してもらいたいポイントは、まず葉の色とつやを確認しましょう。
シルバーリーフと呼ばれるユーカリの葉は、銀色がかった色が特徴ですが、元気な苗は葉がしっかりとつややかで、色にムラがありません。
また、葉がしおれている・パリパリに乾燥している苗や、芽が育っていないものは避けます。
苗を手に取って、茎や枝を軽く揺らしてみて、しっかりと根付いているかどうかも確認しましょう。
もし茎がぐらついているようであれば、その苗は地植えや鉢植えにしても育ちにくく、最悪の場合、枯れる可能性もあります。
②根っこの伸び具合を確認
苗の根っこもチェックポイントです。
購入時に鉢を軽く持ち上げて、根が鉢底から飛び出しているか確認しましょう。
根が鉢底から見えている苗は、元気に育っているものです。
逆に、根が鉢の中で巻いているような場合や、根がほとんど見当たらない苗は、栽培が難易度の高くなるので注意してくださいね。
③育てる場所を確認する
ユーカリの苗選びで特に注意したいのは、冬の寒さです。
ユーカリは寒さに弱い品種が多く、耐寒性のある品種を選ぶか、鉢植えにして寒い時期には室内に取り込めるような管理が必要です。
特に雪が降る地域では、ユーカリが枯れるリスクが高いため、寒冷地で育てる場合は防寒対策も視野に入れて苗選びをしましょう。
ユーカリに最適な栽培環境

ユーカリを元気に育てるためには、適切な栽培環境を整えてから、地植えや鉢植えで育てます。
基本的にユーカリは、日当たりの良い場所を好むため、育てる場所はできるだけ直射日光が当たる場所を選びましょう。
日陰では生長の流れが鈍くなったり、葉の色が悪くなったりしてしまうので、午前中に日光が多く差し込む場所を選びます。
特にユーカリ・ポポラスやウェブステリアナは明るい日差しを好むため、風通しの良い日向での栽培がべスト。
また、ユーカリは過湿に弱いため、購入後すぐに植える場合は、鹿沼土や軽石を入れた水はけの良い用土を準備しましょう。
庭の排水性が悪い場合は、などを混ぜて、水はけを改善するのがポイントです。
特に鉢植えで管理する場合、用土が適していないと根腐れを起こし、枯れてしまうことがあります。
地植えにする場合も、鹿沼土・赤玉土など排水性を良くした土を選び、植木の周りが水はけの良い環境になるように工夫しましょう。
鉢植えで育てる場合は、鉢底に砕いた瓦や鉢底石を敷き、マグァンプなどの肥料を混ぜた通気性の良い用土を使うと良いです。
さらに、ユーカリは風にも弱いため、強風にさらされやすい場所では支柱を立てて、木が倒れないように固定しましょう。
特に、若い苗木の段階では幹がやわらかく、風によって曲がりやすいので注意が必要です。
また、ユーカリの栽培にはスペースも押さえておきたいです。
ユーカリは生長スピードが早く、大きくなり過ぎることもあるため、庭に十分なスペースがない場合は鉢植えで管理するのが良い方法です。
植木の根っこが広がり過ぎないように、定期的に剪定をして樹形を整えることも忘れずに行いましょう。
ユーカリに最適な土づくり

根っこが浅く、過湿に弱い性質を持ったユーカリは、水はけの良い用土を用意することがポイント。
健康に育てるためには、通気性・排水性・保肥性の高い土づくりがとても大切です。
まず、鹿沼土や赤玉土を混ぜた排水性の高い土を準備しましょう。
これにより、根が常に湿った状態になるのを防ぎ、根腐れのリスクを軽減できます。
また、ユーカリの生長を促すために、植え付け時にはマグァンプなどの緩効性肥料を元肥として使うのがおすすめです。
肥料を土にしっかりと混ぜ込むことで、ユーカリの苗が育つために必要な栄養を持続的に供給でき、
ただし、たくさん肥料を与えてしまうと生長スピードがさらに早くなり、樹高が大きくなり過ぎることも。
1〜2掴み程度を目安に、多く与え過ぎないように心がけましょう。
ユーカリ・ポポラスなどの品種は、特に通気性が良い土を好みます。
鉢植えにする場合は、軽石やパーライトを加えることで、さらに水はけと通気性が良くなります。
根っこが酸素をしっかりと取り込みやすくなるため、根腐れが起きにくくなり、健康に育ちやすくなるでしょう。
鉢植えは過湿になりやすいため、用土の選び方がとても大切です。
また、地植えの場合は、植える場所の排水性を事前に確認しておくこともポイント。
水が溜まりやすい場所では土が湿りすぎてしまい、根が呼吸できなくなります。
必要に応じて、植える場所の土に腐葉土や砂を混ぜ、通気性を確保します。
庭に広いスペースがある場合でも、定期的な土のチェックは忘れずに行いましょう。
さらに、ユーカリは自然な酸性の土壌を好むため、植え付け前に土のpH値を確認するのも大切です。
酸性度が足りない場合は、ピートモスなどを加えて調整します。
ユーカリの健康な生育を促すためには、適度な酸性の環境が欠かせません。
適切な土づくりを行うことで、ユーカリはしっかりと根を張り、元気に育ちます。
土の選び方ひとつで、ユーカリが枯れるか、立派に育つかが大きく変わるため、丁寧な準備が必要です。
ユーカリの植え付け、移植
ユーカリの植え付けは、4〜6月の春から初夏にかけて行いましょう。
日当たりと風通しの良い場所を選びと、ぐんぐん生長します。
また、ユーカリは若い時期に幹がやわらかく、風や自重で曲がってしまうこともあります。
そのため、植え付け直後には支柱を立て、しっかりと木を支えるようにしましょう。
支柱があることで、幹が真っ直ぐ育ち、風の強い日でも安心です。
鉢植えでユーカリを育てる場合は、植え替えを1年に1回程度行いましょう。
剪定後や生育が落ち着いたタイミングで、一回り大きな鉢に移してあげることで、根が伸びるスペースが確保され、元気に育ち続けます。
植え替え時には、必ず水はけの良い用土を使用し、マグァンプなどの緩効性肥料を適量加えると、栄養が長く持続して木がさらに健康に育ちます。
定期的な植え替えと管理を行うことで、ユーカリはどんどん元気に育ってくれますよ。
ユーカリの育て方(お手入れ)

ユーカリは、お手入れのポイントを押さえれば初心者でも育てやすい庭木です。
成長が早く、定期的な水やりや摘芯を行うことで、美しい樹形を保つことができます。
また、ユーカリは肥料をあまり必要としない木ですが、植え付け時や生育期に適した肥料を与えることで、さらに元気に育ちます。
病害虫にも強い一方で、風通しが悪くなると病気が発生しやすくなるので、剪定や摘芯で適度に枝葉を整理しましょう。
夏越しや冬越しにもコツがあり、特に寒い地域では防寒対策が必要です。
ここでは、栽培環境においてのユーカリの育て方ついて、下記4つを詳しく紹介します。
- ユーカリに最適な水やり
- ユーカリの摘芯
- ユーカリが好む肥料
- ユーカリによくある病害虫
- 剪定方法と剪定時期
ユーカリに最適な水やり
ユーカリの水やりは、過度な乾燥や過湿を避けることがポイントです。
ユーカリは乾燥に強い反面、水が多すぎると根腐れを起こしてしまうため、土の状態をしっかり確認しながら水やりを行いましょう。
特に春から夏にかけて気温が上がる時期は、土が完全に乾いてからたっぷりと水を与えるのがコツです。
植え付け直後の苗木はまだ根がしっかり張っていないため、この時期には特に十分な水やりを心がけましょう。
逆に、気温が下がってくる秋から冬にかけては、水やりの頻度を控えめにします。
寒い季節はユーカリの成長もゆっくりになるため、土が乾いてもすぐに水を与える必要はありません。
水を与えるタイミングは、土が完全に乾いてから少し間を置く程度で大丈夫です。
また、鉢植えのユーカリは特に水はけに注意が必要です。
鉢の底からしっかり水が流れるように管理し、鉢底には排水性の良い素材を使うことで、過湿を防ぐことができます。
ユーカリの摘芯

ユーカリの摘芯は樹形を整えたり、枝数を増やしたりするためにとても効果的なお手入れ方法です。
摘芯とは、生長点である先端の芽を摘み取ることで、ユーカリの生長をコントロールしながら、脇芽を促進させる作業です。
ユーカリは生長が早い木なので、摘芯を行うことで背が高くなり過ぎず、横に広がる美しいシルエットを保つことができます。
特に鉢植えでユーカリを育てる場合、摘芯は大切です。
鉢のスペースに限りがあるため、摘芯をしないとユーカリが伸び過ぎてしまい、全体のバランスが崩れてしまう場合も。
植木が背丈ばかり伸びるのを防ぎ、枝を分岐させることでコンパクトで風通しの良い形に整えられます。
また、鉢植えユーカリ・ポポラスなど、生長スピードが早い品種にとっても摘芯は効果的です。
摘芯で切り取った枝は、ドライフラワーとして部屋のインテリアにもなりますよ。
摘芯を行うタイミングは、ユーカリの生長が活発になる春から初夏がベスト。
この時期に行うことで、脇芽がしっかりと伸び、夏場にはたくさんの葉を楽しむことができます。
また、秋に摘芯を行うことで、冬の間の生長を抑えることができ、寒さによるダメージを軽減させることができます。
ユーカリの摘芯方法
まず、ユーカリの伸びすぎた先端の新芽を、剪定ばさみ・芽切りばさみでカット。
枝先から2~3節目の数ミリ上でカットすると、枝枯れしにくくなります。
これにより、その下から脇芽が出てきてユーカリの葉がより密に茂り、見た目もふんわりとした仕上がりに。
もし、摘芯した後に脇芽が伸び過ぎるようであれば再度摘芯を行うことで、さらにコンパクトに仕上げられます。
ユーカリが好む肥料

ユーカリに最適な肥料の与え方ですが、植え付けや植え替えのときに元肥としてマグァンプなどの緩効性肥料、または有機質の肥料を使うのがおすすめです。
例えば、油かすなどを土にしっかりと混ぜ込むことで、植物に必要な栄養を安定的に与えられます。
元肥をしっかりと入れることでユーカリの根がしっかりと張り、元気に育ちます。
それ以外の時期には、定期的に液体肥料を施すと良いでしょう。
水やりのタイミングに合わせて液肥を使うことで、手軽に栄養を与えることができます。
特に生育が活発になる春から初夏にかけては、月に1〜2回のペースで液肥を与えると、ユーカリの生長が促進されます。
逆に気温が下がる秋や冬は、ユーカリの生長が緩やかになるため、肥料を控えることがポイントです。
ユーカリは肥料をあまり多く必要としない木ですが、適度に栄養を補うことで、より丈夫で美しい木に育ちますよ。
ユーカリによくある病害虫

ユーカリは香りに防虫効果があるため、病害虫に強い木ですが、環境が整っていないと被害にあうことも。
特に日当たりが悪かったり、風通しが悪くなったりする場所では、病害虫が発生しやすくなるので注意が必要です。
置き場所は、しっかり日が当たる場所を選び、風通しが良い環境で育てましょう。
また定期的に剪定を行い、枝葉が混み合わないようにすることも病害虫の予防には効果的です。
ユーカリの木には、比較的カイガラムシやハダニ、さらにイラガの幼虫(毛虫)が付くこともあります。
茎や葉に寄生して養分を吸い取り、木を弱らせてしまうカイガラムシは、見つけたら早めに手やピンセットで取り除くようにしましょう。
乾燥した環境で発生しやすいハダニは、葉が白っぽく変色させ、定期的に葉に霧吹きで水をかけると予防に効果があります。
ただし、夏から秋(7~11月)ごろにかけて1~2回発生するイラガの幼虫は毒トゲを持ち、刺されると電気が走ったような痛みが生じます。
触れないようにピンセットで駆除したり、殺虫剤を散布したりして対処しましょう。
また、病気ではうどんこ病が代表的です。
白いカビのようなものが葉に広がる病気で、風通しが悪く湿度が高い場所で発生しやすくなります。
これも、風通しを良くする剪定が予防策になります。
剪定方法や剪定時期

ユーカリは、4~5月のが気温が暖かくなってきたタイミングで剪定を行いましょう。
強剪定をしても新しい芽が出やすく、木の健康を保ちながら樹形を整えることができます。
根が浅いため枝葉が多く茂ると、風にあおられて倒れるリスクが高まるので適度に剪定を行うことが大切です。
地植えの場合、側枝を10cmほどの長さで切り戻し、枝数を増やして自然な樹形に整えましょう。
風通しが良くなり、木全体のバランスが保たれます。
毎年の剪定を繰り返すことで、ユーカリはどんどん大きく生長していきますが、目的の高さになったら主幹を剪定して高さを抑えるようにします。
主幹を切った後は、切り口が腐敗しやすいので保護剤を塗ってケアすることが大切です。
鉢植えでユーカリを育てている場合は、茎の先端を摘み取る摘心を行うことで枝分かれを促し、コンパクトな樹形に仕立てることができます。
ユーカリの剪定は、見た目を整えるだけでなく、木を健やかに育てるために欠かせないお手入れです。
適切な時期と方法で剪定を行い、美しい樹形を維持しましょう。
夏越し/冬越し
ユーカリは、夏越しと冬越しのお手入れが必要な庭木です。
特に夏場の高温多湿や、冬の寒さ対策をしっかり行うことで元気に育てることができます。
まず、暑さに強い一方で湿気に弱い性質を持っているユーカリは、夏越しをする場合水やりは控えめにし、土が乾いたのを確認してから行いましょう。
特に梅雨の時期や猛暑が続く時期は、土の過湿を避けることが大切です。
風通しが悪くなると根腐れや病害虫の被害が出やすくなるので、鉢植えの場合は日陰や風通しの良い場所に移動させるといいです。
また、比較的霜に弱くて、耐寒性の低い品種が多くあるユーカリは、寒さの厳しい地域では防寒対策が必要です。
特に雪が降る地域では、地植えではなく鉢植えにして、冬場は室内に取り込むことでユーカリが枯れるのを防ぎます。
耐寒性のある品種であっても、霜が降りる時期には麻布などで幹巻き、腐葉土やバークチップでマルチングなどの防寒対策を施してあげると安心です。
根元にマルチングを施すことで土の中を保温でき、幹にわらや麻布を巻いて寒さから守ることで、霜にも当たりにくくなります。
鉢植えの場合は、室内に移動させて管理し、水やりも控えめにして土が乾いてから少量ずつ与えましょう。
夏越しや冬越しの管理をしっかり行うことで、ユーカリは一年を通して健康に育ち、美しいシルエットを保つことができます。
ユーカリの育て方(挿し木)

ユーカリの挿し木は、比較的簡単に増やせる方法のひとつです。
特にユーカリ・ポポラスなどの品種は、挿し木でも根付きやすく、初心者の方でもチャレンジしやすいです。
適した時期に挿し木を行い、正しい方法で管理すれば、丈夫なユーカリの木を育てることができます。
挿し木で増やしたユーカリは、庭木としてだけでなく、鉢植えや寄せ植えとしても楽しめます。
挿し木のやり方を覚えておくと、お気に入りのユーカリをどんどん増やすことができ、庭やベランダでたくさんのシンボルツリーとして育てることができますよ。
ここでは、ユーカリの挿し木での増やし方について下記2つ紹介します。
- 挿し木の時期
- 挿し木のやり方
挿し木の時期
一般的に、ユーカリの挿し木に最適な時期は、春から初夏にかけての4〜6月、または秋の9〜10月です。
春から初夏は、気温が安定して暖かく、ユーカリの生長が活発になる季節です。
この時期に挿し木を行うと、根が付きやすく、挿し穂が順調に生長します。
特に、ユーカリ・ポポラスやウェブステリアナなどの品種は、春に挿し木を行うと高確率で成功します。
また、秋に挿し木を行う場合は、気温が極端に下がる前に作業を終えることがポイント。
9〜10月に行うと夏の暑さを避けつつ、十分な温かさを保ちながら挿し木を管理できます。
ただし、冬の寒さが厳しい地域では、秋に挿し木を行った場合は防寒対策が必要です。
寒さに弱いユーカリは、冬を越す際に枯れてしまうことがあるため、鉢植えで管理して冬場は室内の暖かい場所に移すなどの工夫をするといいです。
逆に、真夏や真冬の挿し木は避けましょう。
夏は気温が高過ぎて土が乾燥しやすく、挿し木の管理が難しくなります。
また、冬は気温が低過ぎて根が付きにくく、成功率が下がります。
挿し木のやり方

ユーカリの挿し木は、初心者でも比較的簡単に挑戦できる。
適切な手順を踏むことで、元気なユーカリの木を増やすことができます。
挿し木に使う枝は、当年枝と呼ばれる新しい枝が最適です。
ここでは、基本的な挿し木のやり方を紹介します。
しっかりと手順を踏むことで、ユーカリを増やすことができます。
挿し木はタイミングが重要なので、適切な時期に挑戦してみてくださいね!
Step1. 挿し穂を選ぶ
ユーカリの元気な枝の先端から15〜20cmほどの長さでカットします。
これを「挿し穂」といいます。
葉の蒸散を抑え、挿し穂の水分を保つために、葉を2〜3枚残し、先端の新芽は取り除いておきましょう。
Step2. 挿し穂の準備
葉が茂っている部分は軽く切り詰めます。
脇芽や小さな葉は、取り除きましょう。
また、切り口は鋭利なハサミやナイフで斜めにカットすると、根が出やすくなります。
Step3. 挿し木用の土を準備する
鹿沼土や赤玉土、小粒のパーライトを使った水はけの良い用土を準備しましょう。
ユーカリは過湿に弱いので、排水性の高い土が適しています。
鉢やビニールポットに土を入れ、挿す前に軽く湿らせておくといいです。
Step4. 挿し穂を植える
用土に挿し穂を5〜10cmほどの深さで挿し、軽く押さえて安定させます。
複数の挿し穂を植える場合は、間隔を十分に空けましょう。
Step5. 管理と根付くまでのケア
挿し木を日陰で管理し、土が乾かないように適度に水を与えます。
透明な袋をかけて湿度を保つと、根付きやすくなります。
2〜3ヶ月で根が出てきたら、少しずつ日光に当てながら育てていきます。
ユーカリをシンボルツリーにする問題点(デメリット)

シンボルツリーとして人気のユーカリですが、注意点が存在します。
それは、成長速度が早くあっという間に大きくなっててしまうことです。
前述の項目では、剪定は4~5月の花後に行うと説明しました。
しかしユーカリの大きさによっては、1年に何度も剪定が必要になる場合があります。
ユーカリをシンボルツリーとして検討している場合は、庭のスペースや手入れにかけられる時間を十分に考慮するようにしてください。
ユーカリの育て方でよくある質問

ユーカリは、見た目の美しさと育てやすさで人気の常緑樹ですが、育て方に関して初心者の方が抱える疑問も多いかと思います。
特に、適した土壌や水やりの頻度、日当たりなど、基本的な管理方法について知っておくことで、ユーカリをより元気に育てることができます。
また、ユーカリは生長が早いため、剪定のタイミングや病気・害虫対策なども気になるポイントです。
これらの疑問に対する答えを知っておくことで、ユーカリの健康を保ち、美しい樹形を維持できるでしょう。
ここでは、ユーカリの育て方に関するよくある質問について下記5つ紹介します。
- ユーカリはどのような土壌で育てるのが理想ですか?
- ユーカリの水やりはどのくらいの頻度で行うべきですか?
- ユーカリはどのくらいの光を必要としますか?日陰でも育ちますか?
- ユーカリの剪定は必要ですか?いつ行うのがベストですか?
- ユーカリの病気や害虫対策にはどのような方法がありますか?
ユーカリはどのような土壌で育てるのが理想ですか?

ユーカリは、排水性と通気性の良い土壌で育てるのが理想です。
根っこが過湿に弱いため、水はけの悪い場所だと根腐れを起こして枯れてしまうこともあります。
庭に植える場合は、掘り起こした土に鹿沼土や赤玉土、パーライトなどを混ぜて、土の排水性を高めましょう。
特に、雨が多い地域や湿気がこもりやすい場所では、排水性・通気性を意識した土づくりがとても大切です。
鉢植えの場合も同様で、ユーカリが過湿にならないようにするため、底に鉢底石や軽石を敷いて排水性を確保します。
また、植木用の土をそのまま使うのではなく、ユーカリに適した用土をブレンドして使うと安心です。
マグァンプなどの緩効性肥料を少量混ぜておくと、栄養分が長く持続し、育ちやすくなりますよ。
また、ユーカリは酸性の土壌を好むため、もしアルカリ性の土壌で育てる場合は、ピートモスや腐葉土を混ぜて酸性度を調整することもポイントです。
特に、地植えで植える場所が酸性に偏っていない場合、事前に土壌のpHを確認しておくと安心です。
ユーカリに最適な土壌を準備することで根がしっかりと育ち、元気に生長します。
土づくりに少し工夫を加えることで、ユーカリが長く健康に育つ環境を整えることができます。
ユーカリの水やりはどのくらいの頻度で行うべきですか?

ユーカリの水やりは、季節や天候によって調整することが大切です。
基本的にユーカリは乾燥に強い木ですが、過湿には弱いので、水の与え過ぎに注意が必要です。
水やりの頻度は、土の乾燥具合を確認しながら行いましょう。
目安として、春から秋にかけては、土の表面がしっかり乾いてからたっぷりと水を与えます。
特に、植え付け後の苗木は根がまだ浅いため、定期的に水を与えて根付きを良くすることが大事です。
気温が高い夏場は、土が乾きやすいので、朝や夕方に水やりを行うと土がしっかりと保湿されます。
鉢植えの場合は特に乾燥しやすいため、土が完全に乾燥しないように注意しましょう。
ただし、水が鉢底からしっかり流れるように、余分な水分を溜めないようにすることが大切です。
一方冬場は、ユーカリの生育がゆっくりになるため、水やりの頻度を控えめにします。
気温が低い時期は根が水を吸いにくくなるので、土が完全に乾いたときにだけ水を与える程度で十分です。
過剰に水を与えてしまうと、根腐れを引き起こす原因になるため、冬の水やりは慎重に行いましょう。
ユーカリの水やりは季節や環境に応じて調整し、乾燥し過ぎず過湿にならないように管理することが元気に育てるコツです。
ユーカリはどのくらいの光を必要としますか?日陰でも育ちますか?

ユーカリは日光を好む植物で、特に日当たりの良い場所で育てると、健康で元気な姿を保ちます。
ユーカリの生長には、1日を通してしっかりと日光が当たる環境が理想的です。
直射日光を浴びることで葉の色も鮮やかになり、しっかりとした枝葉が茂ります。
日光不足の環境では、ユーカリの幹や枝が間延びしてしまい、葉も元気を失ってしまうことも。
完全な日陰では育ちにくいので、半日陰になる場所を選んで管理します。
生長が遅くなったり、樹形が乱れたりすることもあるので、できるだけ日当たりの良い場所に植えましょう。
特に鉢植えで育てる場合は、季節に応じて日照が確保できる場所へ移動させると良いです。
ユーカリは風通しの良い環境を好むので、直射日光が当たるだけでなく、適度に風が通る場所を選ぶのもポイントです。
特に湿気がこもる環境では、病気にかかりやすくなるため、日当たりと風通しを意識した場所で育てることが大切です。
このように、ユーカリは日当たりをしっかり確保できる場所で育てると、元気で丈夫な木に成長します。
日陰でも育つことはありますが、可能な限り日光を確保することが成功のカギです。
ユーカリの剪定は必要ですか?いつ行うのがベストですか?

ユーカリの剪定は、健康的に生長するために・美しい樹形を保つために必要です。
特にユーカリは生長スピードが早い木なので、放っておくとすぐに背が高くなりすぎてしまったり、枝が暴れて樹形が乱れることも。
定期的な剪定を行うことで、理想の大きさや形に整えながら、風通しを良くして病害虫の予防にもつながります。
ユーカリの剪定に最適な時期は、気温が暖かくなってきた4~5月にかけてです。
この時期であれば、強剪定をしても新しい芽が出やすく、木がバランスよく育ちます。
新芽もしっかりと育ち、枝葉がふんわりとした仕上がりになります。
剪定のポイントとしては、長く伸びすぎた枝や交差している枝を根元から切り落とし、全体の樹形を整えることが大切です。
また、内側の密集した部分を少し間引くように剪定すると、風通しが良くなり、病気の予防にもなります。
剪定をし過ぎると、逆に木にストレスを与えてしまうことがあるので、様子を見ながら適度に行いましょう。
ユーカリは強剪定にも耐える木ですが、適切なタイミングと方法で剪定することで、さらに元気に育ちます。
ユーカリの病気や害虫対策にはどのような方法がありますか?
ユーカリは基本的に病害虫に強い木ですが、環境や育て方によっては病気や害虫の被害を受けることがあります。
特に、湿気が多い場所や風通しが悪い場所では、カビや害虫が発生しやすくなるので注意が必要です。
比較的ユーカリに多い病気は、うどんこ病や根腐れがあります。
うどんこ病は、白い粉のようなカビが葉に広がる病気で、風通しの悪さが原因で発生します。
予防策としては、定期的な剪定を行い、枝葉を間引いて風通しを良くすることが大切です。
また、カイガラムシ・ハダニがユーカリの茎や葉にくっつきやすく、養分を吸い取り木を弱らせてしまいます。
見つけたら、早めにピンセットや歯ブラシを使って取り除きましょう。
ハダニは乾燥した環境で発生しやすく葉が白っぽくなったり、点々としたダメージが見られたりします。
こまめに葉に水を吹きかけて、極端な乾燥を防ぐことが予防策になります。
さらに、ユーカリを健全に育てるためには、定期的に消毒や殺虫剤の散布も有効です。
消毒剤は3月や7月の時期に散布すると、病気や害虫の予防効果が高まります。
ただし、ユーカリは根が過湿に弱いので、水やりの際も水のやりすぎに注意し、根腐れを防ぐために排水性の良い土で管理しましょう。
ユーカリの剪定を低負担でおこなうならsmileガーデンへ!

品種が多く、好みのものが見つかりやすいユーカリ。
品種によっては乾燥にも寒さにも強いのでシンボルツリーにおすすめではあるのですが、実は成長がかなり速いため日々の剪定がとても大変だったりします。
もしも「自分で剪定を何度もするのは大変」と感じるのであれば、プロの造園会社に日々の剪定を依頼してみてはいかがでしょうか。
smileガーデンでは、お庭のプロとして5mを超える高木であってもしっかりと剪定作業をおこないます。
ご自身では作業が難しい高さであっても、プロの技術と経験で安全確実に剪定作業をおこないますので、安心して作業をお任せくださいませ。

愛知県稲沢市生まれ。稲沢市が「日本四大植木産地」であることもあり、幼少期から植木に囲まれて成長。
東京農業大学卒業後、名古屋市内の造園会社に就職。公園の整備工事から国交省事業の国道整備工事における土木及び街路樹等の植栽工事に現場代理人として携わる。
熊本県の海と山に囲まれた田舎で育ち、幼少期からガーデニング好きの祖母を手伝う。高校時代には、音楽を中心に様々な芸術分野に興味を持つようになり、同時に自然の持つ面白さや奥深さに気づく。現在はライターとして活動し、多趣味を活かして幅広いジャンルで執筆。他にもカメラやデザインについて勉強中。自然に囲まれて暮らすのが1つの目標。