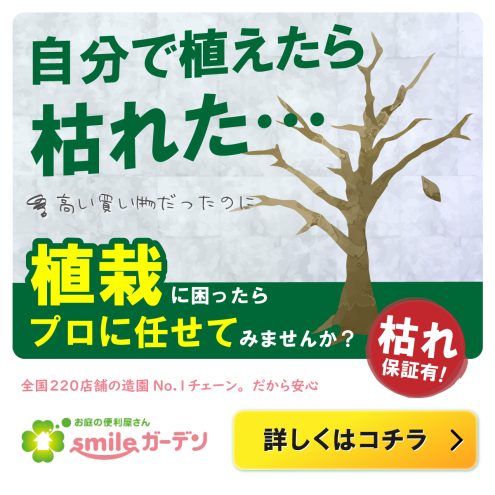植えたばかりのまだ根付いていない木は、非常に不安定なため支柱を付ける必要があります。根っこが伸びて根付くまでの期間は、庭木が特に枯れやすいタイミングでもあります。せっかく植えた庭木を大事に育てていくために、支柱の立て方を覚えておきましょう。
 目次
目次
植えたばかりの庭木に支柱が必要な理由

植えたばかりの庭木は、まだ根が十分に張っておらず、少しの風でも倒れてしまうこともあります。
そんなときに支柱の立て方をしっかり押さえておけば、DIYでも簡単に木を支えることができ、苗木の生長をスムーズにサポートできます。
八掛や添え柱をはじめ、縛り方にもいろいろな工夫があり、庭木のサイズや場所にあわせて補強の強度を調整できるのがポイント。
また、しっかり支柱を立てておくと、幹や根に負担が少なく、苗木が地面にしっかり根付きやすくなるので、根本がぐらついてしまう庭木には支柱を検討しましょう。
ここでは、植えたばかりの庭木に支柱が必要な理由について下記2つを詳しく紹介します。
- 風で倒れることを防ぐ
- 苗木が根付きやすくなる
風で倒れることを防ぐ

まだ根が十分に張っていない苗木は、少しの風でも大きく揺らされてしまい、枝葉や幹に負荷がかかって倒れてしまうことがあります。
そこで大事なのが、庭木をしっかり補強する支柱です。
DIYでも簡単に木を支えられ、コツを押さえておけば、風の被害から苗木を守ることができるので安心です。
特に、地面にまだ十分な根を下ろしていない初期の段階では、一度大きく傾いてしまうだけで苗木の生長が止まったり、枯れてしまったりすることも。
そうならないために、植えたばかりの庭木にはしっかりと支柱をつけましょう。
風は横方向の力を与えるので、苗木に合わせて支柱の数や結ぶ位置を見極め、隙間ができないよう縛り方を調整するのがポイント。
幹と支柱の間にクッション材を挟むと、すり傷や圧迫を防げます。
定期的に支柱の状態をチェックし、庭木の成長に合わせて紐の締め具合や支柱の位置を変えていくことも大切です。
そうすることで、木を支える役目を果たしながら、根がしっかり張るまで守ってあげられます。
風から木を守るという目的を意識して支柱を立てるだけで、健康的な樹形を保ちやすくなるのもうれしいポイントです。
苗木が根付きやすくなる

苗木が根付きやすくなるためには、まだ幹や根が十分に伸びきっていないうちから木を支えることが欠かせません。
少しの風や衝撃でも揺れる庭木は、根が動くと生長の妨げになることもあります。
支柱をしっかりと立て、DIYでも簡単に八掛や添え柱などの補強を取り入れれば、強い風でも倒れにくくなります。
縛り方を丁寧に行い、幹との間にクッション材を挟むなどの工夫をすれば、樹皮を傷めにくくなりますよ。
そもそも支柱を使う目的は、根が落ち着く時間を与えること。
そうすれば、苗木は養分と水分を吸収しやすくなり、ぐんぐん生長していきます。
根付くまではこまめに様子をチェックして、縛り目がきつくなっていないか、補強が外れかけていないかを確認しましょう。
木を支える工夫が、丈夫な幹と美しい樹形を作ってくれます。
植木支柱の種類

植木の支柱には、庭木を風や傾きから守り、きちんとした樹形を維持する大切な役割があります!
特に苗木はまだ根が浅く、少しの風でも倒れてしまうことがあるので、支柱の立て方をしっかり知っておけば、DIYでも簡単に木を支えることができます。
支柱の縛り方や補強にはいくつかの方法があり、八掛や添え柱など、それぞれに合ったやり方を選ぶのがポイント。
また、苗木のうちからしっかり支柱を設置しておくと、根が張るまでの間に枝葉が風で揺れても倒木しにくく、樹形が乱れにくいのもメリットです。
さらに、大きく育った庭木に支柱を立て直すときも、立て方を見直すだけで強度が増すので安心です。
ぜひポイントを押さえて、植木を元気に育ててみましょう。
ここでは、植木支柱の種類について下記7つを詳しく紹介します。
- 八ツ掛け支柱
- 布掛け支柱
- ワイヤー支柱
- 添え柱支柱
- 鳥居支柱
- 金属製支柱
- 樹木地下支柱
八ツ掛け支柱
八ツ掛け支柱は、苗木などの庭木をしっかりと補強するために、八本の支柱を放射状に配置して木を支える立て方です。
支柱の縛り方も八掛に結ぶので、風が強い場所でも大きく揺れず、木の成長を安定させやすいのが特徴。
見た目は少し複雑そうに感じますが、ポイントを押さえればdiyでも簡単に設置できる方法です。
支柱をしっかりと八方から立てることで、添え柱を1本だけ使うよりも大きな庭木を支えるときに適しています。
設置のコツとしては、苗木の重心がずれないように位置を確認しつつ、支柱同士を交差させるように立てて、八掛の要領でしっかりと結びましょう。
特に結び目の縛り方は、樹皮を痛めないように麻ひもや支柱用テープなどやわらかい素材を使うと安心です。
八ツ掛け支柱の立て方を正しく押さえておけば、風が吹いても木が倒れにくく、樹形が乱れにくいのもメリット。
庭木が大きく育ってきたら、少しずつ支柱を外しつつ必要に応じて再調整し、きれいなシルエットをキープしましょう。
布掛け支柱
木の幹や枝に布を巻いて支える布掛け支柱は、庭木の樹皮を傷めにくいのがメリットです。
苗木やまだ樹皮がやわらかい木に適していて、DIYでも簡単に取り入れられます。
支柱の立て方は、幹に沿わせて支柱を設置し、クッション代わりの布や麻袋を重ねて縛り、補強するのがポイント。
ひもの縛り方も、強く締めすぎると木を痛める恐れがあるため、ぴったり巻いてから少し余裕を持たせると良いでしょう。
また、布掛け支柱は添え柱と組み合わせることもできるので、風が吹いても木を支える力が上がります。
設置時には、八掛支柱のように多方向から補強する必要はありませんが、木がぐらつかないよう定期的に布の位置や紐の強さをチェックすることが大切です。
特に苗木のうちは樹皮が薄く、傷がつきやすいので、優しい素材を使った布掛け支柱がぴったりですね。
庭木が育ってきたら布を一旦外して幹の状態を確認したり、支柱の立て方を再調整したりしながら、きれいな樹形を維持しましょう。
きちんとチェックしておけば、見た目もすっきりした仕上がりになるはずです。
ワイヤー支柱
ワイヤー支柱は、金属製のワイヤーを使って庭木を固定する方法で、苗木からある程度生長した木まで幅広く対応できるのが特徴です。
支柱の立て方としては、添え柱を組み合わせたり、八掛のように複数方向からワイヤーを張ったりと、状況に応じて自由にアレンジできます。
特に傾きやすい木を支えるときには、ワイヤーをしっかり補強し、たるまないように注意しながら縛り方を工夫すると安心です。
DIYで取り入れる場合は、ワイヤーが幹に食い込まないように保護材を巻いたり、樹皮を傷めないクッション材を挟んだりして、きちんとケアしてあげましょう。
また、ワイヤー支柱は比較的簡単に設置できる一方で、強風などで揺れると緩みやすいことがあります。
定期的にワイヤーの張り具合をチェックし、庭木がしっかりと根を張るまでこまめにメンテナンスをするのがポイントです。
支柱を外すタイミングは、木が自分の力だけで立てるようになってからが理想ですが、まだ幹が細く不安定な場合は無理に外さず、少し長めに設置しておきましょう。
立て方をきちんと押さえておけば、苗木から大きくなった木まで、スムーズに樹形を整えられます。
添え柱支柱
添え柱支柱は、庭木のそばに1本の支柱を立てて木を支えるスタイルで、DIYでも簡単に取り入れられるのが魅力です。
苗木のうちは樹形が不安定なことも多いので、しっかり補強してあげると安心。
支柱の立て方としては、まず植え穴を掘る際に添え柱を一緒に入れ込んで固定し、その後、木の幹と支柱を麻ひもやテープなどで結びます。
縛り方は、強く締めすぎないように注意して、木の生長に合わせて調整するのがポイント。
樹皮と支柱の間に布やゴムをはさんでおくと、摩擦による傷も防げます。
また、添え柱支柱は八掛のように何本も支える方法とは違い、少ない材料でスッキリと仕上がるのが特徴です。
背丈が低めの木には特に向いていて、苗木の段階から地道に世話をすることで、後の手間を減らすことにもつながります。
風の強いエリアや、根の張りがまだ浅い庭木には、補強として添え柱をさらに増やすのも一つの手です。
定期的に結び目をチェックし、木が自力で立てるようになったら支柱を外したり、支柱の立て方を見直したりして、木の自然な生長をサポートしていきましょう。
鳥居支柱

鳥居支柱は、柱を2本立ててその上に横木を渡し、まるで鳥居のような形で庭木を支える方法です。
見た目にもインパクトがあり、木をすっぽり囲むように設置できるのが特徴。
風が強い地域や、幹がまだ細い苗木にも適していて、揺れを抑えながら生長を促せます。
その鳥居支柱の一部として組み合わせるのが、この添え柱支柱。
鳥居を構成する支柱を1本増やすように添え柱を設置すると、さらに安定感が増すので、大きめの庭木や根が浅い木でもしっかり補強できるのが魅力です。
添え柱支柱の設置では、支柱の立て方と縛り方がポイント。
幹に直接触れる部分にはクッション材をはさんで、木の表皮を傷つけないようにしましょう。
DIYで行うときも、八掛など他の支柱方法と組み合わせれば、より風対策が強化できます。
特に背丈のある庭木の場合、添え柱を追加するだけで、支柱同士が支え合う形になるため、しっかり固定しやすくなります。
木が安定すれば、根の張りも良くなり、余計なストレスをかけずに健やかな生長を期待できます。
鳥居支柱と添え柱支柱をうまく活用して、庭木を元気に育てましょう。
金属製支柱
金属製支柱は、頑丈さが魅力の方法で、庭木を長期間しっかり支えるのに適しています。
木の幹や枝が太くなっても曲がりにくく、苗木からしっかり補強したいときにもちょうどいいです。
八掛や添え柱などほかの支柱方法と組み合わせやすく、DIYで簡単に実践できる方法でもあります。
縛り方も、幹に保護材を巻いてから結ぶようにすれば、木を傷めずに固定できます。
また、風の強い地域や土壌が安定しにくい場所でも、金属製ならではの強度で木を支えることが可能。
サビ対策としては、定期的に防錆塗装を施したり、耐久性の高い素材を選んだりすると長く使えます。
設置後は、木が生長するたびに支柱との当たり具合をチェックし、縛り方や高さを都度調整しましょう。
きちんとメンテナンスをすれば、長期にわたって庭木を元気に育てられます。
見た目が気になるときは、カバーやデザイン性のある支柱を取り入れるのもおすすめです。
金属製支柱を上手に活用して、より快適な庭づくりを目指してみてくださいね。
樹木地下支柱
樹木地下支柱は、地面の下に支柱を設置して庭木を固定する方法で、地上部分に支柱が見えにくいのがメリットです。
見た目をすっきりさせたい方や、八掛や添え柱などの従来型の支柱の立て方が合わない場合にもおすすめ。
DIYでも簡単に導入できますが、作業手順をしっかり押さえておくことが大事です。
まず、苗木を植える前に支柱や金具を地中に埋め込み、木の根元付近をサポートする形で補強します。
木を支えるときは、樹皮や根を傷つけないようにクッション材を活用したり、ひもの縛り方を工夫したりするのがポイント。
地下支柱なら地上部分での見栄えを損なわず、風や振動にも強く仕上がるので安心です。
ただし、取り付ける場所や深さを誤ると、木が生長する過程で根に負担がかかりやすくなる場合もあるので要注意。
地盤の状態や根張りの具合を考慮しながら設置しましょう。
庭木が育ってからも、地下支柱の状態をときどきチェックし、必要に応じて補強やメンテナンスを行えば、しっかり木を支える効果が長続きします。
地上型の支柱の縛り方が合わないときや、どうしても支柱を目立たせたくないときには、この樹木地下支柱を取り入れてみてくださいね。
支柱を立てるのに使う道具

木に支柱をつけるためには、支柱本体の他にもいくつかの道具が必要になります。
道具の種類や大きさは庭木のサイズなどによって変わる場合もあるので、自分の庭木に合ったものを選ぶ必要があります。
庭木に支柱を付ける前に、これらの道具をまず準備しましょう。
支柱本体

支柱の本体となる柱には、細長く丈夫なものを使います。これに使う素材にはいくつかの種類があるため、植える庭木の大きさに応じて選ぶ必要があります。
基本的には竹を使うことが多いですが、他にも選択肢があることを覚えておきましょう。
プラスチックの棒
1mより低いような小さい木であれば、100円ショップの園芸コーナーで売っているようなプラスチックの棒を使うことができます。
小さな苗から育てたい場合や、木ではなく草を育てる場合などは、こちらを選択肢に入れてみても良いでしょう。
安価で手に入りやすいので、最も手軽に使うことができます。
竹
人の背丈くらいか、それより少し高いくらいの庭木であれば、竹を使うのが良いでしょう。
丈夫で太さも長さも十分で、比較的安価に手に入るので、よく使われています。
庭に竹林があれば、そこから採って使ってみても良いでしょう。
また、太さは様々なものがあり、笹の茎のように細いものから、人の腕くらいの太さのものまであります。
100円ショップでは売っていないことも多いですが、ホームセンターなどで手に入ることがあるので、探してみましょう。
長さはありませんが、使い古した竹ぼうきの柄の部分を再利用して使うこともできます。
木の丸太
5m以上にもなるような大きな木には、木の丸太を使うことがあります。
倒れた時に、竹では支えきれないような大きく太い木に対して用いられます。
木の丸太を使う場合、ボルトで支柱同士を固定するなどする必要があり、竹の支柱などに比べると大掛かりな工事になります。基本的には、その大きさの支柱をつける場合は造園屋さんなどのプロにお願いするのが無難です。
麻布と麻ひも

支柱と木をくっつけて固定する際に、麻ひもや麻布を使います。
麻布は、支柱が木の幹を傷つけないために使うため、木の幹にグルッと巻いてからその上に支柱をつける形になります。
素材は必ずしも麻ひもや麻布を使わなくても、他の布や紐でも機能的には問題ありません。
大きな竹で支柱をつくる際には、針金や釘で支柱同士を固定する場合もあります。
しかし、たとえばビニールひものような自然に分解されない素材だと、長くつけっぱなしにした場合に木の幹にひもが食い込んでしまうおそれがあります。麻ひもも麻布も安価で手に入りやすいので、基本的にはこれらの素材を使うようにしましょう。
その他の道具

その他に、作業時につける軍手や、支柱を立てる部分の土を掘るためのスコップ、麻布や麻ひもを切るために使うハサミといった道具が必要になります。これらは、自分が普段使っているものなど使いやすいものを用意すれば問題ありません。
支柱設置の手順

道具が準備できたら、いよいよ支柱を設置します。庭木が倒れないように支柱をつけるのに、支柱がうまく固定されていなかったら意味がありません。しっかり手順を踏んで支柱をつけるのがおすすめです。どんな手順で作業を行うのか、チェックしておきましょう。
支柱を立てる場所を決める
まずは、支柱を立てる場所を決めます。支柱は、木の大きさに応じて斜めに1本つけるか、八の字に2本立てるかなどの立て方があります。
1mほどの小さな木の場合は1本、人の背丈より高い木の場合は2本あれば安心です(木の丸太の支柱をつける場合、3本立てたり神社の鳥居のような形の支柱をつくったりといったやり方もあります)。
角度は30~45度くらいで、庭木が倒れそうなときにしっかり支えられる角度にしてください。
また、幹が一本立ちのものは幹の途中で一か所支柱と交差すれば良いですが、株立ちの木の場合、たくさんの幹の中でとくに太いものと2か所交差させるのがおすすめです。
いったん仮置きして、どのように設置するのかイメージしてみてください。
土を掘る

支柱を立てる箇所の土を掘ります。支柱を立てる角度に合わせて、40㎝くらい掘るようにしてください。実際に支柱を置いてみながら作業するのがおすすめです。土が掘れたら、支柱の根元を埋めて軽く踏み固めておきます。
支柱と木を固定する
支柱を木を固定します。木の幹を傷つけないように、幹の支柱をつける位置に麻ひもを1~2周巻き付け、その上に支柱を取り付けて麻ひもで固定します。結び方に指定などはありませんが、外れないようにしっかりと結んでおきましょう。
土を踏み固める
支柱を埋めた土をしっかり踏み固めます。支柱が動いてしまっては庭木を支えられないので、念入りに踏み固めておきましょう。ただし、周りの土すべて踏み固めてしまうと庭木の成長に影響が出てしまうので、踏み固めるのはあくまで支柱を埋めた土の周りだけにとどめるのがおすすめです。
大きな木の場合
5mを超えるような大きな木を植え付ける際に支柱をつける場合、個人で見様見真似で行うのはあまりおすすめしません。支柱がしっかり固定できていないと、木が倒れてくる危険性もありますし、支柱自体が大きく重いので、作業自体も危険な場合があります。
竹の支柱では支えられないような大きな木に支柱をつける場合、プロに相談して施工してもらいましょう。
植木支柱のコツ
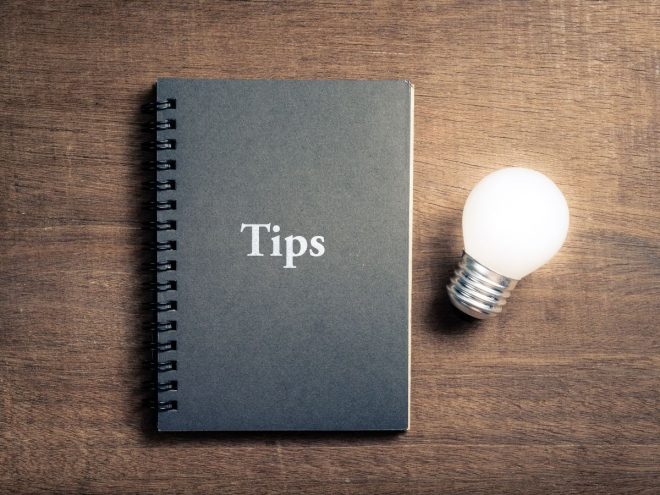
庭木がまだ苗木の段階だったり、幹がしっかり生長していないときは、風で木が傾いてしまうことも。
そんなとき、支柱の立て方を覚えておけば、DIYでも簡単に木を支えることができます。
縛り方を工夫すれば、八掛や添え柱など、いろいろな設置方法と組み合わせながら、より安定感を得られるのも魅力です。
特に支柱の位置や補強の仕方を間違えると、かえって木に負担をかけてしまう場合もあるので注意しましょう。
また、定期的に支柱をチェックしながら、樹形の変化や幹の太さにあわせて結び目を調整することも大切です。
庭木がスムーズに生長するためには、根元への水やりや日当たりの確保などもあわせて意識しておきたいですね。
ここでは、植木支柱の立て方のコツについて下記4つを詳しく紹介します。
- 根杭の縛り方
- 支柱の結び方
- 支柱の補強方法
- 根付いたら支柱は外す
根杭の縛り方
根杭とは、庭木の根元に杭を打ち込み、その杭と幹を結んで木を支える方法です。
特に苗木のうちは根の張りが弱く、少しの風でもグラついてしまうことがあるので、支柱の立て方の一つとして取り入れておくと安心。
DIYでも簡単に取り組めますが、杭を打つ位置を間違えると根を傷つけたり、補強が十分でなかったりする場合があるので、しっかり確認しながら進めていきましょう。
まず、庭木の根鉢を崩さない程度に周りの土を掘り、安定感のある場所に杭を打ち込みます。
杭の長さや太さは、庭木の大きさに合わせて選ぶのがポイント。
八掛や添え柱のように複数本の支柱が必要な場面でも、根杭を1本補助として打っておくとさらに効果的です。
縛り方は、根杭と幹の間に保護材を挟み、木を傷つけないよう配慮しましょう。
麻紐や支柱用テープなど、弾力があって樹皮に優しい素材を使うと安心です。
結んだ後は、木が風や振動で動いたときにきつく締まりすぎないかをチェックし、必要に応じて結び目を調整します。
また定期的に根元の状態を見ながら、支柱の立て方や縛り方をアップデートしていくことも大切です。
木がしっかり自力で立てるようになってきたら、補強が過度にならないよう、タイミングを見て支柱を外したり変更したりしていきましょう。
支柱の結び方

支柱を結ぶときは、まず結び方のポイントを押さえておけば、DIYでも簡単に木を支えることができます。
特に苗木やまだ根がしっかり張っていない庭木の場合、縛り方を間違えると樹皮を傷めるだけでなく、かえって倒れやすくなることもあるので要注意。
支柱の立て方としては、八掛や添え柱など、それぞれの方法に合わせて結び方を変えると補強効果もアップします。
結ぶには、幹と支柱の間にクッション材を挟み、紐やテープを優しく巻くようにしましょう。
きつく締めすぎると幹を締め付けて傷めてしまうので、適度に余裕を持たせることが大事です。
また、庭木の生長速度に合わせて結び目を調整し、定期的に確認することも忘れずにしてくださいね。
特に木が大きく育つと、同じ結び方のままでは幹との間に負荷がかかりやすくなるため、紐の長さや位置を見直すと良いです。
風当たりの強い場所にある庭木は、結び目が緩みやすい傾向があるので、雨上がりや台風のあとには状態をチェックしておきましょう。
縛り方をひと工夫するだけで、苗木でもしっかり支えられるので、ぜひ支柱の立て方をマスターして、元気な庭づくりに活かしてみてくださいね。
支柱の補強方法
支柱の補強方法は、庭木を安定させるうえでとても大切です。
苗木の段階ではまだ根が張りきっていないため、支柱の立て方に合わせてしっかり補強してあげると安心です。
DIYでも簡単に取り入れられるのが魅力です。
たとえば、八掛や添え柱を使った方法で複数の方向から木を支えると、風や雨などの強い揺れにも耐えやすくなります。
縛り方に工夫を加えるのもポイントで、きつく締め過ぎると幹を痛めるおそれがあるため、麻ひもやゴムベルトなど、ある程度やわらかさのある素材を使うのがおすすめ。
支柱を複数設置する場合は、すべての支柱が同じテンションで木を支えるように調節してください。
1本だけ強く引っ張ってしまうと、木が偏ってしまったり、幹に負担がかかったりする場合があります。
また、補強しているからといって完全に安心するのは早いです。
定期的に結び目の状態をチェックし、緩んでいないか、木が生長して幹と支柱が当たっていないかをこまめに確認しましょう。
支柱の立て方に合った補強を組み合わせれば、庭木が風に負けず、元気にすくすく育ってくれますよ。
根付いたら支柱は外す

しっかり庭木を補強するために取り付けた支柱ですが、ずっと付けたままでは木が自分で立つ力を養えなくなります。
幹は風で適度に揺さぶられることで太く育ち、根元から安定していくからです。
いつまでも支柱に頼っていると、幹や根の発達が遅れ、かえって変な樹形になってしまう場合も。
苗木のうちは八掛や添え柱など、庭木に合った支柱の立て方で木を支えることが大切ですが、十分に根付いたら思い切って支柱を外してあげましょう。
目安は1〜2年ほどで、枝葉が元気に茂り、風が吹いてもしっかり自立できるようになったころがおすすめです。
外すタイミングを焦りすぎると、まだ根が張りきっていない場合は倒れるリスクがあるので注意してくださいね。
支柱を外すときは、簡単にできる縛り方の見直しや段階的な外し方を試し、木が十分に揺れに耐えられるかを確認しながら進めましょう。
庭木が自力で根を張り、たくましく生長していく姿を楽しめるかもしれません。
困ったらプロに相談!

まずは庭木をなぜ植木支柱で支えるのか、その目的をしっかり理解しておくことが大事です。
木がまだ苗木のうちは、風や重みですぐに倒れてしまうこともあるため、適切な支柱の立て方を押さえておけば、DIYでも十分に対応できます。
また八掛や添え柱など、庭木の大きさや特性にあわせた支柱の方法を選ぶことがポイント。
小さな庭木なら自分で簡単に設置可能ですが、大きく生長した木や地盤が不安定な場所だと、作業が難しくなることがあります。
そんなときに無理をすると、かえって木を傷めたり、作業中にけがをしてしまうリスクも。
だからこそ、困ったらプロに相談することも大切です。
造園業者や植木屋さんに頼めば、木の状態や環境を踏まえたベストな支柱の立て方を提案してもらえます。
プロならではのノウハウや道具を使って施工してもらえるので、安心して庭木を育てることができます。
「植木支柱は目的を理解して正しく行うこと」「小さめの庭木ならDIYでもOK、でも難しいときはプロに頼むのがおすすめ」です。
木の健康と美しい樹形を守るには、適切な支柱のやり方が欠かせません。
ぜひ植木支柱の立て方とポイントを活かして、自分に合った方法を選びながら庭づくりを楽しんでみてください。

愛知県稲沢市生まれ。稲沢市が「日本四大植木産地」であることもあり、幼少期から植木に囲まれて成長。
東京農業大学卒業後、名古屋市内の造園会社に就職。公園の整備工事から国交省事業の国道整備工事における土木及び街路樹等の植栽工事に現場代理人として携わる。