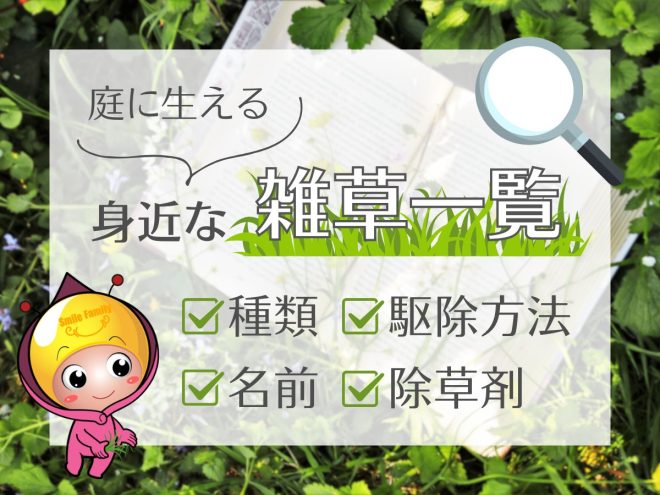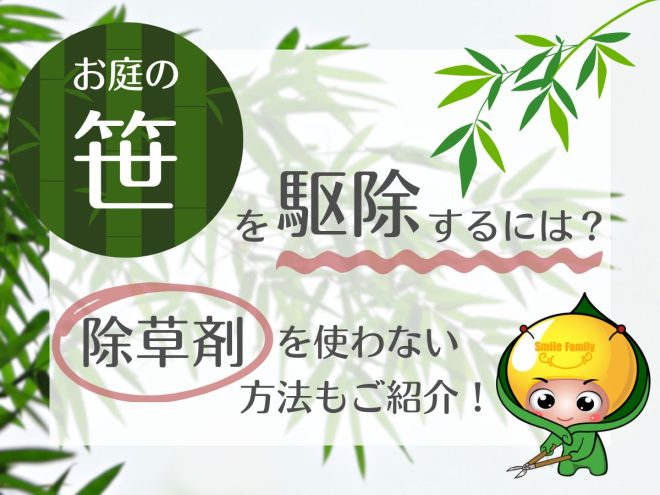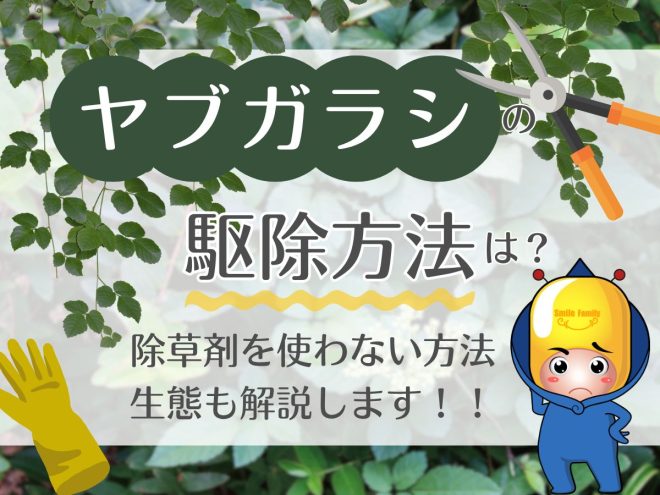お庭に生える雑草は種類が豊富で、どれも手入れが大変ですよね。
雑草の種類や特徴によって、適切な駆除方法も異なるため、どの方法を選べばいいのか迷ってしまうことも。
また、雑草によっては地中ある茎である地下茎や根が深いものもあるため、草むしりだけでは完全に取り除くことが難しいケースもあります。
しかし、各雑草に合わせた除草対策を行うことで、被害を小さくすることができ、庭の景観を美しく保つことができます。
今回は、お庭によく見られる代表的な雑草22種類を写真付きで紹介!
スギナやドクダミなど、それぞれの特徴や効果的な駆除方法について詳しく解説します。
雑草ごとの駆除方法やおすすめの除草グッズも紹介するので、どの雑草にも対応できる策を見つけられるはずです。
ぜひ、お庭に生えている雑草の種類を確認し、それぞれに合った駆除方法を試してみてください!
雑草が生えない庭は害虫を防げるって知っていますか?
雑草シーズン到来前に、お得に雑草対策ができる方法をプロが解説します。
 目次
目次
雑草の定義とは

お庭を手入れしている人にはもはやおなじみの存在といってもいいであろう雑草ですが、じつはよくよく考えた時に「何を根拠に雑草といっているんだろう?」と疑問に思うこともあるのではないでしょうか。
雑草の定義とは、広義のものでは「管理者の意図とは別に勝手に生えてきたもの」とされています。
資料元:農文協の会員制データベース「ルーラル電子図書館」より
つまり、お庭の持ち主が望んでもいないのに気づいたら生えている植物は雑草という認識になるのです。たとえ生えてきたものにかわいらしいお花が咲いたとしても、お庭の持ち主が「要らない」と感じたらそれは邪魔者以外の何物でもありません。では、勝手に生えてきた植物たちが「ああ、この生えてきた草、邪魔だなぁ」と感じる原因になりやすいのはどういった点があるからなのでしょうか?
雑草と呼ばれる理由①|繁殖力が強い
雑草と呼ばれるものの多くは、とても繁殖力が強いと言われています。特に地下茎を使って個体を増やすタイプの植物はものすごい勢いで生長していくため、増えていくスピードに対応できず手入れを渋っているうちにあっという間にお庭の植物生態を壊してしまうのです。
気付いたら大量に生えているので、草刈をするにも大変な労力が必要に。お庭のこまめな手入れが難しい人にとっては、雑草は憎き敵になってしまいます。
雑草と呼ばれる理由②|お庭のデザインを壊す
雑草には広範囲に広がって繁殖するタイプ、背丈が高くなるタイプなど様々あります。お話した繁殖力の強さゆえに、お庭の持ち主にとって想定外の育ち方をしてしまいます。お庭に自分が植えた植物以外のものを見つけたときは早めの処置が必要です。
このように、雑草と呼ばれる種類の植物は生長をコントロールするのが難しいため、魅力的なお庭作りをおこなうためには適切な生やさないための対策や駆除をおこなう必要があります。では一体どのような雑草対策や駆除をおこなう必要があるのでしょうか?今回はよく生える雑草をタイプごとに紹介し、それぞれの雑草に適した駆除方法を紹介します。
雑草の駆除方法・対策
雑草は一度生えると繁殖力が強く、駆除が難しい厄介者です。
どれだけ丁寧に草むしりをしても、またすぐに新たな芽が出てきてしまい、庭全体を覆ってしまうことも。
正しい雑草の駆除方法を知っておくことで、次に新しく生えてくるまでの期間を延ばしたり、二度と生えないようにしたりすることができます。
ここでは、手軽にできる草むしりから、根までしっかり取り除ける方法、さらに除草剤を使った効果的な対策まで、雑草駆除の具体的な方法を詳しく解説します。
雑草が生えない庭は害虫を防げるって知っていますか?
雑草シーズン到来前に、お得に雑草対策ができる方法をプロが解説します。
草むしり
雑草を駆除する最も基本的な方法が「草むしり」です。
特に地表に出ている雑草を手で一つずつ引き抜く作業は、雑草対策の中でも手軽に始められる方法の一つです。
しかし、表面の葉や茎だけを取るだけでは根が残ってしまい、また新しい芽がすぐに生えてきてしまうことも。
草むしりを効果的に行うためには、根ごとしっかりと引き抜くことが大切です。
また雑草の種類によっては、根が深く張るものや、地下茎で広がるものもあります。
こうした雑草には、雨上がりのタイミングなど、土がやわらかい状態のときに草むしりを行うと、比較的力を加えずに根まで取り除くことが可能です。
特にドクダミやスギナのような地下茎を持つ雑草は、根が残ると再生しやすいため、慎重に掘り起こしながら作業を進めましょう。
ただし、草むしりは手軽で費用もかからない反面、根までしっかり取り除かないと効果が薄れてしまう場合もあります。
根が浅い雑草には効果的ですが、根深い種類にはほかの対策と併用して行うといいかもしれません。
根っこから引き抜く
雑草を完全に駆除するためには、根っこからしっかりと引き抜くことが必要です。
表面の茎や葉だけを取り除いても、根が残っていると再び芽が出てきてしまい、完璧に駆除することはできません。
地下茎を持つ雑草や根が深く張る種類では、根を残さずに全て取り除くことが長期的な雑草対策につながります。
根っこから雑草を引き抜くときには、まず土がやわらかくなっているタイミングを狙って行うのがポイント。
雨上がりや水やりの後など、土が湿っているときは、根までしっかり引き抜きやすくなります。
硬い土壌の場合は、スコップやフォークを使って土をほぐしながら作業を進めるといいです。
特に、スギナやドクダミのような地下茎を持つ雑草は、地下茎が少しでも残っていると再生するため、丁寧に掘り返して根ごと除去します。
作業中に根が切れないよう注意し、時間をかけて丁寧に作業しましょう。
草刈り
広範囲に雑草が生い茂っている場合は、草刈りで除草するのがおすすめです。
手作業での草むしりは時間がかかるので、草刈り機を使って一気に雑草を刈り取ることで、労力を大幅に減らし、見た目もすぐに整えることができます。
ただし、草刈りは表面の雑草を刈り取るだけで、根や地下茎は残ったままになるため、再び芽が出てくる場合も。
特に、スギナやドクダミのような地下茎で繁殖する雑草は、草刈りを行った後にもすぐに新しい芽を出してしまうことが多いため、定期的な草刈りやほかの対策を併用することが必要です。
根の深い雑草には、刈り取った後に除草剤を使うなど、追加の対策を行うのがおすすめです。
また草刈りを行うときは、刈る高さを調整し、根元に近い部分で刈り取ると再生までの時間を長くすることができますよ。
除草剤
雑草を効率駆除したい場合は、除草剤の使用を検討するのもいいです。
特に、根が深く張る雑草や広範囲に繁茂する雑草に対しては、手作業では限界があるため、除草剤を活用することで労力を大幅に軽減できます。
また除草剤にはいくつかの種類があり、それぞれの雑草のタイプや用途に応じて適切なものを選ぶことが大切です。
芝生など特定の植物を傷つけずに雑草のみを枯らす「選択性除草剤」は、庭に芝生を植えている場合に適しています。
一方、非選択性除草剤は広範囲に使用でき、地表にあるすべての植物を枯らすため、庭木や芝生が生えた場所には使用できません。
例えば、グリホサート系の除草剤は根まで浸透し、地下茎を持つ雑草にも効果的です。
使用するときは、雑草の種類に応じた除草剤を選び、適切な時期に散布することがポイント。
効果を最大限に引き出すために、雨が降る前や風が強い日は避け、晴天の日に作業しましょう。
雑草をタイプ別に分類
雑草を効率的に駆除するためには、その種類や特性を理解することがポイント。
雑草にはさまざまな種類があり、それぞれ生長する環境や駆除の難易度、必要な対策が異なります。
タイプ別に分類することで、最適な駆除方法を選びやすくなり、無駄な労力や時間を省くことが可能です。
たとえば、地下茎で広がる雑草と、種で増える雑草では駆除の仕方が大きく異なります。
それを理解せずに一つの方法だけで対処しようとすると、効果が十分に発揮されないことも。
根が深く張る雑草には、地面まで浸透する除草剤を使う必要があり、浅く根を張る雑草なら、手作業で簡単に取り除ける場合もあります。
また、繁殖力の強い雑草や多年草には、継続的な対策が必要です。
雑草を種類別に把握することで、作業の優先順位や駆除方法を適切に計画できるようになるでしょう。
さらに、季節ごとに生える雑草や、庭の環境によっては特定の種類が生えやすい場合もあります。
そだぞれの特徴を踏まえた分類を行えば、予防策を講じることも可能です。
雑草が繁茂する前に対策を取ることで、庭の美観や植物の健やかな生長を守ることができます。
雑草タイプ①|背が高い雑草
雑草といわれるものの中でも、とくに扱いに困るのが背丈が高く生長する雑草です。大きく育ってしまうので、お庭の景観を著しく損ねてしまいます。芝生の中に生えてきてしまうものなら、見た目も悪くなるわ歩きにくいわで困ったことに……。
他にも、背が高い雑草が庭で繁殖すると周囲に日陰ができ、ほかの植物の生育に悪影響を与えることもあります。住宅の窓に光が入らなくなったり、風通しが悪くなったりという弊害もあるため、大きくなる前に対処しましょう。
この章では、背が高くなる雑草の中でも代表的な2種類を詳しくご紹介していきます。
オオアレチノギク

キク科の植物であるオオアレチノギクは、日本の本州以南に繁殖が確認されている特定外来種植物です。日本の侵略的外来種ワースト100にも選出されているほどの繁殖力の高さを誇っています。高さ1m~1.8mほどまで大きくなるので、お庭に生えてきてしまうと景観を損ねやすい植物の代表格です。
オオアレチノギクの厄介なところは、荒地から畑、果樹園や牧草地、道端に至るまでありとあらゆる環境に適正があるためしぶとく生えてくるところ。土壌の性質に適応して元気に生えてくるので、本当に育てたい植物を押しのけて増えてしまうおそれが高くなってしまいます。
オオアレチノギクが生えてきているのを見つけたら、早めの処理が大切です。
オオアレチノギクの駆除方法・対策
冠毛のある種を飛ばして繁殖していくため、種ができる夏前までに駆除してしまうのがベストです。
オオアレチノギクは、秋に発芽したものがロゼットで越冬します。秋冬の間に手やカマでロゼットを抜いてしまえば、しっかりと駆除することができます。
もちろん、除草剤を使ってオオアレチノギクを駆除することも可能です。オオアレチノギクは1年草なので、ロゼットの状態のときに葉や茎を枯らす葉茎処理剤を振りかけておくとしっかりと駆除することができますよ。
ただし、現在ではオオアレチノギクは雑草に効きがいいとされるグリホサート系の非選択性除草剤に対する耐性が出来ている個体があります。オオアレチノギクを除草剤で駆除する場合は、パラコート系の成分の入った非選択性除草剤、もしくはグリホサート系より効果の強いグリホシネート系の非選択性除草剤を使用しましょう。
オオアレチノギクを駆除するオススメの除草剤
オオアレチノギクを枯らすには、除草剤の成分をしっかりとチェックしておくことが大切です。そこで、オオアレチノギク駆除に効く、おすすめの駆除剤をご紹介します。
バスタ
ザクサ
バスタはグリホシネート系の非選択性除草剤です。オオアレチノギクも、葉っぱ部分に振りかけておけばしっかりと枯れさせて駆除してくれます。オオアレチノギクの駆除で使用する場合は、ロゼットの状態の時期から20cm~30cmくらいまでに生長した頃に原液を200倍に薄めて使ってください。
ザクサも、バスタと同じくグリホシネート系の非選択性除草剤です。100倍~200倍程度に希釈した状態で、ロゼット状態もしくは20cm~30cm程度に生長してオオアレチノギクに頒布して使用してください。
使用の際の注意点
今回ご紹介しているバスタ、ザクサは非選択性の除草剤です。この除草剤がかかった植物は、枯渇効果が見られるものに関しては全て枯れてしまいます。間違えて残したい植物にまでかかってしまうとオオアレチノギクと一緒に枯らしてしまうおそれがあるので、使用するときはオオアレチノギクのみに頒布することがポイントです。
セイタカアワダチソウ

セイタカアワダチソウは、1950年代ごろに日本各地で急増した外来種の雑草です。大人の身長を優に越える2.5mほどまで大きくなることもあるので、お庭に生えてしまうと荒れたお庭に見えてしまうことも少なくないでしょう。
セイタカアワダチソウが雑草として扱われてしまう大きな理由が繁殖力の強さです。作られる種の数が多く、1つ生えるとものすごい数で増えていきます。また、種だけでなく地下茎でも増えていくのも繁殖力が莫大になる大きな理由の1つ。セイタカアワダチソウの駆除は、すさまじい繁殖力との闘いといってもいいかもしれません。
また、セイタカアワダチソウは生長するにつれてアレロパシー物質という他の植物の生長を阻害する物質を放出するようになります。一度セイタカアワダチソウが庭に生えてしまうと、他の植物を植えたくてもちゃんと育たずに気づいたらセイタカアワダチソウまみれに……なんてことにもなりかねない状態になってしまうので要注意。お庭の植物たちを守るためにも、セイタカアワダチソウを見つけたらなるべく早く駆除してしまいましょう。
セイタカアワダチソウの駆除方法・対策
セイタカアワダチソウの駆除は、個体数が少ないうちに少しでも早く行いましょう。草刈や草むしりでは地下茎が残ってしまうので、繁殖力に太刀打ちすることが難しくまた生えてきてしまいます。根気よく定期的に草刈をすることが難しい場合は、除草剤を使用して地下茎を枯死させ全滅させる方法がおすすめです。
駆除剤を効果的に使う方法は以下通りです。
セイタカアワダチソウの駆除は、地下茎根絶に向けた根気勝負です。時間もかかりますが、しっかりと地下茎ごと駆除してしまいましょう!
セイタカアワダチソウを駆除するオススメの除草剤
セイタカアワダチソウを駆除する場合、葉茎駆除剤と土壌処理剤の併用が最も効果を得られます。この項では、入手しやすく使用しやすいおすすめの葉茎処理剤・土壌処理剤を紹介します。どれもセイタカアワダチソウの駆除に効果が高いことが知られていますので、是非活用してみてください。
おすすめの葉茎処理剤
まずはおすすめの葉茎処理剤からご紹介します。
サンフーロン
サンフーロンは、グリホサート系の葉茎除草剤です。葉や茎に吹きかけることで地上部を枯らせ、地下茎まで栄養を届けなくさせて枯渇させます。地下茎のある植物には、100倍希釈での使用が推奨されているので、用法を守って使用してくださいね。
おすすめの土壌処理剤
次に、とどめの地下茎対策で使う土壌処理剤の紹介です。
除草王
除草王は、顆粒タイプの土壌処理剤です。葉茎処理剤を使ってセイタカアワダチソウを地下茎まで枯死させたあと、除草王を撒いて再びセイタカアワダチソウが生えてくるのを予防します。撒く時は、雨が降らない晴天にしてくださいね!
雑草タイプ②|つる性の雑草
つる性の植物は、繁殖力の高さと増えたときのうっとうしさから雑草の代名詞として扱われることも多いです。フェンスや周りの植物に絡みつきながら大きくなっていき、そのまま放置すると草に建物が覆われてうっそうとした印象を与えることになってしまいます。絡みついたつるを一つひとつ取り除くのは大変なので、生えてきているのを見つけたら早めの処置が大切です。
この章では、駆除が大変だと言われているつる性の植物を2種類ご紹介します。
ヤブガラシ

ヤブガラシは、つる性の雑草のなかでも特に厄介な植物です。つる性の茎と巻きひげを伸ばし、ほかの植物に巻きつきながら繁殖します。ヤブガラシという名前は、ほかの植物(ヤブ)を覆い枯らしてしまうことから付けられました。
ヤブガラシを放置するとものすごい勢いで繁殖するだけでなく、花の蜜を求めてスズメバチなどが巣をつくるなど日々の生活の中で危険が増えるおそれもあります。害虫被害を避けるためにも、ヤブガラシの繁殖はできる限り早期の段階で根絶やしにしてしまいましょう。
ヤブガラシは多年生植物のため、地下茎が残っていると地上に見えている葉や茎が無くなっていたとしても翌年には再び生えてきます。ヤブガラシの駆除をするときには、しっかりと地下茎まで枯らすことがポイントです。
ヤブガラシの駆除方法・対策
ヤブガラシを根絶するのは、その繁殖力からかなり難しいと言われています。根っこや茎部分が少しでも残っていると再び生えてきてしまうので、ヤブガラシの駆除は手で全て刈り取るよりも葉茎処理剤を複数回使用して根っこまで枯らしましょう。
ヤブガラシを根っこまで枯らすためには、以下の手順で葉茎処理剤を使用します。
葉茎処理剤を使用するときは、刷毛を使用して1枚1枚丁寧に葉っぱに手塗をすると他の植物にかからずヤブガラシのみを枯死させることができますよ。
ヤブガラシを駆除するオススメの除草剤
ヤブガラシの駆除には、葉茎処理剤が最も適しています。特に、グリホサート系(カリウム塩液剤)はヤブガラシの地下茎までしっかり枯死させてくれるので葉茎処理剤を選ぶときはグリホサート系のものを選ぶようにしましょう。
ラウンドアップ・マックスロード
ラウンドアップ・マックスロードALⅢは、グリホサート系の葉茎処理剤でも比較的使いやすいものになります。ラウンドアップシリーズの中でも駆除成分が強く、しっかりとヤブガラシを駆除してくれます。ラウンドアップ・マックスロードALⅢを使うときは、液剤を薄めずにそのままヤブガラシに塗り付けてくださいね。早ければ翌日には枯れ始めますよ。
カラスノエンドウ(ヤハズノエンドウ)

カラスノエンドウは、初春から夏にかけて旺盛に生育するマメ科の雑草です。カラスノエンドウが雑草として扱われることが多い理由は、沢山出来て四方八方に飛び散る種の存在があるからと言われています。カラスノエンドウの種は麦などの種と大きさが似ている為、混ざりこんでしまったときに選り分けるのが難しいのです。そのため、麦を育てる農家にとって厄介な雑草という位置づけをされるようになりました。
また、飛び散る種によって爆発的に増えていくのも、カラスノエンドウが厄介な理由の1つです。つると巻きひげでフェンスなどに絡みつき、放っておくとフェンスや壁全体がカラスノエンドウで覆われてしまうことも。可愛らしい花を咲かせるカラスノエンドウですが、旺盛に生長していくのでつるまみれになるのを避けたい時は早めの駆除をおすすめします。
カラスノエンドウの駆除方法・対策
カラスノエンドウは種を飛ばして増えるため、種が飛散しても生長を防げる土壌処理剤と既に生えている葉茎を枯らす葉茎処理剤を併用する方法が一番確実に駆除することができます。カラスノエンドウそのものは根も深くなく比較的駆除しやすい雑草ではあるので、沢山の種が発芽しないような土壌に改良してしまうことで生えてこなくなりますよ。
カラスノエンドウの駆除手順は以下の通りです。
カラスノエンドウの駆除のポイントは発芽対策です。生えてしまったあとの草部分の駆除はそう難しくないので、土壌処理剤をうまく活用してくださいね。
雑草タイプ③|イネ科の雑草
日本には非常に多くのイネ科の雑草が存在します。繁殖力が強いうえ、薬剤に耐性のある種類も多いため、「イネ科に効果的」と表記されている除草剤を選んでください。
スズメノカタビラ

スズメノカタビラは、踏みつけに強く、庭の芝生をはじめ公園やゴルフ場などでもよく見られます。小さなうちは葉が芝生と見分けにくく、発見しづらいのも厄介なポイントです。
種で増えるため、結実しないうちに対処してください。イネ科の雑草に有効な除草剤を選びましょう。芝生に生えているスズメノカタビラには、芝生は枯らさずに雑草を駆除できる選択性の除草剤が最適です。
「芝生は枯らさずに、雑草を駆除できる除草剤を自分でまくのは怖い。」
「芝生が枯れてしまいそうで不安だな。」という方は、プロに相談するのもいいかもしれません。
雑草が生えない庭は害虫を防げるって知っていますか?
雑草シーズン到来前に、お得に雑草対策ができる方法をプロが解説します。
スズメノカタビラの駆除方法・対策
芝生や庭の空間に生えやすく、繁殖力がとてもに強いスズメノカタビラは、春先の3月から初夏の6月ごろにかけて活発に生長します。
踏みつけられても簡単に枯れないため、広い面積にわたって雑草が広がることが多いのが特徴です。
根が浅く、踏まれても強いので、気づいたら広がってしまうことも。
早めの対策が効果的で、適切な方法を選ばないと芝生と区別がつきにくいため、除草作業が難しくなることもあります。
まず、根が浅いため比較的簡単に引き抜けるため、少量の場合は手作業でスズメノカタビラを引き抜くといいです。
ただし、種で増殖するため、取り残しがあると再び広がってしまう場合も。
手作業での駆除だけでは限界があるので、選択性の除草剤を使って効果的に駆除するのもおすすめです。
エノコログサ

エノコログサは「猫じゃらし」とも呼ばれるフワフワの穂が目立つ雑草です。庭や空き地でよく見られ、夏から秋にかけて種で増殖します。
繁殖力の旺盛なエノコログサですが、根が浅いため手で簡単に抜けます。比較的駆除が容易な雑草と言えるでしょう。除草剤を使う場合は、イネ科の雑草に特化した薬剤がおすすめです。
エノコログサの駆除方法・対策
初夏の6月から秋の10月ごろにかけて、よく見かけるようになるエノコログサ。
根が浅いため比較的簡単に引き抜ける一方で、繁殖力が強く、気を抜くとすぐに庭全体に広がってしまう厄介な存在です。
エノコログサは種で増えるため、花芽を付ける前にしっかり管理することで、再発を防ぎ、美しい庭を保つことができます。
雑草タイプ④|地下茎のある雑草
地下茎(ちかけい)とは、地下に伸びた茎のこと。
地表に出ている部分を刈っても、地下茎が残っているとまた芽が出てきます。多くの雑草が地下茎を持ちますが、今回は特に地下茎で増えやすい雑草を紹介します。
ドクダミ

ドクダミは、地下茎で増える雑草の代表種です。葉や茎には独特のにおいがあり、生薬や茶葉としても利用されています。
ドクダミの地下茎は、横に伸びる性質があり、広範囲に群生します。完全に根絶するためには土を深く掘り返して根を取り除く必要があります。株が小さいうちに抜き取るか、根まで浸透する除草剤を利用するのがおすすめです。
ドクダミの駆除方法・対策
独特なにおいと白い花が特徴のドクダミは、6月から9月にかけて庭や畑でよく見かけるようになります。
地下茎でどんどん広がるため、放っておくと庭全体を覆い尽くしてしまうことも。
コンクリートの割れた隙間でも生え、取り除いてもしつこいほど再び生える強い生命力があります。
また地下茎が強く、簡単に引き抜けないため、根本的な対策が必要です。
スギナ

トクサ科の雑草であるスギナは、地下茎を広範囲まで伸ばして繁殖します。スギナの地下茎は生命力が強く、中途半端に掘り起こしても、地中に残った根から再生します。
薬剤が効きにくい強い雑草でもあるため「スギナにも効果が期待できる」と明記された除草剤を選んでください。
スギナの駆除方法・対策
スギナは、4月から7月にかけて勢いよく生長する厄介な雑草です。
地下茎が深く広がり、ふさふさのやわらかい見た目よりも強力な生命力を持っているため、表面を刈り取っただけではすぐに再生してしまうことも。
手作業だけで駆除するのは難しいため、除草剤を使った、確実な対策が必要です。
地下茎が残らないように根までしっかり取り除くことが、再生を防ぐためのポイントです。
雑草タイプ⑤|北海道など寒い地域に生える雑草
北海道などの寒い地域でも旺盛に生育する、耐寒性のある雑草を紹介します。
ブタナ

ブタナは、日本では北海道の札幌市で初めて発見された外来種の雑草です。セイヨウタンポポの花に似た小さな花を付けることから「タンポポモドキ」と呼ばれることも。
北海道など寒い地域をはじめとし、日本全国に分布しています。ロゼットで冬を越すため、発見したら手や除草用のカマで根ごと抜き取ってしまいましょう。除草剤を使うなら、根まで枯らせるタイプが最適です。
ブタナの駆除方法・対策
5月から10月にかけて黄色い花を咲かせるブタナ。
セイヨウタンポポに似た見た目からタンポポモドキとも呼ばれることもありますが、地下茎で増えるため、繁殖力がとても強いのが特徴です。
特に北海道では、広がりやすい雑草として知られ、見た目はかわいらしいですが、放っておくとどんどん増える厄介な雑草です。
ブタナの駆除には、早期発見と根までしっかり取り除くことが重要です。
手作業と除草剤を組み合わせて、効率よく駆除を進めましょう。
雑草タイプ⑥|根が深い雑草
根を深く張る雑草は、手やカマでは抜き取ることができず、駆除が大変です。
重機で土を掘り起こさないと根絶できないケースもあります。
ササ

ササ(笹)は、地下に根を伸ばして増殖するイネ科の植物です。ササの根は木のように硬く、手や除草用のカマなどでは容易に切ったり抜いたりすることができません。
ササの対策には、地中の根までしっかり浸透するタイプの除草剤が有効です。
ササの駆除方法・対策
ササは地下茎で増えるため、一度根を張ると広範囲に広がりやすい雑草です。
地上部分を刈っても地下茎が残っていると再び芽を出すため、根本から処理しましょう。
特に春の4月から夏の7月にかけて生長が早いため、早めに対処することが大切です。
少ししでも地下茎が残ると再生しやすいので1〜2か月ごとに庭をチェックし、再発の兆しがあれば早めに取り除くことがポイントです。
基本にササの駆除には手作業での掘り起こしと除草剤の併用が効果的で、地下茎を残さず取り除き、再発を防ぐために定期的な管理が大切です。
雑草タイプ⑦|家庭菜園でよく見かける雑草
家庭菜園の畑によく生える代表的な雑草を紹介します。
食べる作物を栽培する家庭菜園の畑では、「非農耕地用除草剤」や、農薬取締法に該当しない「無登録の除草剤」は使用しないようにしましょう。
ハマスゲ(コウブシ)

ハマスゲは、畑や海岸付近でよく見られるカヤツリグサ科の雑草です。生命力が強く、芝生に生えると芝生を枯らすほど増殖してしまうこともあります。
地下茎で増えるため、ハマスゲの駆除には根まで浸透するグリホサート系などの除草剤が役立ちます。
ハマスゲ(コウブシ)の駆除方法・対策
地下に球根のような地下茎を持つハマスゲ(コウブシ)。
地下茎から繁殖するため、表面の草を刈り取るだけでは駆除が難しいのが特徴です。
特に夏の6月〜8月ごろにかけて生長が活発になるため、この時期にしっかりと対策を行うことがポイント。
基本的にハマスゲの駆除は地下茎までしっかり取り除くことが肝心です。
手作業と除草剤を併用して、再発を防ぐための定期的な管理が効果的です。
コニシキソウ

葉の黒い斑点模様が目印のコニシキソウは、地面を這うように茎を伸ばす雑草です。畑や空き地でよく見られます。
コニシキソウの根はそれほど強くなく、株の根元をつかめば手で抜くことができます。ただし、広範囲に繁殖したものは薬剤で対処するのがおすすめです。
コニシキソウの駆除方法・対策
特徴的な黒い斑点が葉に現れることが多く、地面を這うように広がって増えるコニシキソウ。
主に7月〜9月にかけて庭や空き地でよく見かけることが多くなり、気づいた時には広範囲に繁殖してしまうことも。
手作業で簡単に抜けるものの、繁殖力が強いため、早めの対策が必要です。
コニシキソウの駆除には手作業での草むしりが有効ですが、広範囲に広がる場合は選択性の除草剤との併用がおすすめです。
また再発を防ぐためには、早めの除草剤散布が欠かせません。
雑草タイプ⑧|薬剤が効きにくい強い雑草
薬剤に耐性があり、効果が出にくい雑草もあります。薬剤が効かない雑草には塩をまくのが有効とする説もありますが、塩は土壌中で分解されないため安易に使用するのはおすすめできません。住宅基礎に悪影響を及ぼしたり、その場所で何年も植物が育たなくなったりする可能性があります。
オヒシバ

イネ科雑草のオヒシバは、生命力が強く、薬剤の効きにくい雑草の代表格です。踏みつけにも負けないため、子供が遊ぶ庭やグラウンドでもよく繁殖します。
除草剤が効きにくいオヒシバですが、根がしっかりと張っているため手やカマでの除草も困難です。根まで浸透する強力な除草剤を選び、効果を最大限に発揮させるために定められた用法・用量を守って使用してみてください。
オヒシバの駆除方法・対策
踏まれても強く、周りへと広がりやすいオヒシバは、6月から9月ごろにかけて細長い葉と茎を伸ばします。
駐車場など身近な場所に生えていることも多いですが、畑や水田、河原などにも生え、農業をする方にとっても厄介なイネ科の雑草です。
根が深く、手では引き抜きにくいのは簡単ではないため、適切な駆除方法が必要です。
オヒシバの駆除には草刈りと選択性除草剤の併用が有効です。
定期的なチェックと早めの対策で、根からしっかり取り除くことが庭を守るポイントになります。
ゼニゴケ

ゼニゴケは、湿気の多い庭や外壁、墓地などによく見られる苔です。苔の一種であるゼニゴケには、通常の雑草用の除草剤では効果が期待できません。そのため、苔専用の薬剤や、苔にも効果が見込める除草剤を選んでください。
繁殖している範囲が狭ければ、熱湯や酢水をかけて対策しても良いでしょう。湿った場所を好むので、庭の風通しを良くして繁殖を予防するのも効果的です。
ゼニゴケの駆除方法・対策
湿気の多い場所を好み、庭や駐車場、石畳などに広がりやすいゼニゴケ。
主に3月から10月にかけて繁殖しやすく、一度広がると見た目にも良くないため、早めの対策が必要です。
通常の除草剤が効きにくいため、専用の除草剤と湿気対策をするのがベスト。
手作業と除草剤を併用し、風通しを改善することで、美しい庭を維持することができますよ。
雑草タイプ⑨|虫が寄りやすい雑草
虫が好んで寄ってくる雑草を放っておくと、周りの庭木や家庭菜園で育てている作物に虫の被害が拡大することもあります。
クズ

マメ科のクズ(葛)は、ゾウムシ・カメムシ・タマムシなどの虫が付きやすい雑草です。つる性の茎を壁やフェンスに這わせながら大きく生長します。
クズは、地上に出ている部分だけを刈り取っても残った根から再生するため、薬剤で根から根絶するのが有効です。巨大化したクズには除草剤も効きにくくなるため、なるべく小さなうちに対策する必要があります。
クズの駆除方法・対策
別名カンコカズラやクズカズラと呼ばれるクズ。
つる性の雑草の中でも繁殖力が強く、2m以上のつるを伸ばし、7月から10月にかけて旺盛に生長します。
一度根を張ると、地下茎から次々に新しい芽を出し、広範囲にわたって繁茂するため、早めの対策が必要です。
放っておくと庭木やフェンスに絡みつき、景観を損なうだけでなく、ほかの植物に悪影響を与えることもあります。
クズの駆除には手作業での根の掘り起こしと除草剤の併用が効果的です。
また再発を防ぐためには、定期的な管理が必要です。
雑草が生えない庭は害虫を防げるって知っていますか?
雑草シーズン到来前に、お得に雑草対策ができる方法をプロが解説します。
カタバミ

クローバーに似た姿をしたカタバミは、シジミチョウに人気がある雑草です。シジミチョウの一種であるウラナミシジミは、エンドウマメなどのマメ科の野菜を食害する害虫でもあります。
家庭菜園を楽しむ庭でカタバミを発見した場合、すみやかに手で除草するか、薬剤を散布して対策しましょう。小さな種が遠くまではじけ飛んで増えるため、結実する前に駆除してしまいます。
カタバミの駆除方法・対策
鉢植えや花壇にも生えていることが多いカタバミ。
5月〜9月に生長し、かわいらしい黄色い花を咲かせる一方で、繁殖力が強く庭に広がりやすい雑草です。
特に種が弾けて飛び散る性質があり、あっという間に広範囲に増えてしまうため、花が咲く前に除去することが大切です。
また、地下茎も持っているため、表面だけを処理してもすぐに再生してしまう場合もあります。
カタバミの駆除は手作業での引き抜きと除草剤を併用し、再発を防ぐために種が飛ぶ前にしっかり対処しましょう。
雑草タイプ⑩|多年草
多年草の雑草は、一度根付くと毎年生長を繰り返し、庭や畑に広がりやすい厄介な存在です。
オオバコやツユクサなど、強い生命力を持つ雑草が多く、手間をかけずに駆除するのは難しいです。
放っておくと根が深く広がり、毎年繰り返し生えてくるため、早めの対策が肝心です。
ここでは多年草の代表的な雑草をとその駆除方法について解説します。
オオバコ

踏みつけられても強く育つ生命力のあるオオバコ。
庭や空き地、道端などでよく見かけ、葉が地面に広がるように生長するのが特徴です。
根が深く、抜き取りにくいのが厄介で、簡単には除草できません。
オオバコは、見た目以上に頑丈で、一度根付くと放置しておくと繁殖が進むため、早めに対処することが大切です。
また種が飛び散ることで次々と新しい株が育ち、どんどん広がる性質を持っているので、発芽する前に除草剤を散布するといいです。
オオバコの駆除方法・対策
オオバコの駆除は、根が深く強いため少し手間がかかりますが、手作業と除草剤の併用が効果的です。
4月から6月にかけて生長が早まるため、この時期に除草を行います。
手作業で引き抜くときは、根元からしっかりと掘り起こし、根を残さないようにしましょう。
土が湿っているときは、根が抜きやすくなるのでおすすめです。
カヤツリグサ

イネ科に似た見た目で、三角形の茎が地面からしゅっと真っ直ぐ伸びるカヤツリグサ。
湿った場所を好み、庭や空き地、畑などでよく見かけるカヤツリグサ科の雑草で、繁殖力が強く、地下茎で広がるため、除草が難しいことでも知られています。
手で抜くだけでは、根が残って再生することが多く、何度も取り除くことが必要です。
カヤツリグサは6月〜9月ごろに生長が早まり、背丈も高くなるため、放置するとほかの植物を枯らしてしまうこともあります。
また、湿度の高い場所で繁殖しやすく、特に水はけの悪い庭では大量に生えてしまう場合も。
地下茎が土の中で広がり、手作業で完全に取り除くのが難しいですが、根を残さずに土ごと掘り起こしたり、除草剤を使用したりする方法がおすすめです。
カヤツリグサの駆除方法・対策
カヤツリグサは地下茎で広がるため、根を残さずにしっかりと取り除くことが駆除のポイントです。
湿った場所を好み、水はけの悪い土壌では特に繁殖しやすいので、根をしっかりと除去しましょう。
手作業と除草剤を併用し、土壌の改善も取り入れながら継続的に管理していくことが大切です。
チガヤ

チガヤは、イネ科の多年草で、5月〜8月にかけて特に勢いよく生長する雑草です。
根が地下深くまで広がり、地下茎で増殖するため、手作業での除去が難しいです。
芝生にも生えやすく、さらに単体で除去するのは難しくなるため、庭の景観を悪くさせることもあるでしょう。
秋に咲く白い穂は風に揺れると趣のある姿ですが、繁殖力が強く、ほかの植物を圧倒してしまうこともあります。
放置してしまうと、広範囲にわたって根を張り、再生力も高いため、駆除には時間と労力がかかります。
チガヤの駆除方法・対策
根が地下深くまで広がり、再生力が強いため、駆除には手間がかかるチガヤ。
5月〜8月の生長期にしっかりと対応することが駆除のポイントです。
特に地下茎で広がるため、表面の草を刈るだけでは不十分なので、深い掘り起こしと除草剤の併用が必要です。
また定期的な管理を行なうことで、再発防止にもなりますよ。
ツユクサ

夏ごろになると茎の先端に青い小さな花をポツポツと咲かせるツユクサ。
見た目はかわいらしいですが、繁殖力が強く、地面をはうように広がっていく性質があるため、放っておくと庭全体を覆ってしまうことも。
茎は水分を多く含み、やわらかくて折れやすい一方で、根が浅いため、表面を刈り取っても再び芽を出しやすいのが厄介な点です。
7月〜10月に庭や道端に生えやすいツユクサは、湿った場所を好むため、雨が多い季節には繁殖が加速します。
草むしりを行っても根が残りやすく、数日後には再生してしまうことも多いです。
また、種も飛びやすく、広範囲に繁殖するため、早めの対策が大切です
除草には、定期的な草刈りと併用して、根ごと引き抜くと
地面が湿っている時期に作業を行うと、根を残さず引き抜くことができ、再発を防ぎやすくなりますよ。
ツユクサの駆除方法・対策
繁殖力が強く、根が浅い一方で、茎が折れやすく切れた部分から再生しやすいツユクサ。
主に7月〜10月にかけて生長が活発になるため、この時期に早めの対策を行うことが大切です。
基本的には手作業での引き抜きと除草剤を併用して、庭の環境を整えることがツユクサの対策となります。
ハコベ

春先から秋にかけて、地面から低い位置で丸みのある葉を展開させるハコベ。
春の七草の1つに数えられる「ハコベラ」の別名で、白い小さな星型の花が点々と咲くかわいらしい一面があります。
湿った場所や日当たりの良い場所に繁殖しやすい多年草で、根が浅く、紫の茎が絡み合うように地面を這って広がるため、庭や畑では厄介な存在といわれることも。
手で簡単に引き抜けるように見えますが、再生力が高く、根や茎の一部が残るとすぐに再び芽を出します。
放っておくと種が飛んでさらに広がり、数週間で庭一面を覆ってしまうこともあります。
特に梅雨時期など、湿度が高い時期には生長が加速しやすいので、早めの対策を行なってしっかりと根まで取り除き、継続的な管理が大切です。
ハコベの駆除方法・対策
繁殖力が強く、湿った場所や日当たりの良い庭に広がりやすいハコベは、春から梅雨時期である4月〜6月にかけて生長が早まります。
手で引き抜くことは可能ですが、茎や根が残るとすぐに再生してしまうので、根が切れないように慎重に引き抜くことがポイント。
手作業では無理なほどたくさん生えてしまっている場合は、除草剤を検討するのもいいかもしれません。
また土の水はけを良くし、湿度を下げることも再発防止につながりますよ。
ヨモギ

春から秋にかけて生長が早く、庭や畑などでよく見かけることが増える多年草のヨモギ。
強い繁殖力と地下茎で広がる性質で、地上の茎を刈り取っても、地下茎から新たに芽を出すため、手作業での除草が難しいことが多いです。
また、根が深く張るため、しっかりと根を掘り起こさないと再生してしてしまいます。
ヨモギは薬草としても利用される植物ですが、庭に広がりすぎると、ほかの植物の生長を妨げることも。
特に放っておくと根が周辺の植物の根と絡み合い、庭全体に広がることもあるので、放置せずに対処しましょう。
繁殖力・再生力の高さが駆除を難しくし、放置すればするほど範囲が広がってしまいますが、早めの対策を行うことで防ぐことができます。
根こそぎ取り除くか、除草剤を使ってしっかりと駆除するのがおすすめです。
ヨモギの駆除方法・対策
ヨモギは地下茎で広がるため、駆除には根からしっかり取り除くことがポイントです。
春から4月〜8月にかけて生長が活発になるので、この時期に早めの対策を行うと効果的です。
表面だけの草刈りでは再び芽を出してしまうため、根本的な対策が必要です。
定期的な確認と継続的な対応で、再発を防ぎましょう。
春・夏・秋・冬の代表的な雑草
春・夏・秋・冬によく見られる代表的な雑草は次の通りです。
春の代表的な雑草
スギナ・スズメノカタビラ・ブタナ・セイヨウタンポポ・ヨモギ・ホトケノザ・オオイヌノフグリ
夏の代表的な雑草
メヒシバ・オヒシバ・カタバミ・ドクダミ・コニシキソウ・ハマスゲ・ササ・ヤブガラシ・クズ・オオバコ
秋の代表的な雑草
セイタカアワダチソウ・オオアレチノギク・カヤツリグサ・エノコログサ・ススキ・アキノノゲシ・ヒメムカシヨモギ・ヒガンバナ
冬の代表的な雑草
ゼニゴケ・タネツケバナ・キク科雑草のロゼット
雑草に関するご相談はプロにお任せ!
雑草でお困りなら、全国チェーン店舗数No.1のsmileガーデンへ一度ご相談ください!
除草、草刈作業、消毒、雑草対策など、雑草除去に関する様々なお困りごとに対応しています。
お見積りは無料ですので、是非一度ご連絡ください。
雑草が生えない庭は害虫を防げるって知っていますか?
雑草シーズン到来前に、お得に雑草対策ができる方法をプロが解説します。

愛知県稲沢市生まれ。稲沢市が「日本四大植木産地」であることもあり、幼少期から植木に囲まれて成長。
東京農業大学卒業後、名古屋市内の造園会社に就職。公園の整備工事から国交省事業の国道整備工事における土木及び街路樹等の植栽工事に現場代理人として携わる。
植物が大好きなライターです。小学校の自由研究は「雑草の研究」でした。忙しい毎日でも無理なく楽しめるガーデニングを日々研究しています。雑草&野草・カラーリーフ・球根植物・100円ショップの園芸グッズ。