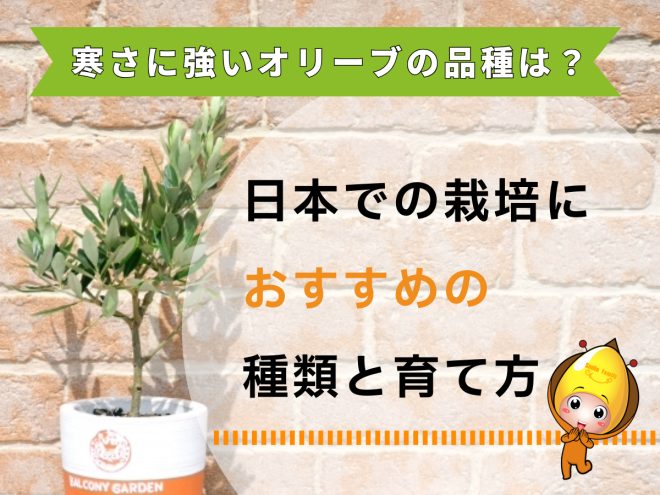みなさんは冬でも葉っぱを楽しめる常緑樹と、明るく涼しげな落葉樹、どちらが好きでしょうか?いろいろな方のお庭を見ていると、どちらも半々くらいで植えられているところが多いように感じます。ただ、落葉樹は冬の姿が寂しいとか、落ち葉の掃除が大変とか、そんなイメージを持っている方もいるかもしれません。常緑樹もとてもすてきなものですが、落葉樹にもたくさんの魅力があります。落葉樹は常緑樹とどこが違うのか、どういうメリットがあるのか、おすすめの種類はどんなものかなど、それぞれ紹介していきます。
 目次
目次
落葉樹とは?

落葉樹の見分け方
落葉樹と常緑樹は、「冬に葉っぱが落ちる」「葉っぱの質感が薄いことが多い」などの違いが挙げられます。
葉っぱを触ったり光に透かしたり、冬の姿を見たりすることで基本的には見分けることができます。
ただし、アコウなど時々思いついたように落葉する木や、シラカシやクスノキのように、常緑樹でも木が弱ると落葉する樹木もあるので注意が必要です。
また、どちらかわかりづらいものがあったり、ツツジの仲間のように、場合によっては落葉する「半落葉」というものもあったりするので、どちらかわからない場合はインターネットなどで種名を検索してみるのが手っ取り早いかもしれません。
落葉樹と常緑樹の違い
基本的には葉っぱに違いがあります。
落葉樹の葉っぱは冬までに落ち、常緑樹の葉っぱは冬でも落ちず、多くの場合数年~十数年くらいついている、というのが大きな違いです。
常緑樹の方が1つの葉っぱを何年も使うので、落葉樹よりもコストをかけた、分厚く丈夫な葉っぱになっています。
また、多くの場合落葉樹の方が常緑樹より寒さに強いです。
落葉樹が1年で葉っぱを落としてしまうのは、冬の寒さに耐えられるよう休眠するためといわれています。
落葉樹の剪定時期
落葉樹は基本的に、冬に葉っぱが落ちてから春に新しい葉っぱが芽吹くまでに剪定を行います。
葉っぱを切らない分木へのダメージが少ないので、常緑樹より安心して剪定できます。
ただし、花や実を楽しむ木の場合、次の花芽がすでにできているものもあるので注意が必要です。
種類ごとに花芽のつく場所や時期が違うので、それに合わせた剪定をするようにしましょう。
たとえばコブシの木だと秋ごろには来年咲く花芽が枝先に出ているので、それを避けた剪定をする必要があります。
落葉樹をお庭に植えるメリット

落ち葉の掃除が大変だからと敬遠されることもある落葉樹ですが、見て楽しく機能的にも嬉しいメリットがたくさんあります。
冬に休眠する落葉樹は寒さに強く、寒冷地でも植えることができます。
さらに冬は太陽の光を通すようになるので、夏は木陰をつくり、冬は庭を暖めるといった、温度調節の機能も嬉しいところです。
また、落葉樹は常緑樹よりも葉が薄いので、全体的に光をよく遠して庭が明るくなります。
他には春先の新緑や、秋の紅葉が楽しめるのも落葉樹のメリットといえるでしょう。
庭木に最適な落葉樹の種類を紹介!

一口に落葉樹といっても、花を楽しむ木から紅葉を楽しむ木まで、たくさんの種類があるので選ぶのに大変ですよね。
そこで今回は、落葉樹の中でも庭に植えるのにおすすめのものを7つ紹介します。
とても立派な大木になるものから、低木として手軽に植えられるようなものまで幅広く紹介するので、ぜひ落葉樹を庭に植える際の参考にしてみてください。
自分の理想の庭をイメージしながら、それに合わせたものを選んでみるとよいかと思います。
ケヤキ

ケヤキは街路樹でよく植えられる木ですが、庭木としてもおすすめの木です。
竹ぼうきをひっくり返したような樹形が独特で、広がりすぎず、小さすぎないちょうどいい大きさの木陰をつくりだしてくれます。
街路樹や野外で見るものは10mを超えた大きな高木が多いですが、庭木なら大きさの調節もできるので問題ありません。
むしろ、めいっぱい大きくして立派なシンボルツリーにしてしまうのもよいでしょう。
赤や黄色、オレンジとカラフルな紅葉も魅力的で、見ていて楽しいです。
植えるには少し大きめのスペースが必要ですが、おすすめの庭木です。
イロハモミジ

手のようなかわいらしい葉っぱが特徴のイロハモミジは、育てやすく庭木にもぴったりな木です。
主に紅葉を楽しむ木で、真っ赤に染まる紅葉は昔から親しまれてきました。
盆栽のような樹形も相まって、和風の庭にぴったりの木です。
病害虫の発生に少し気をつければ、特に問題なく育てることができます。
普通に紅葉を楽しむために植えてもいいし、剪定して好きな樹形に整えてもいいし、春先の樹液を使って自家製メープルシロップをつくってみても良いでしょう。
まだ余談ですが、イロハモミジの冬芽はシカのひづめにそっくりな形をしています。
植えた際にはぜひ観察してみてください。
季節に応じてとても多彩な楽しみ方ができる木です。
ヤマボウシ

ヤマボウシは常緑のものがよく植えられますが、落葉のものもとても魅力的です。
常緑のものと比べ少し花数は少ないですが、その分大きめの花をつける特徴があります。
また落葉樹ならではの紅葉もきれいで、常緑のヤマボウシとは一味違った楽しみ方ができます。
病害虫が少なく剪定もあまり気を使わなくていい木なので、育てる際にはあまり手がかかりません。
雑木の庭に植えても洋風な庭に植えてもマッチする、使いどころの多い木です。
カツラ

カツラはもともと渓流沿いや河原など湿ったところに生える木ですが、乾燥した街中でも育ちます。
萌芽力が強く、枝も乾燥していると横に広がるので、目隠しに向いている木です。
丸っこい葉っぱがかわいらしく、赤いグラデーションがきれいな新芽と、鮮やかな黄色に染まる黄葉がとてもきれいです。
落ちた葉っぱからはみたらし団子の匂いがするというおまけつき。
カツラにしかない魅力がたくさんあり、新芽から落葉まで一年中楽しめる木です。
ソメイヨシノ

ソメイヨシノは桜の仲間で、一般的に花見で使われる品種のものです。
日本中に植えられているソメイヨシノは全て接ぎ木からつくられたクローンで、全て同じ条件で同じ時期に開花します。
庭に一本植えておけばいち早く桜の開花を知ることができるし、庭で満開の桜を独り占めすることもできますよ。
公園や街路樹で植えられている桜と全く同じものが自分の庭にあると考えるととても嬉しいですね。
庭でお花を楽しみたい方はぜひ植えてみてください。
ジューンベリー

ジューンベリーは桜と同じバラ科の植物で、桜の花びらを細くしたような花を咲かすのが特徴です。
ソメイヨシノと同じで葉っぱが開く前に花が咲くので、春が来ると木全体が花の色で染められます。
また、実が食べられるのがジューンベリーの嬉しいところで、クセのない実がとてもおいしいです。
そのまま食べてもいいし、タルトなどのデザートに添えてもいいし、ジャムにしても良いでしょう。
見て楽しい食べておいしい、いろいろな楽しみ方ができる木です。
ドウダンツツジ

ドウダンツツジは季節によってそれぞれ違った姿を見せる木です。
春には芽吹きと同時に鈴のようなかわいらしい花が咲き、秋には真っ赤に紅葉します。
葉っぱもひし形のきれいな形でさわやかな印象を与えるし、冬芽もマッチ棒のようにかわいらしい姿をしています。
刈り込みにも耐えるので、庭のテイストに応じて好きな形に整えてあげるとよいでしょう。
ビジュアル的に、他にはない魅力を持っているのがドウダンツツジの特徴で、四季折々の姿を楽しむことができる木です。
ナナカマド

ナナカマドは、その鮮やかな色合いと独特な美しさで知られる落葉樹です。秋になると、その葉は鮮やかな赤やオレンジ色に変わり、眺める人々を魅了します。この木は、様々な環境に適応しやすいため、庭園や公園、都市の緑化にもよく利用されています。
ナナカマドは比較的成長が早く、適切な条件下では年に数十センチの速さで成長することがあります。また、寒さにも強く、多くの場合、厳しい冬の条件下でも生き残ることができます。この木は、日当たりが良く、水はけの良い土壌を好みますが、さまざまな土壌の条件にも適応することができ、手間がかからない点も魅力の一つです。
落葉樹には一緒に下草も植えるのがオススメ

落葉樹を植える場合、一緒に下草も植えるのがオススメです。
落葉樹は木の下が比較的明るくなるので植える種類の選択肢が増えるし、種類によっては落葉して寂しくなる冬の賑やかしにもなります。
木の雰囲気や大きさ、庭のテイストなどに合わせて、タマリュウやローズマリー、マホニアコンフューサなど、好きなものを植えてみるとよいでしょう。
庭のスペースを無駄なく使うことができるし、木の雰囲気もガラッと変わります。
ぜひ木と一緒に植えてみてください。
シンボルツリーや低木の落葉樹をお探しの方はsmileガーデンへ!
smileガーデンならお庭のお手入れ・植栽を依頼できます。
専用フォームからのお問い合わせ、またはお電話で相談可能です!
植えることはもちろん、植えた後のお手入れまでトータルで見てくれるから頼りになりますね!
見積もりは無料のようですので、まずはお気軽にお問合せしてみてはいかがでしょうか?

愛知県稲沢市生まれ。稲沢市が「日本四大植木産地」であることもあり、幼少期から植木に囲まれて成長。
東京農業大学卒業後、名古屋市内の造園会社に就職。公園の整備工事から国交省事業の国道整備工事における土木及び街路樹等の植栽工事に現場代理人として携わる。