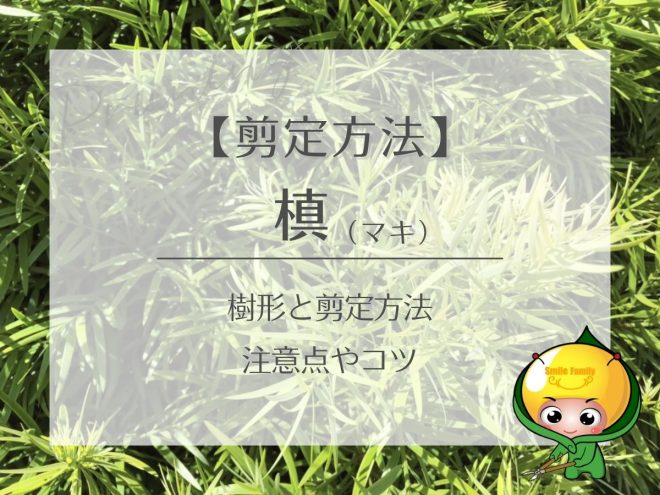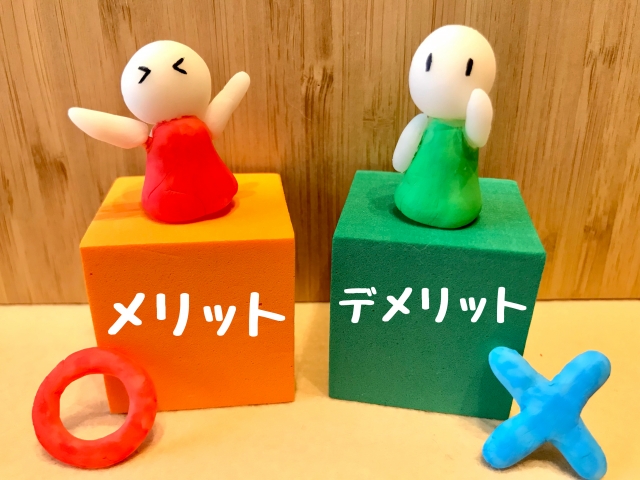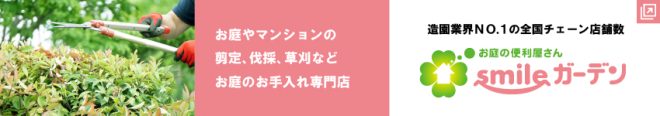マキは、イヌマキやラカンマキなどの種類がありますが比較的管理も簡単で様々な樹形に仕立てられている樹木です。
イヌマキはラカンマキに似ていますが葉の大きさはイヌマキの方が大きいです。
どのマキも魅力的な樹形を維持するためには、こまめな剪定が必要です。
ここでは、マキの管理方法について剪定時期や剪定方法も含めて、ご紹介します。
また、剪定に不安のある方や作業が面倒な方のために専門の造園業者や庭師への剪定依頼についてもご紹介していますので、ぜひ、ご参考にしてください。
関連記事はこちら⇩
マキ(槙)の木の育て方や特徴
イヌマキの育て方や特徴
 目次
目次
マキ(槙、イヌマキ、ラカンマキ)剪定の時期

マキの剪定をする上では、適切な剪定の適期・可能期で剪定を行うことが重要です。
ここでは、マキの剪定の適期・可能期について、ご紹介します。
年に2回の剪定
マキの木は、年2回ほどの剪定を目安に整えると美しい樹形を保てます。
特に生長が旺盛な時期には枝葉が広がりやすく、放置すると風通しが悪くなり、害虫が発生しやすくなることも。
剪定を適切に行うことで、枝葉がスッキリとまとまり、庭の印象も明るくなります。
基本的に伸びすぎた枝を元から切り戻したり、不要な枝を間引いたりする切り戻し・間引き剪定を行いましょう
枝先だけを軽く整えるだけでは、形が乱れてしまうため、全体のバランスを見ながら剪定をします。
また、刈り込みばさみで葉先をそろえると、玉仕立てや生垣としてもきれいに仕上がりますよ。
適期・可能期
基本的に年2回程度の剪定が必要なマキの木ですが、樹形を美しく整えたり、枝葉を健康に保つためには適期を見極めて行うことが大切です。
特に、マキの木は生長スピードがゆっくりな庭木なので、一度剪定すると形が長く維持できるのも特徴です。
剪定のタイミングを上手に選べば、剪定後に枯れる心配も少なくなり、葉や枝の勢いも保ちやすくなります。
マキの木は、夏の7〜8月にかけて新しい枝葉が伸びやすく、この時期に剪定を行うと、すっきりとした形に仕上がります。
また、冬の11〜2月は生長が緩やかになるため、余分な枝を整理しておくことで、次のシーズンに向けて準備を整えられるでしょう。
剪定可能な時期は比較的長く、多少タイミングがずれても枝葉の状態を見ながら手入れできます。
ただし、強く剪定しすぎると枝葉が弱ってしまうことがあるため、適度に切り戻すのがポイント。
マキの木は生長がゆっくりな分、形を整える作業も落ち着いて取り組めるため、初心者にも扱いやすいです。
注意時期
マキの木の剪定では、適期・可能期だけでなく、注意する時期も知っておくことが大切です。
生長期の剪定は避ける
マキの木の生長期である春から初夏にかけての剪定は避けましょう。
この時期に剪定を行うと、木が新しい枝や葉を伸ばそうとエネルギーを消費するため、負担が大きくなります。
特に若い木や新しく植えた木は、生長期に剪定すると弱りやすくなるので注意してくださいね。
梅雨時期は避ける
梅雨の時期は湿気が多く、剪定した切り口から病原菌が侵入しやすくなり、病気にかかってしまうことも。
また、雨が続くと切り口が乾燥せず、腐敗するリスクも高まります。
梅雨が明けてから剪定するほうが安心です。
極寒期や猛暑時は控える
極端に寒い時期や暑い時期も剪定には不向きです。
極寒期に剪定すると、切り口が凍結して傷が広がることもあります。
猛暑時は水分の蒸散量が多くなり、木が弱る原因になるため注意が必要です。
まきの木(槙、イヌマキ、ラカンマキ)の剪定のやり方
マキの木の剪定は、庭木の形を整えながら健康を維持するために欠かせない作業です。
剪定の仕方によって枝葉の密度や見た目が変わるため、用途に応じて方法を使い分けるといいです。
特にマキの木は、生垣やシンボルツリーとして人気があるため、バランスの良い樹形を保てるように剪定してみましょう。
基本的にマキの剪定には、大きく分けて「刈り込み剪定」と「透かし剪定」の2種類があります。
刈り込み剪定は、生垣や玉仕立てなど、葉をきれいにそろえるのに適しており、見た目を美しく仕上げられるのが特徴です。
一方、透かし剪定は、枝抜きや間引きをして風通しを良くしながら樹形を整える方法で、病害虫の予防にも効果的です。
ここでは、マキの剪定に必要な道具と刈り込み剪定・透かし剪定方法のポイントをそれぞれを詳しく紹介します。
マキの剪定に必要な道具

マキの木の剪定には、専用の道具を準備することが大切です。
基本的にそろえておきたいのは、剪定ばさみ、刈り込みばさみ、植木ばさみ、剪定用三脚、園芸用手袋の5つ。
これらを使い分けることで、剪定作業がスムーズに進みますよ。
①剪定ばさみ
細い枝ややわらかい新芽を切るのに便利です。
②刈り込みばさみ
葉を均一にそろえたり、玉仕立てや生垣として整えたりする際に役立ちます。
③植木ばさみ
太めの枝を切るときには、しっかりと握れる植木ばさみがおすすめです。
④剪定用三脚
高い位置にある枝を剪定する場合は、安定感のある剪定用三脚を使いましょう。
脚立よりも傾斜地や凸凹のある場所に設置しやすく、安全に作業ができます。
特にマキの木は、樹高が高くなる庭木なので、剪定後に枯れるリスクを避けるためにも、正確に枝を切り落とせる環境を整えることがポイントです。
⑤園芸用手袋
手をケガから守るための園芸用手袋も忘れずに準備します。
トゲや枝で手を傷つけないようにするだけでなく、剪定中のグリップ力もアップするので、細かい作業がしやすくなりますよ。
マキの木を健康的に育てるためには、道具の手入れも大切です。
剪定後はハサミの刃をきれいに拭き取り、サビや汚れを防ぎましょう。
刃の切れ味を保つことで、剪定の仕方がよりスムーズになり、庭木の負担も軽減できます。
マキの剪定方法

マキの木の剪定に必要な「刈り込み剪定」と「透かし剪定」のポイントについて、詳しくそれぞれを解説します。
「刈り込み剪定」
刈り込み剪定は、マキの木の樹形を整えながら、美しい仕上がりを保つための剪定方法です。
丸く整えた「玉ちらし」や、生垣として四角く仕立てる場合におすすめ。
枝葉が乱れてくると見た目が悪くなるため、刈り込み剪定で形をそろえて管理します。
刈り込み剪定のポイント
Point1. 樹形を仕立てる
マキの木は、玉ちらし仕立てなら丸く、生垣なら四角く整えるのが基本です。
刈り込みばさみを使って、樹形の輪郭を揃えながら剪定しましょう。
Point2. 傷んだ葉を取り除く
剪定後に傷んだ葉や枯れた葉が残ると、見た目が悪くなるだけでなく、風通しも悪くなる場合も。
剪定ばさみや植木ばさみを使って丁寧に取り除きましょう。
Point3. 最上部をしっかり整える
樹木の上部が乱れていると全体のバランスが崩れてしまいます。
最上部は特に丁寧に刈り込んで形を整えましょう。
Point4. 刈り込みは面を意識する
樹形の表面を滑らかに仕上げることで、まとまりのある印象になります。
刈り込みばさみを使い、葉先を軽く整えるだけでも形が引き締まりますよ。
Point5. 刈り込み後の手入れを忘れずに
刈り込み剪定の後は、枯れ葉や切り落とした枝を取り除きましょう。
肥料を与えることで、剪定によるストレスを軽減し、元気に育てられます。
「透かし剪定」(枝抜き、間引き剪定)
透かし剪定は、マキの木の枝を間引いて風通しや日当たりを良くするための剪定方法です。
枝葉が込み合うと、風通しが悪くなり病害虫が発生しやすくなるため、定期的に手を入れることがポイント。
枝を整理することで、マキの木が健康に育ち、樹形も自然で美しく仕上がりますよ。
透かし剪定のポイント
Point1. 不要な枝を取り除く
風通しと日当たりが良くなるように、枝が重なって混み合った部分や、内側に向かって伸びている枝を剪定ばさみで間引きます。
Point2. 枯れ枝や細い枝を整理する
枯れた枝や細く弱々しい枝は、病気の原因になりやすいため優先的に切り落としましょう。
樹木の生育を助けるためにも、不要な枝を早めに取り除くことがポイントです。
Point3. 太い枝は付け根から切る
太い枝を切るときは、枝の根元に近い部分で剪定します。
切り口を斜めにすると水が溜まりにくく、病気の予防にもつながります。
Point4. バランスを見ながら剪定する
全体の形を確認しながら、透け感を均一に整えましょう。
切りすぎると枝葉がスカスカになってしまうため、様子を見ながら少しずつ剪定するのがベスト!
Point5. 剪定後の管理を忘れずに
剪定した後は、肥料を与えることで樹勢を回復させます。
剪定による負担を和らげ、マキの木を元気に育てましょう。
マキの剪定注意点

生長スピードがゆっくりなマキの木は、一度にたくさんの枝を切りすぎてしまうと、新しい枝葉が伸びるまで時間がかかり、見た目が悪くなることもあります。
特に目隠し用に植えた生垣の場合は、剪定に失敗すると隙間ができてしまい、目隠し効果が薄れる原因にもなるので注意しましょう。
失敗しないように慎重に剪定作業を進めてくださいね。
剪定時の注意点
枝を切りすぎない
枝を一度に切りすぎると、木のバランスが崩れてしまいます。
透かし剪定では、不要な枝を間引く程度にとどめておきましょう。
刈り込み剪定では、形を整えるために表面を軽く刈るイメージで進めるのがポイント。
全体のバランスを確認する
剪定を始める前に、理想の樹形や高さを決めてから作業を行います。
遠くから木を眺めながらバランスを調整し、切りすぎを防ぎましょう。
切り口の処理を忘れない
剪定後の切り口は、乾燥や病気に弱くなることもあります。
癒合剤を塗ると、傷口の保護ができて安心です。
剪定に自信がない場合はプロに依頼する
剪定に不安があるときや、高さのある木を剪定する場合は、専門の造園業者や庭師に依頼するのもおすすめです。
マキの剪定料金は木の大きさによって異なりますが、安全に仕上げてもらえるので安心感があります。
剪定はマキの木の健康を守るためにも欠かせない作業です。
注意点をしっかり押さえながら管理を続けて、美しい庭木を長く楽しみましょう。
造園業者・庭師にマキ(槙、マキ、イヌマキ、ラカンマキ)を剪定してもらうには?

マキの剪定を自分で行うのは手間や難しさを感じることもありますが、造園業者や庭師に依頼することでその負担を軽減できます。
ここでは、自分で剪定するメリット・デメリット、造園業者や庭師に依頼する際の流れや、依頼することで得られるメリットについて詳しくご紹介します。
プロに頼むことで、美しい樹形を保ちながら木を健康的に育てることができます。
見積もりや相談を上手に活用して、自分の希望に合った剪定を実現しましょう。
自分で剪定するメリット・デメリット
自分で剪定するメリット
自分でマキの木を剪定すると、手間はかかりますがさまざまなメリットがあります。
庭木の管理を自分のペースで行えるため、樹形をこだわって整えたり、コストを抑えたりしたい方におすすめです。
メリット1. 好みの樹形に仕立てられる
自分で剪定をする最大のメリットは、マキの木を自分好みの形に仕立てられることです。
丸く仕立てる「玉ちらし」や、生垣として四角く刈り込むデザインも自由自在です。
剪定を繰り返すうちに、枝の伸び方や葉のつき方の特徴をつかめるようになり、理想の仕上がりに近づけやすくなります。
樹木の状態をじっくり観察できるのも、自分で剪定するからこその楽しみです。
メリット2. コストを抑えられる
マキの剪定料金は木の高さや状態によって変わりますが、プロに依頼すると3,000円〜10,000円程度かかることが多いです。
自分で剪定をすれば、この費用を節約できるのが大きな魅力。
剪定ばさみや刈り込みばさみなど、道具をそろえる初期費用はかかりますが、一度そろえておけば何度でも使えるのでコストパフォーマンスも良くなります。
メリット3. 自分の都合に合わせて剪定できる
自分で剪定をすれば、忙しいスケジュールの合間を縫って作業ができるのもメリットです。
プロに頼むと予約や日程調整が必要ですが、自分で行う場合は好きなタイミングで作業できます。
剪定後に枯れるのが心配なときも、こまめに様子を見ながら管理できるので安心です。
マキの木は生長がゆっくりな庭木なので、一度形を整えると長く維持しやすいのも魅力です。
剪定作業を通して庭木に愛着を持ちながら、自分だけの理想の庭づくりを楽しみましょう。
自分で剪定するデメリット
自分でマキの木を剪定する場合、手軽に取り組める反面、いくつかのデメリットもあります。
剪定の仕方を間違えると樹木を傷めたり、思い通りの仕上がりにならなかったりすることもあるので注意しましょう。
デメリット1. 樹木を傷めたり枯らしたりする可能性がある
剪定には、枝を切る位置や切り方にコツがあります。
間違った方法で剪定すると、枝の切り口から病気が発生したり、剪定後に枯れる原因になったりする場合も。
また、強く切りすぎると樹形が崩れ、回復までに時間がかかることもあります。
剪定を行うときは、樹木の特性をよく理解したうえで慎重に作業を進めましょう。
デメリット2. 仕上がりにムラが出やすい
プロに依頼した場合と比べると、自分で剪定したときは仕上がりのバランスが悪くなることがあります。
特に、生垣として育てているマキの木は形をそろえる必要があるため、刈り込みのラインが曲がってしまったり、切りすぎて隙間が空いてしまったりすることも。
仕上がりにこだわりたい場合は、何度も剪定を繰り返しながら感覚をつかむことが大切です。
デメリット3. 道具や手間、後片づけが必要になる
剪定には剪定ばさみや刈り込みばさみ、剪定用三脚などの道具を用意する必要があります。
道具をそろえるには初期費用がかかるうえに、使用後は手入れも欠かせません。
また、剪定で出た枝葉の片づけも意外と手間がかかります。
ゴミ袋にまとめて処分するほか、大きな枝の場合は自治体のルールに従って処理する必要があるため、作業後の管理までしっかり考えておきましょう。
一度失敗すると形を整えるまでに時間がかかることもあります。
剪定に自信がない場合は、プロに依頼して管理するのも安心です。
デメリットを踏まえたうえで、自分に合った方法でマキの木を育ててみてください。
マキの剪定を造園業者・庭師に頼む際の流れ

マキの木の剪定を造園業者や庭師に依頼する場合、作業がスムーズに進むように手順を確認しておくと安心です。
以下が一般的な流れです。
Step1. 業者を探して見積もりを依頼する
まずは複数の業者に見積もりを依頼しましょう。
インターネットや口コミを活用して評判の良い業者を選び、マキの木の剪定に対応しているか確認するといいです。
見積もりは無料の場合が多く、出張費もかからない業者を選ぶと安心です。
Step2. 希望や条件を伝える
見積もり時に希望する剪定の仕上がりや予算を伝えましょう。
樹形のイメージや具体的にどのくらいの高さに整えたいかを伝えると、業者側も作業内容を把握しやすくなります。
不明点があれば遠慮せず質問することが大切です。
Step3. 業者を比較して選ぶ
複数の業者の見積もりを比較し、料金やサービス内容、信頼性を確認します。
特に料金が安すぎる場合は、作業内容やアフターケアが十分かどうか注意しましょう。
剪定の経験や実績が豊富な業者を選ぶと安心です。
Step4. 作業日程を調整する
業者を選んだら、剪定作業の日程を決めます。
作業が希望通りに進むよう、事前に天候や庭の状況を確認しておきましょう。
日程が混み合う時期は早めの予約がおすすめです。
Step5. 作業後の確認とアフターケア
剪定が終わったら、仕上がりを確認します。
希望通りの樹形になっているか、不満な点がないかをチェックしましょう。
剪定後の管理方法についてアドバイスをもらうと、木を元気に育てやすくなります。
マキの剪定を造園業者・庭師に頼むメリット
メリット1. 道具や後片づけの準備が不要
専門の造園業者や庭師に依頼すれば、剪定ばさみや刈り込みばさみ、剪定用三脚などの道具を自分で用意する必要がありません。
剪定後に出た枝葉の片づけや処分も依頼できるため、作業後の掃除の手間も省けて楽です。
また、高所作業や重い枝を扱う場合でも、ケガの心配がないのも安心です。
メリット2. 剪定後に枯れる心配が少ない
プロは木の生育状態や特性を見極めて剪定を行うため、枝の切り方を間違えてマキの木を傷めたり、剪定後に枯れたりするリスクが減らせます。
仕上がりもバランス良く、美しい樹形に整えてくれるでしょう。
メリット3. 放置して伸びすぎた木でも対応できる
長く剪定をせずに枝葉が生い茂ったマキの木も、プロならきれいに仕上げられます。
自分では手に負えないほど大きく育ってしまった木や、剪定が難しい場所に植えられている木も安心して任せられます。
メリット4. 病害虫対策も依頼できる
剪定時に病気や害虫の被害が見つかった場合、適切な処理や薬剤散布も依頼できます。
木の健康を守るために、専門的なアドバイスがもらえるのもメリットです。
メリット5. 剪定以外の相談もできる
造園業者や庭師は経験豊富なので、植え替えのタイミングや肥料の選び方など、剪定以外の管理方法についても相談できます。
庭全体のバランスを考えたアドバイスも受けられるため、庭づくりにも役立ちます。
マキ(槙、マキ、イヌマキ、ラカンマキ)の剪定は最低価格保証のsmileガーデンへ
自分でマキの剪定をするのに専門知識や時間がなく道具の準備等も難しいと思ったら、最低価格保証のsmileガーデンへ依頼しましょう。
smileガーデンが選ばれる理由
- 全国展開の便利さ
smileガーデンは、造園業界No.1の全国チェーン店舗数を誇り、全国どこでも迅速で確かな品質のサービスを提供しています。
お客様の最寄りに店舗があり、庭木1本の剪定でも電話で依頼が可能で、土日も営業しているため、迅速に対応できます。 - 明瞭会計とリーズナブルな料金
smileガーデンは、全店舗が完全自社施工を行っており、余分な手数料や中間マージンがないため、料金が安く設定されています。
また、見積(出張見積)は無料で、最低価格保証を実施しており、他社より高い見積もりがあった場合は相談可能です。 - 高い技術力と信頼性
smileガーデンのスタッフの9割以上が造園経験10年以上のプロフェッショナルであり、年間20,000件以上の依頼から得た信頼と実績があります。
徹底した社員教育により、常にお客様の要望に応じた最適な方法を提案し、技術とサービスの向上に努めています。
マキの木の剪定でよくある質問

ここではマキの木の剪定に関するよくある質問について、アドバイスとともに紹介します。
マキの木を剪定後に枯れるのはなぜでしょうか?
マキの木が剪定後に枯れる原因は、剪定の仕方や管理方法に問題がある場合が多いです。
剪定後に枯れる主な理由としては、以下のポイントが考えられます。
強剪定による負担
マキの木は生長がゆっくりなため、強剪定をすると枝葉への負担が大きくなり、枯れるリスクが高まります。
一度に枝葉を切りすぎると光合成ができる葉の量が減り、木全体の活力が低下します。
剪定は少しずつ進めることが大切です。
切り口の処理不足
剪定した枝の切り口が大きすぎたり、処理を怠ると病気や害虫が侵入しやすくなることも。
切り口は癒合剤を塗って乾燥や感染を防ぐことがポイントです。
特に梅雨や湿気が多い時期はカビや腐敗が発生しやすいので注意しましょう。
根へのダメージ
根が傷んでいる場合も剪定後に枯れる原因になります。
植え替え時に根を切りすぎたり、剪定と同時に根の負担が大きくなると、水分や栄養の吸収がうまくいかずに弱ることがあります。
剪定後はたっぷり水を与え、根の負担を減らしましょう。
水分不足や過湿
剪定後は水やりの管理も重要です。
乾燥しすぎると枝葉に十分な水分が行き渡らず、枯れることがあります。
一方で、水を与えすぎると根腐れを起こす場合もあるので、土の状態を確認しながら適量の水を与えることがポイントです。
日当たりや風通しの悪さ
剪定によって枝葉の量が減ると急に日当たりや風通しが変わり、木にストレスがかかることがあります。
特に植え替え後や環境の変化に弱いマキの木は、剪定後の管理を丁寧に行なってください。
対策と管理方法
剪定後に枯れを防ぐためには、適切な剪定時期を選び、無理のない切り方をすることが大切です。
剪定後は癒合剤を塗り、水やりや肥料で栄養補給を行います。
また、枝葉の状態や土の乾燥具合をこまめにチェックして、必要に応じて対策を取りましょう。
マキの木を強剪定する時期はいつですか?
マキの木の強剪定を行う時期は、木の生長が落ち着く秋から冬にかけてがおすすめです。
特に11月から2月ごろは、樹液の流れが穏やかになり、枝葉への負担を抑えながら剪定できる時期です。
この時期に剪定することで、新しい芽が春から勢いよく伸びてきます。
そもそも強剪定とは、枝葉を大幅に切り戻して樹形を整える剪定方法です。
枝を根元から切ったり、幹を短くする作業を含むため、木にかかる負担も大きくなります。
そのため、剪定後の管理を丁寧に行うことが枯らさないためのコツです。
強剪定の注意点
①切り口を保護する
切り口が大きくなるため、癒合剤を塗って病気や害虫から守ります。
②根の負担を減らす
強剪定後は水やりや肥料を調整して、根に過度な負担がかからないように管理します。
③段階的に剪定する
いきなり大きく切り戻すと枯れるリスクが高まるため、1〜2年かけて段階的に整えるのがおすすめです。
強剪定後の管理
剪定後は日当たりと風通しを確保しながら、土の状態に注意して水やりを行います。
また、剪定によって弱った枝葉を回復させるために、春には肥料を与えて生長をサポートします。
冬場は寒さ対策として、株の周りに腐葉土やバークチップを強いてマルチングを行ったり、防寒シート貼ったりするのも効果的です。
マキの木を低くするにはどうしたら良いですか?
マキの木を低く仕立てるためには、剪定で高さを調整しながら、全体のバランスを整えることがポイントです。
特に生長がゆっくりなマキの木は、一度に切りすぎると回復までに時間がかかるため、段階的に低くするのが安心です。
剪定の手順
Step1. 理想の高さを決める
最初に木全体を見て、最終的に仕上げたい高さをイメージします。
Step2. 上から順に剪定する
上部から徐々に切り戻しながら形を整えます。枝葉の量を確認しながら、少しずつ調整するのがポイントです。
Step3. 太い枝は付け根でカット
太い枝は根元から切り、細い枝は間引きながらバランスを整えます。
Step4. 刈り込み剪定で仕上げる
最後に表面を刈り込みバサミで整えると、きれいな仕上がりになります。
注意点
剪定後に枯れるのを防ぐため、切り口に癒合剤を塗って乾燥や病気から守ります。
また、剪定後は水やりと肥料を調整し、根の負担を軽減させることが大切です。
マキの木の剪定のポイントを教えて下さい
マキの木の剪定では、樹形を整えながら健康的に育てるためにいくつかのポイントがあります。
ポイントを押さえながら剪定を進めると、美しい樹形を長く保てます。
Point1. 樹形のバランスを意識する
剪定前に木全体を確認し、理想の形を決めてから作業を始めます。
刈り込み剪定で丸く仕立てたり、生垣なら四角く整えたりする場合も、全体のバランスを意識しながら剪定します。
Point2. 切りすぎに注意する
枝葉を一度に切りすぎると木に負担がかかるため、少しずつ形を整えるのがポイントです。
特に透かし剪定では、不要な枝を間引きながら風通しと日当たりを良くします。
Point3. 剪定後の管理を忘れずに
剪定後は切り口を保護し、水やりや肥料で回復をサポートします。
また、剪定で落ちた枝葉は片づけて風通しを保つことで、病害虫の予防にもつながります。

愛知県稲沢市生まれ。稲沢市が「日本四大植木産地」であることもあり、幼少期から植木に囲まれて成長。
東京農業大学卒業後、名古屋市内の造園会社に就職。公園の整備工事から国交省事業の国道整備工事における土木及び街路樹等の植栽工事に現場代理人として携わる。