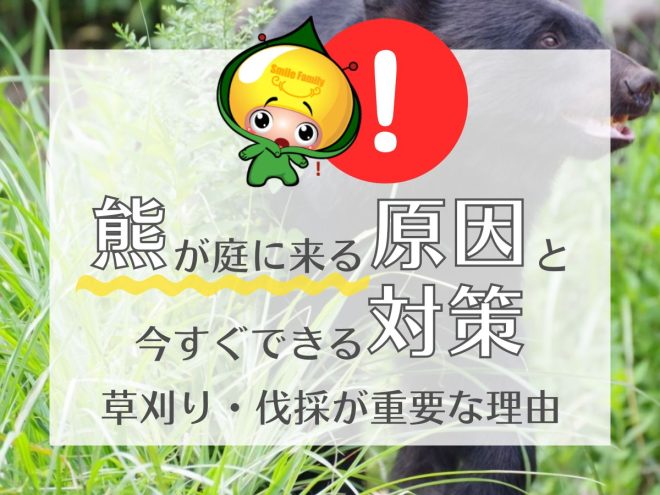庭でミカンの木を育てていると、うまく実がならないということがよくあります。できることなら、毎年たくさんのミカンを収穫したいですよね。庭で育てるミカンの木について、実がならない原因やその対策などについてご紹介します。
 目次
目次
ミカンの木に実がならない理由

ミカンの木に実がならない原因には、様々なものがあります。手入れの仕方に原因があることや、植えている場所の環境自体がミカンの生育に適していないことなど、様々です。
ミカンの木に実がならない原因について、代表的なものをご紹介します。
手入れの仕方

ミカンの木の手入れの仕方を間違っていて、実がならなくなっているのかもしれません。実がならないと、何か手をかけてあげなくてはいけないのではないかとソワソワしてしまう方もいるかもしれませんが、あれこれ手入れをしてあげたら、かえって逆効果だったという場合もあります。
逆に、放置しすぎても良くならないという場合もあります。適切な手入れをしてあげることで、ミカンの木に実がなるようになるかもしれません。
剪定のしすぎ
剪定をしすぎていたり、やり方を間違えていたりすると、実がならない可能性があります。剪定する量が多すぎると、すでにつくられていたミカンの木の花芽を落としてしまう可能性があるだけでなく、ミカンの木が光合成できる量が少なくなってしまい、実をつけるほどの栄養が貯められなくなる可能性もあります。
また、剪定しすぎると、失った枝葉を補うために徒長枝というあまり花芽をつけない枝が伸びてしまうことも多いです。もちろん、適度な剪定はミカンの木に実をつけるために必要なことではあるのですが、毎年丸坊主になるような剪定をしている場合は、見直したほうが良いかもしれません。
実をつくる養分が足りない
ミカンの木を育てるにあたって、肥料は適切にあげられているでしょうか。光合成量だけでなく、土の養分が足りないと実がならないことがあります。
土の中に微量に含まれている窒素やリンなどの養分は、植物が生育するために必要なものです。ただ大きく育つだけでなく、大きな実をつくるとなると、さらに養分が必要になります。
そのため、ただ木を生かすだけなら肥料があまり必要無くても、実をたくさんつけるためには肥料がたくさん必要になることも多いです。適切に肥料をあげられているか、確認しておきましょう。また、肥料がたくさん必要だからといってあげすぎると、かえってミカンの木を枯らしてしまう結果になることがあるので注意が必要です。
生育環境、生育状態の問題

お庭のミカンの木を植えている場所の環境や、ミカンの生育状態はどうでしょうか。生育環境が良くないと、ミカンの木もうまく育たず、実もならない可能性があります。
お庭がミカンの木にとって好ましい環境になっているか、そもそもミカンの木が充分に生育できているかなど、確認してみましょう。
実がなるまで育っていない
ミカンの木が、実をつけるほど成熟していない可能性もあります。1年生の苗木を植えると早いものでは3年ほどで実をつけるといわれています。
ただし、それは順調に育った場合のもので、環境が悪い、剪定のしすぎなどの理由でうまく育っていなければ、実をつけるにはさらに時間がかかる可能性が高いです。また、種から育てているような場合も、さらに時間がかかることが考えられます。
いずれにせよ、植えてからそれほど日が経っていなければ、いきなり実をつけることは少ないと考えておいた方が良いでしょう。
日当たりが悪すぎる
日当たりが悪いと、ミカンの木がうまく育たない可能性があります。ミカンの木は、日当たりが良く風通しの良い場所を好みます。日陰になっているような場所だと、うまく育つことができません。
他の木や建物などの遮蔽物がミカンの木の周りにあると、あまり光合成できずミカンの木が弱ったり枯れたりしてしまう可能性があります。日当たりが悪くなっている場合は、改善できないか確認してみてください。
病害虫の影響

病気や害虫によって、ミカンの木がうまく育たず実ができないという場合もあります。病気はカビや細菌など、害虫は昆虫類などが挙げられます。いずれも、ミカンの木の葉っぱや枝、実などを食べて育つものなので、被害が大きいと生育がうまくいかず、あまり成長しなかったり実がならなかったりすることも多いです。
多少発生しているくらいならあまり問題ない場合もありますが、明らかに葉っぱがかじられていたり、葉っぱに病気による斑点が大量に発生して早い時期に落葉したりしている場合は、対処したほうが良いかもしれません。
ミカンの木に出る病気
ミカンの木に発生する病気には、様々なものがあります。葉に発生するものや、枝に発生するもの、果実に発生するものと様々です。
葉に発生するものとして、「かいよう病」があります。細菌による病気で、葉だけでなく枝や果実などの表面に黄色い斑点が発生した後、表皮が破れてボロボロになるものです。病気の出た葉は落葉してしまうだけでなく、せっかく果実ができても果実にこの病気が発生してしまう可能性もあります。
キンカンやユズなどはかいよう病に強いのですが、ナツミカンなどは比較的弱いです。斑点の出たところが病原菌の越冬場所になり、風により飛んで伝染します。そのため、発生したら枝ごと切って焼却処分したり、防風垣で風から守ったりして対処しましょう。適用のある殺菌剤を散布するのも有効です。
その他に、葉や果実などに輪郭のはっきりしない黄色い斑点ができる「黄斑病」が発生することもあります。病気が多発すると落葉してミカンの木が弱ってしまうことがあるので、対処が必要です。ミカンの木の元気が無くなると発生することがあるので、肥料を適切に与えるなどして木を健康に保ちましょう。
また、発生が多い場合には5~8月の時期、発生してすぐに適用のある殺菌剤を散布して蔓延を防ぐこともできます。他にもカイガラムシやアブラムシがいると発生するすす病など、様々な病気が発生することがあります。
ミカンの木につく害虫
ミカンの木には、多くの害虫が発生します。それぞれミカンの木を食べるものですが、食べ方も葉っぱをかじるもの、葉っぱや茎の汁を吸うもの、幹を食べるものなど様々です。
葉っぱをかじるものには、アゲハチョウの仲間がよく見られます。アゲハチョウの仲間には様々な種類がいて、多くは幼虫がミカンの仲間の葉を食べますが、日当たりの良いところに植えられることの多いミカンの木には、ナミアゲハの幼虫がよく見られます。
たくさんつくと、小さい木では葉っぱを丸坊主にされてしまうこともあるので注意しましょう。直接捕殺するか、薬剤を使うことなどで対処が可能です。
葉っぱや茎の汁を吸うものでは、イセリアカイガラムシ、ツノロウムシ、カメノコロウムシなどのカイガラムシの仲間や、アオバハゴロモなどが見られます。
特にカイガラムシの仲間は、放っておくとどんどん増えてしまうので注意しましょう。カイガラムシはブラシでこそぎ落とすか、薬剤を使用するなどして対処します。他の虫に効いてもカイガラムシには効かないという薬は多くあるので、薬を選ぶ際はカイガラムシに効くものかよく確認しておきましょう。
幹を食べるものでは、ゴマダラカミキリが見られます。主に幹の根元付近などで幼虫が育ち、ミカンの木をそのまま枯らしてしまうことも少なくないです。幼虫が発生していたら、根元付近にフラス(木くずとフンが混じったもの)が出ているので、よくチェックしておきましょう。
隔年結果

ミカンの木には、実がなりやすい年と実がなりにくい年を繰り返す「隔年結果」という性質があります。「去年はたくさん実がなったのに、今年は全然実がならない」というような場合は、これが原因かもしれません。
隔年結果の性質がある理由については諸説ありますが、実がなりやすい年には花の量を抑えて、たくさん葉っぱのつく新芽を芽吹かせるようにして、実がなりにくい年にはあまり剪定せずに、実のなる枝が栄養を貯められるようにしておくなどして調整すると、隔年結果が弱まる場合があります。
放っておくと、そのまま実がなりやすい年と実がなりにくい年を繰り返すだけになってしまうので、剪定や摘果などによってコントロールしてあげるのがおすすめです。
実がなりやすいミカンの手入れの仕方

ミカンの木にたくさん実をつけるための、手入れの仕方をご紹介します。剪定や施肥などのほかに、花や果実を摘み取る摘果を行うと良い場面もあります。どんな手入れを行うと良いのか、チェックしておきましょう。
剪定
ミカンの木の剪定は、冬が終わるころから春ごろに行うのがおすすめです。骨格になる枝を決めた後、それに覆いかぶさる枝や、密になっている箇所の枝を間引くように切ります。
上に勢いよく伸びる徒長枝は、剪定などによって枝葉を失うことをきっかけに光合成量を補うために出てくる枝です。この枝には花芽がつきづらいので、根元から切ってしまいましょう。
また、樹高が高くなりすぎると剪定や収穫などが大変になってしまうので、低く抑えておくのもおすすめです。上に高く伸びる枝は、紐に重しをつけるなどして下の方に誘引してしまうという方法もあります。
隔年結果がよく出ている木では、少し剪定の時期ややり方を変えます。よく実がなりそうだという年には、花のつく量を減らすことと、新芽の芽吹きを促すために2月下旬以降の少し早めに剪定を行うのがおすすめです。やや強めに切り戻して、新芽の芽吹きを促しましょう。
今年はあまり実がならなそうだという場合は、花が咲いたのを確認してから、枝を間引いて花のつく枝に光を当てるように剪定します。上に被さっている枝や込み合っている枝を整理しますが、基本的には弱めの剪定にするのが良いです。
肥料や水のあげ方

定期的に肥料を与えるのも忘れないようにしましょう。2月から3月上旬くらいに、鶏糞や油かすなどの有機質肥料に加え、緩効性の化成肥料などを与えるのがおすすめです。また、葉の色があまりよくなかったり、よく成長できていなかったりしたら、即効性のある化成肥料などを与えます。
収穫後に、尿素を葉面に散布するのも効果的と言われています。寒すぎない時期に、薄めた尿素を数日おきに与えるようにするのがおすすめです。
水やりは、庭に地植えしてから根付く(枝が旺盛に伸びるようになるくらい)までは定期的にたっぷり水を与えるようにしましょう。根付いてからは、ミカンの木を枯らさずに育てるだけなら特に水やりの必要はありませんが、多く収穫するためには水切れを起こさないように、雨が降らない日が長く続いた場合などは定期的に水やりをするのがおすすめです。また、鉢植えで育てている場合は土が乾いたら鉢底から水が出るくらいたっぷり水やりをしましょう。
摘果など
ミカンの隔年結果を防ぐために、花や実を適度に間引くという方法があります。摘果を行うのは、栄養を少数の実に集中させて大きくするなどの目的もありますが、隔年結果を防ぐことにも役立つと言われています。
やり方としては、花が咲いている時期から咲き終わりくらいまでに、特定の枝についているつぼみや花を全て摘み取ればOKです。それによって、その枝の栄養を来年に持ち越して、来年も実ができるようになります。
ミカンの木がよく育つ生育環境

ミカンの木にたくさん実をつけるために、ミカンの木がよく育つ生育環境をつくってあげることも大切です。快適な環境をつくってあげれば、ミカンの木がよく育ち、たくさん実をつけるかもしれません。ミカンの木が好む生育環境などについてご紹介します。
ミカンの木が好む環境
ミカンの木は、日当たりが良く風通しの良い環境を好みます。日陰や、周りに他の木などが茂ってじめじめした環境はなるべく避けるようにしましょう。また、土は水はけが良く、保水力のある弱酸性くらいのものがおすすめです。
常に濡れていて雨が降るといつまでも水たまりが引かない場所や、逆にすぐに乾燥してしまうような環境は避けるようにしましょう。
また、温州ミカンの場合はpH5.5~6.2くらいが生育に適しているとされています。日本は雨が多い気候なので、月日が経つと徐々に土は酸性に傾いてきます。もちろんアルカリ性に傾きすぎてもダメですが、酸性が強くなるとミカンの木の元気がなくなる原因になるので、土の状態を見て苦土石灰などで調整してみるのもおすすめです。
病害虫対策としてできること
病害虫を未然に防ぐためにできることとしては、まず木を元気にしておくということが第一に挙げられます。自然界で弱った生き物から狩られていくように、ミカンの木も弱ってしまうと病気や害虫がつきやすくなります。木が元気でいられるような手入れをしてあげましょう。
風通しが悪いと病害虫が発生しやすくなるので、剪定時に混み合っている枝は間引いて風が通りやすくしてあげるのもおすすめです。
また、病害虫の被害を最小限に抑えるという意味では、日ごろからしっかりミカンの木を観察して、異常に気が付きやすくなっておくということも非常に大事なことです。病害虫の発生があったら、なるべく早く対処してあげることが、被害を最小限に防ぐことに繋がります。
まとめ

ミカンの木を育てて実をたくさんつけるためには、適切な手入れと環境づくりが大切です。難しそうだと思ったり、そこまで手をかける時間がないと思ったりした方もいるかもしれませんが、そうした場合はプロの業者にお願いするということもできます。
プロが作業する様子を見たり色々質問したりすると、一人で手探りで作業するよりもよほど学びがあるかもしれません。ぜひ検討してみてください。

愛知県稲沢市生まれ。稲沢市が「日本四大植木産地」であることもあり、幼少期から植木に囲まれて成長。
東京農業大学卒業後、名古屋市内の造園会社に就職。公園の整備工事から国交省事業の国道整備工事における土木及び街路樹等の植栽工事に現場代理人として携わる。