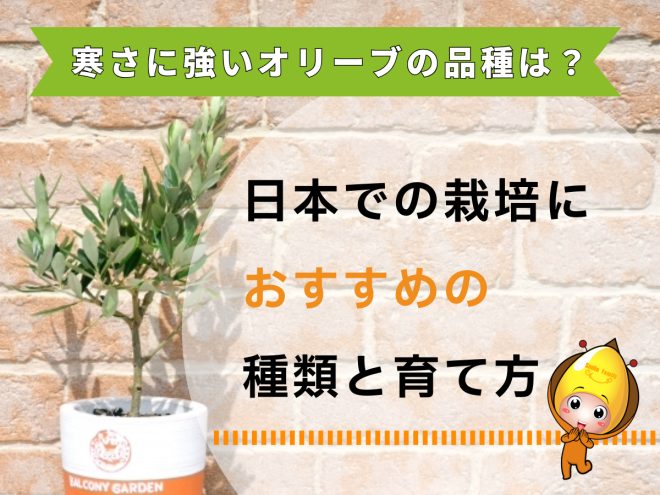庭に木を植えるとき、小さな木だと「庭師さんに頼むほどじゃない」「自分で植えたいなあ」と思うこと、ありますよね?今回は、シンボルツリーを自分で植える際の方法をご紹介します。注意点や作業のポイントなど、しっかり抑えるようにしましょう!
その他、オススメの記事はこちら
◇虫を寄せ付けないシンボルツリーの紹介
◇シンボルツリーにオススメ!人気の常緑樹7選~害虫や日当たりなど注意点も~
◇風水・運気が向上するとされるシンボルツリーを紹介
◇寒冷地や北海道で育てられる人気のシンボルツリーとは
◇シンボルツリーの料金の相場は?植栽工事の値段の相場も徹底解剖
◇庭のプロおすすめのシンボルツリー15選!テイストや環境に合わせてご紹介します
 目次
目次
シンボルツリーを植えてみよう
シンボルツリーを植えるには、それぞれの工程でいくつか注意しなければいけないことがあります。
木は一度植えたらそうそう動かせないし、生き物なので失敗すると枯れてしまいます。
木を植え付けるということは、ただ穴を掘って木を放り込めばいいというものではないのです。
植え付けに失敗して、労力もお金も余計にかけるのはいやですよね。
後悔しないように、自分で植えるときはきちんとそれぞれのポイントを抑えるようにしましょう。
植える際の道具一式
シンボルツリーを植える際には、穴を掘るスコップ、水をあげるホース、埋め戻す際に混ぜる肥料、支柱が最低限必要です。
支柱はシンボルツリーの大きさに応じて、竹のものや木のものなど、材料を選ぶようにしましょう。
また、支柱を縛る麻ヒモなどの用意も必要です。
時間と労力のかかる作業なので、なるべく忘れ物のないようにしましょうね。
これだけあれば、とりあえずは問題ありません。
準備ができたら、作業にとりかかりましょう。
植える前の準備
植える前にまずやっておかなければいけないのが、場所の確認です。
一度植えるとそう簡単には動かせなくなるので、本当にその場所でいいのかよく見るようにしましょう。
日当たり、風当りはどうか、日が当たっていても他の時間は日陰にならないか、植える木はその環境でも耐えられる木なのか、大きくなったら枝が邪魔になる位置にないか、など、慎重に吟味することが大事です。
また、忘れがちなのが水環境。
土が粘土質で水はけが悪いと、植えてすぐに枯れてしまう原因となります。
土の成分よりなにより、水はけが一番大事です。
あらかじめ水をたくさん入れてみて、土がどんな状態か確認しておくようにしましょう。
土の水はけが悪く、他に良い場所が無いときは、竹を埋めて土を改良することができます。
割った竹の節をとって再度しばり、一本のパイプのようにします。
その竹に合わせて掘った縦穴に、竹を入れると、そこが排水パイプの役割をして水はけがよくなるのです。
土を排水性のあるものに入れ替える方法もありますが、これが一番労力が少ない方法です。
何にしても水はけが悪いと根腐れしやすいので、そこは後悔しないようちょっとこだわりましょう。
植える場所に穴掘りをする
植える場所に穴を掘ります。
注意しなければいけないのは、深く掘りすぎないこと。
深く植えて根っこの上に土がたくさんかぶさるようになると、根っこが息ができなくなり、弱ってしまう原因となります。
根っこの高さちょうどくらいの穴を掘って、深く掘りすぎてしまったら埋め戻して調整しましょう。
また、作業中に穴の中を踏み固めると、それが原因で水はけが悪くなることがあります。
不安な時は水を注いで水はけを確認してみてくださいね。
また、水はけをよくするために竹を埋める場合は、掘った穴の底にも埋めるのがオススメです。
土と肥料を混ぜる
土と肥料を混ぜます。
基本的には腐葉土やバークたい肥などを混ぜておけばいいのですが、土の質によって、水はけが悪いならパーライト、逆に水はけがよすぎるならもみ殻など、用途に応じた肥料も混ぜておくのがオススメです。
また、肥料をやりすぎると「肥料焼け」といって木が枯れてしまう原因になるので、植える木の周りの土全部を肥料にしてしまうことのないようにしましょう。
特によそから移植してきたような木だと、もともと根っこが弱っているので肥料焼けしやすいです。
植える際の注意点
植える際には、シンボルツリーの根っこを包む資材を取るか取らないかがちょっと重要です。
基本的には「土の中で分解されるものはそのままで、分解されないものは取り除く」ことを意識しましょう。
たとえば麻布と麻ひもで根巻きされている場合は、どちらも土の中で分解されるので取らずに植えてしまって大丈夫です。
むしろこの場合は、下手にほどいて根鉢が崩れてはいけないので、取らない方が良いでしょう。
ポリポットに入っている場合や、不織布で包まれている場合はとってから植えるようにします。
土を戻して水を与える
シンボルツリーを植えたら、土を戻して水をあげます。
昔ながらの工法として、水をたくさんあげてドロドロにすることで、根っこと土をくっつける「水極め」という方法がありますが、これは土を固めてしまうので賛否両論あります。
根鉢がよっぽど崩れたとかでなければ、やらなくても基本的には問題ありません。
また、水が根っこにきちんと届くように「水鉢」をきるようにしましょう。
やり方は、根元にすりばち状に土を盛るだけ。
これで根っこに水がいきわたります。
また、植えたあともしばらくは定期的に水をあげるようにしましょう。
土は表面が乾いても中は湿っていることが多いのでそう頻繁にやらなくても大丈夫ですが、新しい芽が開くまで気にかけるようにしてください。
シンボルツリーを植えた後は、支柱で補助
植えたあとには、支柱で支えるようにしましょう。
それなりに大きい木でなければ、竹の簡易的な支柱で大丈夫です。
ただ、支柱は木が活着したら取り外すのがオススメです。
木は自分の体を支えられるように自分の幹を無駄なく太らせるので、そのまま何年も育てると、とても風に弱い木になってしまいます。
また、支柱より上だけが風を受けてゆれるので、その部分だけ太ってしまうということも。
不安なら1年ほどつけておいても大丈夫ですが、新しい芽が開いたら外すくらいでも問題ありません。
植え付けの適切な時期はある?
植え付けするのには、木によって適切な時期があります。
細かくいうと種類によって若干時期がずれたりするのですが、大まかに針葉樹、常緑広葉樹、落葉広葉樹で植え付けの時期が変わってくるのです。
どの樹種でも共通なこととして、真夏は植え付けに向きません。
根っこをたくさん伸ばして葉っぱを広げなければいけないのと、真夏は植物にとって乾燥するしたくさん光合成しなくていはいけないしで少し大変な時期。
急に環境が変わるのでそれに対応できなくなってしまうのです。
針葉樹の適期
針葉樹の植え付けは、3~4月ころの春か、9~10月ころの秋がオススメです。
葉っぱが細く小さいため環境への耐性が強いものが多いですが、やはり気候の落ち着いた時期が一番木にとって負担が少なく、植え付けがうまくいきます。
針葉樹はウラジロモミのように山の高い場所で寒く厳しい環境に耐え抜いてきたものや、マツの仲間のようにやせた土地で生き抜いてきたものなどが多いです。
とはいえあまり乱暴にしてはいけませんが、広葉樹ほど気をつかう必要はないでしょう。
常緑樹の適期
常緑樹の植え付けは、新芽が芽吹く前の3月~4月か、梅雨の時期の6~7月ころがオススメです。
6~7月ころは梅雨で雨が多く、根っこが水を吸いやすいというのもありますが、その年に新たに芽吹いた新芽が固まって、木にとってようやく落ち着いた時期でもあるからです。
落ち着いたところに植え付けという大イベントを持ってきてしまうのは酷ですが、仕方ありません。
梅雨の雨で水をたくさん吸わせて根っこを伸ばし、暑くて厳しい真夏に備えるようにしましょう。
落葉樹の適期
落葉樹の植え付けは、11~3月の、葉っぱが落ちてから新芽が芽吹くまでの時期に行うようにしましょう。
葉っぱが落ちた時期は落葉樹にとって休眠している期間なので、ここでなにかトラブルがあっても芽吹くときに葉っぱの量を調整するなどしてしのいでくれます。
理屈としては剪定する時期と同じですね。
もちろん基本的なことを守って植え付けする必要がありますが、落葉樹の植え付けはあまり気をつかう必要がなく、時期さえ守ればだいたいなんとかなる感じです。
自分で植える場合の注意点・デメリット
シンボルツリーを自分で植える場合、植え付けが成功すれば安く済むというメリットはありますが、それなりに労力を必要とすることと、なにより植え付けが失敗したときに木の代金も無駄になってしまうというデメリットがあります。
庭木の、それもシンボルツリーにするような木だと、ばかにならない金額をドブに捨ててしまう可能性があるのです。
よっぽど技術か財布に自信があるのでなければ、プロにお願いした方が結局安く済むことすらあります。
業者に依頼するなら、植木市場
『お庭のデパート植木市場』は国内初の植栽工事を含めて植木の注文ができる、オンラインショッピングモールです。
インターネットで植木を販売しているECサイトでは植木の販売と配送は対応しているものの、植栽工事はほとんど対応していません。
せっかく購入した大切なシンボルツリーを間違った植え方で枯らしてしまわないためにも、植込みまで全てを任せることが出来る『植木市場』で、お気に入りの1本を探してみてはいかがでしょうか?

愛知県稲沢市生まれ。稲沢市が「日本四大植木産地」であることもあり、幼少期から植木に囲まれて成長。
東京農業大学卒業後、名古屋市内の造園会社に就職。公園の整備工事から国交省事業の国道整備工事における土木及び街路樹等の植栽工事に現場代理人として携わる。