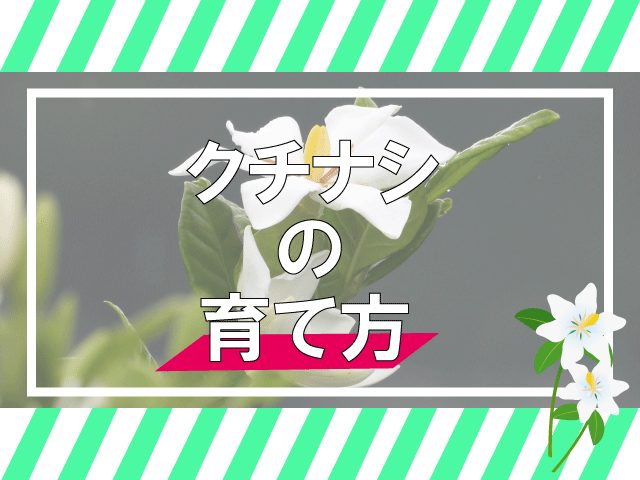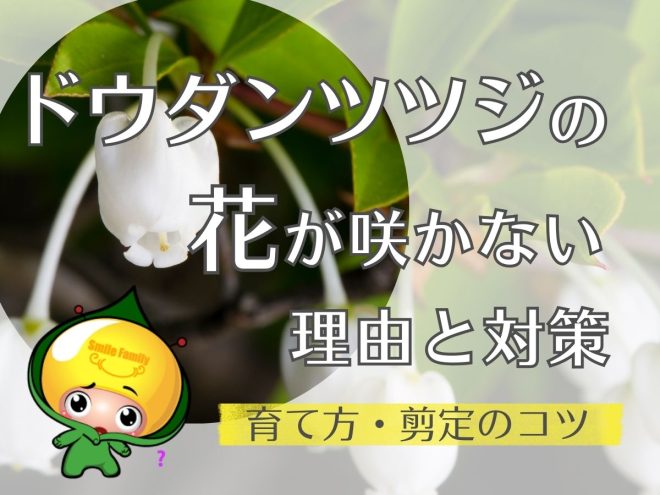南国らしい美しい花を咲かせるブーゲンビリア。トゲがあって手入れが大変な分、たくさん花を咲かせてほしいですよね。しかし、ブーゲンビリアを育てていてもうまく花が咲かないことがあります。ブーゲンビリアに花が咲かない原因と、その対策についてご紹介します。
 目次
目次
ブーゲンビリアに花が咲かない理由

ブーゲンビリアに花が咲かない理由には、様々なものが考えられます。手入れの問題や、生育環境の問題などです。
それらの原因のうち、重要なものから改善していけば、いずれ花が咲くはずです。手入れのやり方を変えてみたり、庭の環境を変えてみたりと、色々推測しながら試行錯誤してみてください。また、原因は複数が関わっていることも多いです。一つの原因に固執せず、様々な方向から考えてみましょう。
ブーゲンビリアに花が咲かない原因についてご紹介します。
手入れの仕方が良くない

手入れの仕方が良くないと、ブーゲンビリアに花が咲かない場合があります。手入れとは、剪定や施肥、水やりなどの人の手で行う作業のことです。
木を育てていると何かと手をかけてやりたくなってしまうことが多いですが、手入れのやり方やその程度によっては、かえって逆効果になってしまうことも少なくありません。この部分に原因があるのなら、手入れの仕方を改善するだけなので比較的簡単です。
ブーゲンビリアの手入れの仕方について、あらためて見直してみましょう。
剪定のやり方が良くない
剪定のやり方によっては、花が咲かなくなる場合があります。花を咲かせようとしているときに剪定をすると、せっかくできた花芽を切り落としてしまうことがあるためです。いくらブーゲンビリアが元気に育っていても、剪定のやり方が間違っていれば全く花が咲かなくなるということも考えられます。
つる性でよく伸びるブーゲンビリアを庭で育てる際には、大きさを整える剪定は必須といって良いほどです。そのため、花が咲かなくなるような剪定は避けるようにしましょう。
剪定をしすぎてしまっている
いくら剪定を行う時期ややり方が正しくても、毎回大量に剪定していると花が咲かなくなる場合もあります。
植物の枝や葉っぱは、光合成を行って自身が成長するために必要なものです。それを大量に切除するということは、それだけ植物に大きなダメージが与えられているということにもなります。強く剪定しすぎると、そこからの回復をしなくてはいけないから、その後1年以上花が咲かなくなる場合もあると考えて良いでしょう。
もちろん、面積が限られている庭で植物を育てる以上、剪定自体は大きさを抑えるためにある程度必要なものなので、剪定をしない方が良いというわけではありません。植物へのダメージを気にしすぎて剪定をほとんどしなかった結果、枝葉が伸びすぎて結局もう一回剪定せざるを得ないという場合もあります。
剪定量があまりに多い場合は抑えるようにして、そこから花が咲かなくなるほどダメージを与えず、かつ伸びすぎて邪魔にならないような剪定量を探っていきましょう。
肥料が足りていない
土の栄養が足りていないと、花を咲かせづらくなります。植物が花を咲かせるためにはそれなりの栄養が必要なためです。
また、植物は土の中の何か一つの栄養が足りていないと、他の栄養がどれだけあっても成長しなくなります。栄養不足で花を咲かせない場合は、花を咲かせないだけでなく枝葉自体の成長も悪くなっていることが多いです。
植え付けしてから肥料をあげていないような場合は、土の栄養を補給してあげることで花を咲かせるようになるかもしれません。
生育環境が良くない

ブーゲンビリアを育てている庭の環境があまり良くないと、ブーゲンビリアが花を咲かせなくなる可能性があります。生育環境が悪いと、花を咲かせないどころかうまく育たずに枯れてしまうということも多いです。
ブーゲンビリアの原産地は熱帯地域で、日本のほとんどの地域とは違った気候です。そのため、そのまま庭に出してあげるだけだとうまく育たないことも多いです。庭のブーゲンビリアの生育環境について、見直してみましょう。
日当たりが悪い
日当たりが悪いと、ブーゲンビリアの生育が悪くなり花を咲かせなくなる可能性があります。ブーゲンビリアは日当たりの良い場所を好む植物です。
他の木の枝葉や建物などでブーゲンビリアの周りが陰になってしまっていると、枯れるほどではなかったとしても花を咲かせられるほど光合成ができない場合があります。
ブーゲンビリアを植えている場所が日陰になっていないかチェックしてみましょう。
土壌環境が良くない
ブーゲンビリアを植えている土の環境が、ブーゲンビリアにとってあまり良くないものかもしれません。
ブーゲンビリアは、水はけが良く、なおかつ水もちも良い土を好みます。また、夏の水切れでしおれてしまうこともあります。そのため、水はけが良すぎてすぐに乾燥してしまうような土や、逆に常に湿っていたり水たまりがなかなかはけなかったりするような土では、ブーゲンビリアがうまく育たないかもしれません。
ブーゲンビリアを植えている土の状態をチェックしてみましょう。
気温が低い
ブーゲンビリアを育てている庭の気温が低すぎて、うまく育てていないのかもしれません。ブーゲンビリアは常に暖かい熱帯地域が原産です。
そのため、冬に気温が低くなる地域は生育にあまり適していません(鉢植えに植えて、冬は室内に取り込むという育て方もあります)。冬の間、ブーゲンビリアの葉っぱの色が変わるなど、ちょっと調子が悪そうにしていないでしょうか。
もしかしたら、ブーゲンビリアはなんとか冬の気温に耐えられているだけで、花を咲かせられるほどの余裕が無いのかもしれません。
病害虫が多い
病気や害虫が多いと、ブーゲンビリアの生育が悪くなって花が咲きづらくなる可能性があります。ブーゲンビリアには、アブラムシ類やハダニ類、ガの仲間の幼虫などの害虫がみられることがあります。
これら単体でブーゲンビリア自体を枯らしてしまうことは考えにくいですが、多少なりともブーゲンビリアを食害するものなので、大量に発生すると弱らせてしまい、花を咲かせるほどの余裕が無くなってしまう可能性はあるでしょう。
屋外で植物を育てていれば多少は虫がつくものなので、あまり目くじらを立てるものではありませんが、大量に発生している場合は対処が必要になります。
花が咲きやすい手入れの仕方

ブーゲンビリアに花を咲かせる場合、ただなんとなく手入れをしているだけではうまく花が咲かない場合もあります。それぞれの作業の目的や意味を理解していないと、やり方もなかなか頭に入らないし、自分の庭やブーゲンビリアの状態などに合わせた応用が効きません。手入れをなぜやるのか、なぜこの方法なのか、難しい部分はありますがなんとなくでも把握しておくようにしましょう。
ブーゲンビリアに花が咲きやすくなる手入れの仕方をご紹介します。
剪定のやり方
ブーゲンビリアの剪定は、花が咲き終わった後に行います。花が咲く前に剪定してしまうと、せっかく準備された花芽を落としてしまう可能性があるためです。
剪定する場合は、ある程度大きくなった株なら強剪定して勢いの良い新芽を出させるとまた花が咲きやすくなりますが、まだ株が充実していないようなころには、伸びすぎて邪魔になった枝を切り戻したり、混んだ枝を整理する程度にするのが良いでしょう。
切った枝は挿し木して、新たな株をつくることもできます。
トゲに気をつける
ブーゲンビリアの剪定を行う際には、トゲに気をつけながら行いましょう。ブーゲンビリアの茎には、硬く鋭いトゲがあります。これがなかなかやっかいで、剪定を行う際にはもちろん、剪定した枝を処理する際にも手に刺さってとても痛いです。
剪定作業時には軍手などを使って手を保護するのはもちろん、剪定した枝を処理しておく場所なども用意しておくのがおすすめです。ゴミ袋に入れておいてもすぐにトゲが袋を突き破ってしまうので、枝の量が少なければトゲを一つ一つ切って処理したり、枝の量が多ければ庭の誰も踏まない場所に積んでおいて分解されるのを待ったりなどの方法がとれます。
肥料のあげ方
ブーゲンビリアに肥料を与える場合、肥料の種類によってあげ方を少し変えるのがおすすめです。
効き目がゆっくりな緩効性肥料は、4~5月と9月に、株もとに与えるようにします。効き目が速い液肥の場合、花が咲いた後に与えるようにします。それぞれの与える量は、肥料のパッケージなどに書いてある用法容量を参考にして与えるようにしてください。
また、肥料は弱っているときに与えると逆効果になる場合があります。元気な場合でも、たくさん与えすぎると濃すぎる肥料の濃度の浸透圧により植物がしおれてしまう「肥料焼け」という現象により枯れてしまう場合があります。肥料はあくまで弱っていない株の成長を促進するためのものと考えておくのが良いでしょう。
水のあげ方
ブーゲンビリアを庭に地植えして育てている場合、根付いてからは基本的に水やりは必要ありません。地面に広く根っこを伸ばせるので鉢植えよりもはるかに水を吸いやすいことと、水やりを頻繁にしていると根っこが土表面に集まり、かえって乾燥に弱い性質になってしまうためです。
ただし、庭に植え付けたり、別の場所から植え替えたりした場合は、根付くまでの間は鉢植えと同じようにしばらく水やりが必要です。土の表面が乾いたら、下の方まで浸透するようにたっぷり水を与えましょう。新しい枝葉が旺盛に伸びるようになったら、そこからは水を与えなくても基本的に大丈夫です。
夏の水切れには弱いので、真夏に長期間雨が降らず、葉っぱが明らかにしおれているような場合は、下まで浸透するようにたっぷり水を与えましょう。
また、冬に屋内に取り込むために鉢植えで育てる場合も多いかと思いますが、その場合は根っこを伸ばせる範囲が限られているため定期的な水やりが必要です。土の表面が乾いたら、鉢底から水が出てくるまで水を与えるようにしましょう。冬の間は水やりの頻度を減らし、乾かし気味で管理を行います。
ブーゲンビリアが好む生育環境

庭の環境をブーゲンビリアが好むようなものにしてあげると、ブーゲンビリアがうまく生育して花が咲くようになるかもしれません。生育環境と一言でいっても、それを構成する要素はいくつもあります。
その中でどれがブーゲンビリアの生育に合っていないのか考えながら、改善していきましょう。
また、ブーゲンビリアの原産地は熱帯地域です。庭でその環境をなるべく再現してあげるように意識すると、うまくいくかもしれません。
日当たり
基本的に日当たりの良い場所で育てるようにしましょう。半日陰でも枯れない場合はありますが、花付きや生育は悪くなります。他の大きな木などで日陰にならないよう、植え付け場所や日々の管理を調整するようにしましょう。
今の場所ではこれ以上日当たりをよくできないという場合は、別の日当たりの良い場所への植え替えも検討してみてください。
土壌
ブーゲンビリアは、水はけがよく、なおかつ水もちが良い土を好みます。水もちが悪く水はけが良すぎると夏に長期間雨が降らない場合などに水切れしやすくなるし、逆に水はけが悪くて水もちが良い場合は、冬などに根腐れしやすくなります。
庭の環境にもよりますが、赤玉土を多めに使い、それに腐葉土を合わせた土などがおすすめです。
土の環境を改善したい場合は、ブーゲンビリアの周りの土を、根っこをなるべく切らないように気を付けながら掘って穴をあけ、改良した土と共に埋め戻すということを行います。
ただし、この土の配合や作業のやり方はある程度経験が必要な場合もあるので、業者に依頼してやってもらうのも良いかもしれません。
気温
ブーゲンビリアが外で冬を越すためには、最低5℃くらいの気温が必要です。西南日本の海沿いなどでは庭に地植えして育てられる場合もありますが、日本の多くの場所では冬にそれ以下の気温になってしまって難しいです。
そのため、鉢植えで育てておいて冬になったら室内に取り込むなどの方法が必要になります。大変ですが、簡易的な温室をつくるというやり方も可能ではあります。あくまで熱帯植物なので、冬対策はしっかりしておきましょう。
病害虫を減らすためには

病害虫を減らすためには様々な方法がありますが、まずはブーゲンビリア自身を健康に保つというのが大事です。弱った株は、病害虫に抵抗できずにやられやすくなります。
また、病害虫は見つけたらなるべく早く対処を行いましょう。葉っぱの周りにいる虫を全て駆除するというものではなく、アブラムシ類など明らかな害虫がついていたら、なるべく早い段階で対処を行うというものです。
ある程度の大きさがある害虫なら直接捕殺するのでも良いし、新芽などに小さな害虫が集まってついている場合は、ついている部分ごと切除してしまうということも可能です。
それらの方法で対処しきれない場合は、適用のある薬剤を散布しましょう。散布する量や頻度などは、薬剤の用法容量や注意点などをよく読んで、それを守るようにしてください。
まとめ

ブーゲンビリアに花が咲かないのには、様々な原因が考えられます。それらの原因を推測し、可能性の高いものからつぶしていけば、いつか花が咲くようになるはずです。
枯らしてしまいそうで怖い場合や、この対策方法であっているのか自信がない場合、作業を行う時間が無い場合などは、smileガーデンなどの業者にお願いしてみるのもおすすめです。
お金はかかりますが、一人で試行錯誤するのにも時間やお金がかかるので、そう考えるとそれほど損失ではない場合もあります。ぜひ検討してみてください。