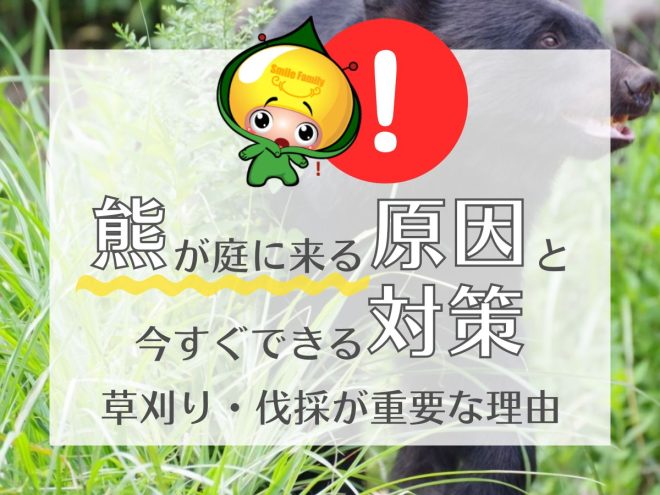実を食べるとピリッとさわやかな風味がある山椒。実だけでなく、芽や花なども利用することができます。自分の家で山椒を栽培して収穫出来たら素敵ですよね。山椒の木に実がならない原因や対策についてご紹介します。
 目次
目次
山椒の木に実がならない理由

山椒の木を育てていても、なかなか実がならない場合があります。山椒の木に実がならない原因には様々なものが考えられますが、育てている環境や手入れの仕方、山椒の木の特性などに原因がある可能性があります。
それらの問題を見直せば、山椒の木に実がなるようになるかもしれません。
自分の育てている山椒に該当する原因が無いか、見直してみましょう。
手入れの仕方

山椒の木に実がならない原因の一つとして、手入れの仕方に問題がある可能性があります。木を育てていると、剪定や肥料などあれこれ手をかけたくなってしまうという方は多いですが、手入れの仕方が間違っていると、それらが逆効果になってしまう場合があります。
また、逆に手をかけすぎないのも、うまく実がならない原因になってしまっているかもしれません。
山椒の木に実がならない手入れのやり方をしていないか、チェックしてみましょう。
剪定のしすぎ
もしかすると、山椒の木を剪定しすぎているかもしれません。山椒の木を剪定する時期は冬の落葉期ですが、山椒は前年の初夏~夏ごろには既に花芽をつけています。
そのため、あまり多く剪定しすぎると花芽を全て落としてしまって、花が咲かず、実もならないということになります。枝先全てをまんべんなく切り詰めているというような場合は、注意した方が良いかもしれません。
実をつくる養分が足りない
実をつくるための養分が足りていないかもしれません。山椒に限らず植物は、光合成によって得た養分だけでなく、根っこから吸いあげる土の微量な養分を使って成長していきます。
この微量な養分にはいくつか種類がありますが、その中のどれかが必要量に達していないと、他の養分がどれだけあろうと成長が止まってしまうということがあります。
普段肥料をあげておらず、土の量に限りがある鉢植えで育てている場合や、土が瘦せていたり、他の植物も同じように育たなかったり、葉の色が少し変になっていたりしたら、土の養分が原因の可能性があるかもしれません。
生育環境、生育状態があまり良くない

お庭で山椒の木を育てている環境が、もしかしたらあまり良くないのかもしれません。山椒の木も生き物なので、良い生育環境で育てた方がよく育ち、花や実もつきやすくなります。また、山椒の木がそもそも花を咲かせるまで育っていないと、当然実もなりません。
庭の環境が山椒の木の生育に適しているのか、チェックしてみましょう。
実がなるまで育っていない
山椒の木は、実がなるまでにある程度まで成長している必要があります。もしかしたら、お庭の山椒の木は実をつけるほど成長できていないのかもしれません。
実がなるまでの年数は環境や苗の大きさなどによっても変わりますが、植え付けてから1~3年くらいは見ておいた方が良さそうです。また、種から育てる、あるいは庭に勝手に生えてきた山椒の木を育てているような場合はさらに時間がかかる可能性が高いと思っておいた方が良いでしょう。
環境が悪かったり剪定をしすぎていたりしてうまく成長できていない場合では、思った年月で実がならない可能性もあります。
日当たりが良すぎるor悪すぎる
山椒の木を植えている場所の日当たりが、山椒の木にとってあまり適していない状態なのかもしれません。山椒の木は、日当たりが良すぎず悪すぎずといった場所で育ちます。
日当たりが良い場所で育てることもできるのですが、乾燥によって枯れてしまう場合があるのでより丁寧な環境づくりや手入れが必要です。
また、多少暗い場所でも育ちはするのですが、あまりに暗いと光合成できず成長が遅くなったり、実がならなかったりします。明るすぎず暗すぎず、ちょうど良い日当たりを見つけるのが大事です。
病害虫の影響
山椒の木に病気や害虫が発生していないでしょうか。多少葉っぱがかじられているくらいなら問題ないことも多いですが、あまりに多く病害虫が発生すると、山椒の木の生育が遅れたり、実がならなかったりすることも多いです。
山椒の木につく病気や害虫の種類は比較的少なめではありますが、それでもたくさん発生して弱ったり枯れたりすることもあります。山椒の木によく発生する病気や害虫についてご紹介します。
【山椒の木に出る病気】
山椒の木には、「灰色こうやく病」「赤衣病」「さび病」などが発生することがあります。いずれも、カビのような菌により発生する病気です。
灰色こうやく病は、枝などにつくカイガラムシ類に菌が共生し、枝に分厚い菌糸の膜が発生する病気です。カイガラムシが汁を吸っておしりから甘い汁を出すことで菌がさらに成長し、病状が進むと枝が衰弱したり枯れたりしてしまいます。
発生したら菌のついている枝を切ってしまうか、ブラシでこそぎ落とすかして対処しましょう。また、木が弱っていると発生しやすいので、山椒の木を健康に保つことも重要です。
赤衣病は、白または赤っぽい菌糸の膜が枝を覆ってしまう病気です。病状が進むと、菌糸がついた部分が壊死し、発生個所から先が枯れてしまうこともあります。枝についた菌糸膜が病気の越冬場所やさらなる感染源になるため、病気の発生があったらなるべく早めに枝を切って焼却処分するようにしましょう。
さび病は、山椒の葉っぱに文字通り鉄さびのような斑紋が出る病気です。二つの宿主を行ったり来たりする病気で、山椒の他に、クロマツのような二葉マツの仲間を行き来します。
そのため、可能であれば山椒の近くにマツの仲間は植えないようにしましょう。とはいえ近隣の家に植えてあるなどして宿主を排除できない場合もあるので、そうした場合は適用のある薬剤を散布して対処します。
【山椒の木につく害虫】

山椒の木には、害虫がつくこともあります。種数は多くありませんが、一度つくと大きな被害を与えるものも多いです。
代表的なものでは、アゲハチョウの仲間の幼虫が付くことがあります。ポケモンのキャタピーを思わせるような風貌のイモムシで、小さい幼虫のころは鳥のフンによく似た姿です。山椒を食べるアゲハチョウの幼虫にはいくつかの種類がありますが、ナミアゲハ、クロアゲハ、カラスアゲハの幼虫などが見られます。
これらのチョウの幼虫は、いずれも終齢幼虫(蛹になる前の大きい幼虫)になるとかなり食べる量が多くなってきます。何匹かついていると、葉っぱを食べ尽くされてしまうことも珍しくありません。綺麗なチョウになるのに少しかわいそうですが、見つけ次第早いうちに捕殺するのがおすすめです。
山椒の木には、他にもアブラムシやカイガラムシなどの茎や葉っぱの汁を吸う害虫がつくことがあります。小さいのでアゲハチョウの幼虫ほど大食感というイメージはありませんが、放っておくとどんどん増えていき、つきすぎると山椒の木の元気が無くなってしまうこともあるので注意しましょう。
特にアブラムシ類は1匹からクローン繁殖していくので、なるべく早く対処するのがおすすめです。枝葉ごと摘み取ったり、ブラシでこすり落としたりして駆除できますが、追い付かない場合は適用のある薬剤を使って対処しましょう。
カイガラムシの場合、効果のある薬剤は限られてくるので、カイガラムシに効果のある薬剤かどうかしっかり確認しておくのが大事です。
受粉などの問題

当然ですが、春に咲く山椒の花のめしべに花粉がつかないと、実はできません。様々な要因によって、うまく受粉ができず、実がならないということも考えられます。庭の山椒の木がどんな状態なのか、しっかり確認しておきましょう。
育てているのが雄株
山椒の木は、オスの木(雄株)とメスの木(雌株)がそれぞれある雌雄異株と呼ばれる性質の木です。そのため、育てているのが花粉を出すだけの雄株であれば、実がなることはありません。
苗木で購入した場合には雄株か雌株か書かれている場合もあるかとは思いますが、どちらか書かれていなかった場合や、種や山取りの苗木から育てているような場合だと、雄株なのか雌株なのか花が咲かないとわかりません。
春に花は咲くけど実がならないという場合は、育てているのが雄株ではないか確認してみると良いかもしれません。
受粉ができていない
庭に雄株と雌株を植えていても、雄株から雌株に花粉が運ばれていないと、受粉がうまくいきません。花は咲くけど実がならない、少数だけしか実がならないという場合は、受粉ができていないことが原因の可能性があります。
数十メートルくらいなら木が離れていても受粉できる可能性はあると思いますが、かなり距離が離れていたり、物理的に隔離されていたりするような場合は、うまく受粉ができていないかもしれません。可能なら、人の手で雄花から雌花に花粉を移動して実験してみるのも良いでしょう。
実がなりやすい山椒の手入れの仕方

山椒の木がたくさん実をつけるためには、適切な手入れが大事です。手入れをしすぎてはいけませんし、しなさすぎるのもいけない場合があります。山椒の木に実をつけるための手入れの仕方についてご紹介します。
剪定
山椒の木は、12月~3月ごろの、葉っぱが落ちている頃に行います。剪定の時期が遅くなると芽吹いて花が咲いてしまう可能性があるので気を付けましょう。混んだ枝や枯れ枝を間引き、風通しをよくします。
その後、枝先を切り戻したり切り詰めたりして樹形を整えるイメージで剪定を行います。長く伸びた枝の横から短く伸びる枝には、花芽がつくことが多いのであまり落とさないように気を付けましょう。
また、剪定をしすぎると花芽を落としてしまうだけでなく、光合成できる量も少なくなるので、切るべき枝を決めて最小限の剪定となるようにするのがおすすめです。
肥料や水のあげ方
山椒の木には、植え付け時に元肥として堆肥、骨粉、油かすなどを与えるようにします。その後、冬の間に寒肥としても与えるようにしましょう。
また、庭に地植えする場合、植え付けしてからしばらくの間は、土が乾いたら下まで浸透するようたっぷりの水を与えるようにします。枝葉が旺盛に伸び始めたら、基本的には水やりの必要はありません(鉢植えの場合は、引き続き同じように水を与えます)。
ただし、山椒は乾燥にそれほど強くないため、真夏に長期間水が降らず、土が乾燥しきっているような場合は水を与えるようにします。逆にずっと滞水しているのも苦手なので、水はけが悪くいつまでも水たまりが無くならないような場所には植えないのがおすすめです。
山椒の木がよく育つ生育環境

山椒の木がよく育つために、お庭を山椒の木が育ちやすい環境に整えてあげましょう。
要素としては、日当たりや風通し、土の状態などが大事な部分です。
幸いにも山椒の木は日本にも自生する木なので、気候が合っていないという可能性は少ないです。山椒の木が好む生育環境についてご紹介します。
山椒の木が好む場所
山椒の木は、日本の山野にも普通に自生しているのを見ることができます。そのため、日本の気候でもともとよく育つ木ではあるので、野外で山椒の木がよく育つ生育環境をイメージすると、環境づくりもしやすいかもしれません。
山椒の木は、山野の林道沿いや、明るめの林内などで見かけることが多い木です。直射日光がガンガン当たる日当たりの良い場所より、やや日陰になる場所にいることが多いです。また、鬱蒼とした森の中にもあまりいないので、適度に明るい環境をつくってあげると良いでしょう。
乾燥に比較的弱く、植え付けた木の場合だと西日が当たるなどして枯れてしまうこともあります。逆に、常に滞水していて過湿状態になっている環境もあまり好みません。そのため、山椒の木を育てる場合、水はけが良く保水性も良い土を作ってあげるのがおすすめです。
病害虫対策としてできること
病害虫の被害を防ぐために、そもそも病害虫が発生しづらい環境をつくってしまうのもおすすめです。病気の中には治療の難しいものや、かかったら治らないものなどもありますが、そうした病気は未然に防げるだけ防いだ方が良いですよね。
出来ることとしては、剪定により風通しを良くしておくというものが一つ挙げられます。病原菌や害虫にはジメジメしたところを好むものが多いので、混んでいる枝を間引くなどして風通しをよくしておきましょう。
また、一度剪定してから他の木の剪定に移る場合、剪定バサミは消毒するのがおすすめです。最初に剪定した木に病原菌がついていた場合、剪定バサミを介して病気が移る可能性があるためです。こうしたルートで感染するものの中には、治療が不可能なものも少なくないので注意しましょう。
病害虫の中には弱った木につくものも多いので、日ごろから環境を整えて丁寧に育てることも、病気を未然に防ぐことに繋がります。
もし病害虫が発生してしまった場合、なるべく早く対処することが被害の拡大や対処の労力を最小にするのに役立ちます。日ごろから木をよく観察しておいて、異常があればすぐに気がつけるようにしておきましょう。
まとめ

山椒の木を旺盛に育てて実をたくさん収穫できるようにするためには、どんな要素が関わっているのかご紹介しました。剪定や施肥などの手入れの仕方や、日当たりや風通しなどの生育環境、山椒の木自身の特性や状態などが、山椒の木の生育や実をつける量に大きく関わってきます。山椒の木がお庭でよく育つように、環境を整えたり手入れしたりしてあげましょう。
しかし、「剪定が難しそうで、うまくやる自信がない」「そもそも、手入れや環境の改善をするにも時間がない」「一度お手本としてプロの技を見てみたい」という方も多いのではないかと思います。
そうした場合は、剪定のできる専門の業者にお願いしてみるのも一つの手です。多少お金がかかっても、失敗して弱らせたり枯らしたりするより、プロとしての知識や経験から適切な剪定を行ってもらうことに価値はあるはずです。また、自分でやる前に一度プロの技を見て覚えたり、色々質問して教えてもらったりしてみても良いでしょう。ぜひご検討ください。