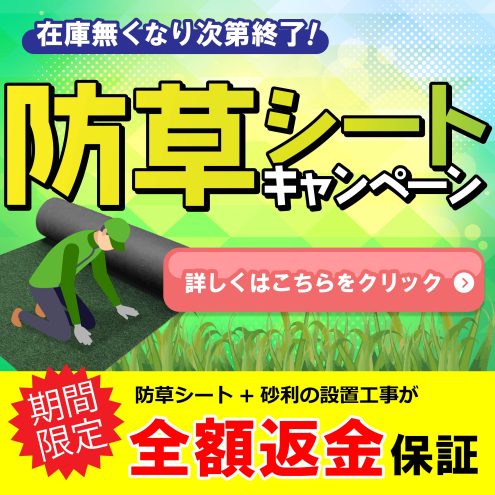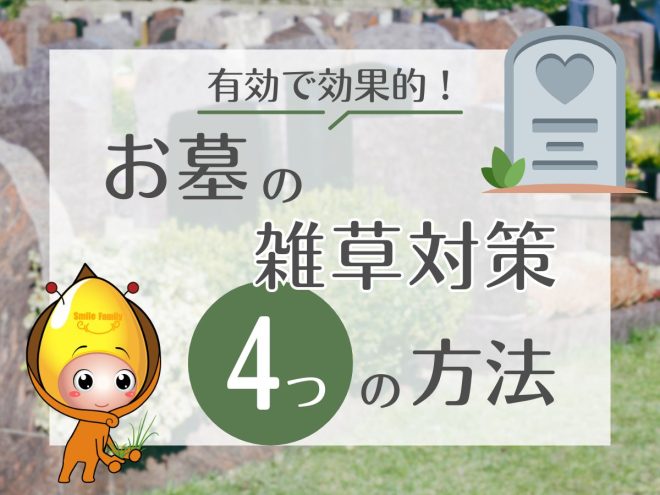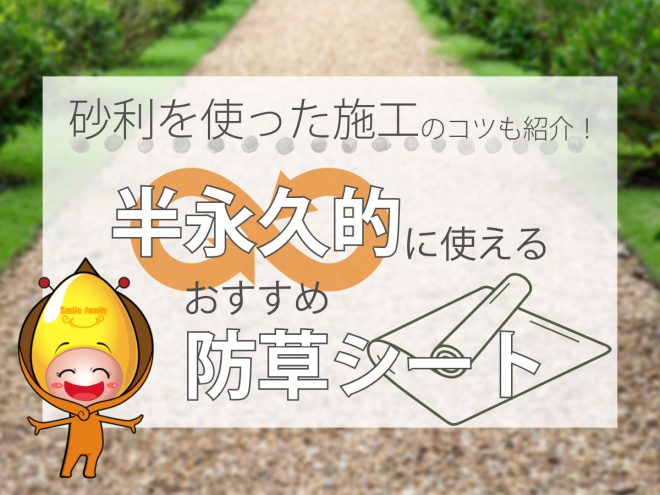雑草が生えるのを抑えてくれる防草シート。庭のお手入れの手間を減らせる便利なアイテムですが、「見た目が地味だから」「施工するのが難しそう」と敬遠している方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、防草シートの上にアイテムをのせて、おしゃれな庭をつくる方法をご紹介します!防草シートを敷く方法や施工時の注意点も詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
 目次
目次
防草シートの上に何を敷くべき?おすすめアイテム5選

まずは、防草シートの上に敷くおすすめのアイテムを5つご紹介します。いずれも、雑草対策だけでなく庭をおしゃれにグレードアップしてくれるアイテム。特徴や注意点から、ご自身の庭に合ったアイテムを選びましょう。
1. 防草シートの上に砂利を敷く

砂利は種類が豊富で、種類や色、敷き方によって庭の印象を大きく変えられるのが魅力です。和風庭園のような落ち着いた雰囲気からモダンな雰囲気まで、様々な表情の庭を作ることができます。
砂利のメリットとデザインのコツ
古くから庭やガーデニングに使われてきた砂利は、防草シートとの相性も抜群。防草シートの上に敷くことで、砂利単体よりも雑草対策の高い効果が期待できます。他のアイテムに比べて費用が比較的安価という点も見逃せません。
砂利は色や大きさ、素材が多彩なので、お好みのデザインや庭の雰囲気に合わせて選びましょう。たとえば、洗練された印象の庭にしたいときは白い角張った砕石がぴったり。あたたかい雰囲気の庭にしたいなら、ピンクやオレンジなど暖色系の玉砂利がおすすめです。
砂利はどんな形状の場所でも敷きつめられるのもポイントです。メインの庭はもちろん、家の裏のような狭いスペース、アプローチのブロックの間などもカバー可能。踏むと音がするので防犯対策になったり、雨の日でも泥はねしないといった実用的なメリットもありますよ。
砂利を敷く際の注意点
砂利は掃除がしにくいというデメリットがあります。ほうきだと落ち葉といっしょに砂利まで掃き集めてしまったり、ガーデンクリーナー(熊手)のツメに砂利が挟まったりと、少々面倒です。
砂利を敷きたい場所の近くに庭木がある方は、落ち葉の掃除のしにくさも踏まえて砂利の導入を検討しましょう。冬場の雪かきも難しくなりますので、積雪がある地域の方も注意が必要です。
また、砂利を敷くもうひとつのデメリットは散らかりやすいこと。砂利は固定されていないため、人が歩いたり車が出入りすることで少しずつ動きます。
そのまま放置していると景観が崩れるだけでなく、道路に砂利が飛散してクレームにつながることも。こまめに片付けるか、あらかじめ砂利の飛散防止剤を使用するなどの対策を取りましょう。
2. 防草シートの上に人工芝を敷く

緑あふれる美しい庭にしたいなら、人工芝がおすすめです。 「芝生に憧れるけどお手入れができるか不安」という方は、ぜひ人工芝を検討しましょう。
人工芝のメリットと施工のポイント
四季を通して、鮮やかでリアルな緑を楽しめる人工芝。水やりや草刈りの手間が不要で、敷いてしまえば維持費がかからないといったメリットがあります。やわらかな素材でつくられているため、子どもが転んだり、ペットが走り回っても安心です。
人工芝の施工では、下地づくりが重要なポイントになります。いきなり防草シートを敷くのはNG。防草シートと人工芝の間に隙間ができて、人工芝が浮く原因になってしまいます。雑草や石を取り除き、地面を平らにする、水はけを良くするためわずかな傾斜をつけるなどの作業を行ってから防草シートを敷きましょう。
人工芝を並べて敷く場合は、芝目(芝の葉の向き)が同じ方向になるように敷いていきます。また、人工芝と人工芝をぴったりくっつけると、その部分だけ不自然に盛り上がってしまいます。自然に仕上げるため、2~3mm程度離して設置しましょう。
人工芝のメンテナンスと注意点
人工芝は、天然芝に比べてお手入れが少なくて済むのが魅力です。日頃の掃除は、ほうきで落ち葉やごみを取り除く程度でOK。泥やジュースなどの汚れがついてしまったときは、都度ホースで水洗いしましょう。
加えて、半年に1回は行っておきたいのがブラッシングです。人工芝の葉は放っておくとだんだんと寝てしまうため、定期的にデッキブラシを使って起こしてあげましょう。寝ている方向と逆にブラッシングするのが効果的です。紫外線で色あせたり、葉が抜けやすくなってきたら張り替えを検討するタイミングです。
プランターやレンガ、イスなどの重いものを人工芝の上で引きずったり、同じ場所に置き続けたりすると葉が劣化しやすくなるため注意してください。
3. 防草シートの上にレンガやタイルを配置する

レンガやタイルは、見た目だけでなく耐久性の高さも兼ね備えています。長く使い続けることができるため、一度施工すれば長く楽しめるのが魅力です。
レンガやタイルでおしゃれな庭づくり
おしゃれで個性的な庭が演出できるレンガやタイル。目地の間から雑草が生えてくるのが難点ですが、防草シートの上に敷けばその悩みも解決できます。
レンガやタイルは、多様なデザインと質感が楽しめる素材です。たとえば、ストーン調のタイルを敷き詰めれば高級感あふれる印象に。明るい色の乱形石(大きさ・形が均一でない自然材料)のタイルを使えば南国風、アンティーク調のレンガはレトロでナチュラルな雰囲気など、種類や配置でさまざまな世界観が表現できます。
植物との相性も抜群なので、ガーデニングが好きな方にもおすすめですよ。
レンガやタイルを使う際の注意点
防草シートの上にレンガやタイルを敷く際に注意するべきことは、レンガやタイルはズレやすいということ。防草シートの上に敷きつめるだけではしっかり固定されないため、徐々に凸凹や隙間ができてしまいます。
ズレるのを防ぐためには、まずは下地となる土を、レンガやタイルの高さの分掘ります。踏み固めて平らにしたら防草シートとレンガを敷き、隙間を目地砂で埋めましょう。歩くためにレンガやタイルを敷くなら、モルタルで固めてしまうのがおすすめです。
タイルは割れやすいため、より下地をしっかりとつくり込む必要があります。割れにくく美しい仕上がりを目指すのであれば、専門業者に依頼すると安心です。
レンガやタイルは半永久的に長持ちするとされていますが、経年劣化によって色あせたり、ひび割れたりすることがあります。定期的に目で状態を確認し、必要であれば補修を行うようにしましょう。
4. 防草シートとウッドチップの組み合わせ

自然な雰囲気を出したい方は、ウッドチップのある庭はいかがでしょうか。ウッドチップは一定の期間で土に還るため、環境に優しい素材です。原料となる木がさまざまなので、自分好みの色や香りで選ぶことができますよ。
ウッドチップの香りやエコ効果を活かす
ウッドチップは、木の幹や樹皮を小さく砕いたもの。扱いやすく、施工も非常に簡単なのでDIY初心者の方にもおすすめしたいアイテムです。木材特有のやさしい色合いが特徴で、クッション性があるため公園やドッグラン、ガーデニングのマルチングなど幅広く使われています。
ウッドチップにはスギやヒノキが使われていることが多く、2か月ほどいい香りが続くのもうれしいポイントです。この香りにはリラックス効果のほか、消臭や殺菌、防虫、さらにはカビの発生を抑える効果も。夏には土の温度の上昇を和らげ、冬には霜や凍結を防ぐ効果も期待できます。
また、ウッドチップは土に還るだけでなく間伐材や廃材となった木を使用していることが多く、環境への負荷を減らせるという点でも注目されています。
防草シートとウッドチップの相性
防草シートとウッドチップを併用することで、防草効果以外にもさまざまなメリットが生まれます。たとえば、使うウッドチップの量を減らせること。通常、防草のためにウッドチップを敷く場合10cmほどの厚みが必要とされていますが、防草シートを敷けば5cmほどで十分です。
ウッドチップの分解を抑えられるのも併用のメリット。有機物であるウッドチップは1~2年ほどで土に還ります。どうしても定期的な補充は必要ですが、防草シートがあれば土による分解が抑えられ、目減りするスピードが緩やかになります。
また、植物の種がウッドチップに飛んできても、根が土の中まで届かないため簡単に取り除けます。スギナやドクダミといった頑固な雑草が多いのであれば、併用をおすすめします。
5. 防草シートの上にロックガーデンを作る

近年人気が高まり、外構の定番となったロックガーデン。おしゃれなカフェや公園など、街中でも見かけるようになりました。防草シートを下地にすることで石の下から雑草が生えてくるのを防ぎ、ロックガーデンを美しいまま楽しめます。
ロックガーデンでおしゃれに演出
ロックガーデンは、庭に岩や石を配置し、その間に植物を植えてつくる庭園のことです。さまざまな種類の石や植物を自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルの庭を演出できるのが最大の魅力。たとえば、丸みのある自然石をランダムに配置すればナチュラルな雰囲気に、角ばった石を規則的に並べれば、モダンな雰囲気に仕上がります。
また、単に石を並べるだけでなく、隙間に植物を植えることで四季折々の変化も楽しめます。シンボルツリーとして植えるならヤシやソテツ、アガベ、ユッカなどがおすすめ。ローズマリーやラベンダーのように乾燥を好むハーブや、多肉植物とも相性がいいです。
ロックガーデンに植える植物は、「乾燥した環境と湿った環境どちらを好むのか」、「耐暑性や耐寒性はあるのか」をチェックして選びましょう。お住いの地域や植える場所に合った植物を選ぶことで、お手入れも楽になりますよ。
石の選び方と注意点
選ぶ石の種類によって庭の雰囲気は大きく変わります。たとえば、モダンな雰囲気の庭にしたいなら、明るいグレーと白の色合いの「白砕石」がよく合います。ワイルドな庭にするなら、ゴツゴツした表面が野性的な「溶岩石」や、茶褐色の石に黒やベージュが混じった「みかも石」、ナチュラルな雰囲気にしたいなら琥珀のような透明感がある「クォーツロック」など。まずは全体のテーマを決めてから、石の色や形状、大きさを選びましょう。
石の置き方に決まりはありませんので、まずは直感で置いてみてください。時間をかけて少しずつ調整していき、完成を目指しましょう。崩れやすい配置にならないよう注意しながら、安定感を意識するのがポイントです。
なお、山や川、公園などからの石の持ち帰りは法律に反する恐れがあります。ロックガーデンに使えそうな石を自然の中で見つけても、持ってくるのはおすすめしません。ホームセンターや石の専門店、園芸店などで探しましょう。
防草シートの上をおしゃれにするためのデザインポイント

ここでは、防草シートを活かしたおしゃれな庭のデザインポイントをご紹介します。家の外観や建物に合わせること、統一感のある庭であることを意識してみましょう。
家の外観や建物に合わせたデザイン
防草シートの上のデザインは、家の顔である庭全体の雰囲気を左右します。そのため、建物の個性に合わせたコーディネートが大切。「おしゃれな庭にしたいけど、具体的なイメージがわかない」という方は、家のテイストに合わせてアイテムや植物を選びましょう。庭全体がより美しくまとまります。
風情ある日本家屋なら庭石や竹、コケといった自然素材を取り入れて、落ち着いた和風庭園を演出できます。
一方、すっきりとしたモダンな家であれば、グレー系の砕石やタイルを敷き詰めることで、スタイリッシュで落ち着いた雰囲気に。木造の家なら、木の温もりを感じられるようなウッドチップやバークチップを使うと、より自然な雰囲気を演出できます。
シンプルで統一感のある庭づくり
シンプルで統一感のある庭づくりのポイントは、素材や色を統一すること。素材や色の調和がとれていないと、ごちゃごちゃして庭造りの難易度が上がってしまいます。使用する素材を限定したり色味をまとめたりするだけで、より洗練された印象になりますよ。
たとえば、防草シートの上の砂利と玄関ドアを同じ色にしたり、レンガの外壁に合わせてレンガをメインに使った庭にしたり。同じ素材でまとめることで、庭全体に統一感が生まれます。
防草シートの上だけでなく、庭や門、フェンスなど、家のまわり全体をセットで考えてみましょう。
防草シートの上に乗せるアイテムの選び方のポイント

防草シートの上に乗せるアイテムを選ぶ際には、長持ちする素材であることと、どんな効果を期待するかという2つのポイントも考慮して選びましょう。ここでは、アイテム選びのコツをご紹介します。
長持ちする素材を選ぶコツ
防草シートの上に乗せるアイテムは、できるだけ長持ちするものを選びたいですよね。製品にもよるため一概には言えませんが、予算があれば高いものを選ぶのが無難です。いずれのアイテムでも、耐久性がある高品質な製品は価格が高いものが多いためです。
たとえば高温で焼いた「焼きすぎレンガ」は一般的なレンガに比べて高価ですが、密度が高く耐久性に優れています。人工芝についても、ナイロン製はやわらかくて安価というメリットがありますが、値段がやや高いポリプロピレン製のほうが耐久性・対候性があります。初期費用が安く済むものは、劣化が早く結果的にランニングコストがかることが多いため、慎重に検討しましょう。
なお、ウッドチップに関しては価格に左右されません。ウッドチップは時間が経つと土に分解されますが、広葉樹チップよりも比較的安価な針葉樹のチップのほうが腐食が遅く長持ちします。補充の手間を減らしたい方は、ヒノキ、スギ、ヒバなどを原料とした針葉樹チップを選びましょう。
どんな効果を期待するか
防草以外にどんな効果を期待するかによって、選ぶアイテムも変わってきます。たとえば、子どもやペットが走り回れる庭にしたいなら人工芝やウッドチップがぴったり。アプローチや小径など、歩行性を重視する場所にも適しています。ただし、バーベキューや焚火をする予定であれば人工芝やウッドチップは避けましょう。
防犯も兼ねたいなら砂利が最適です。特に、家の裏側など人目に付かない場所には、上を歩くと大きな音が出る防犯砂利や砕石を敷くと良いでしょう。
ガーデニングに力を入れたいなら、年月を重ねるごとに風合いを増すアンティークレンガや、自然の恵みをそのままに活かした天然石がよく似合います。
そのほかにも、家族で団らんするスペースにしたい、趣味の空間にしたい、家庭菜園のスペースが欲しいなど、まずはどのような庭にしたいかをはっきりさせてから方向性を定めましょう。
防草シートを敷く際の注意点と施工方法

防草シートがどれだけ効果を発揮できるかは、実は敷き方で大きく変わってきます。DIYも可能なので、ぜひ参考にしてみてください。
防草シートの施工手順
DIYで防草シートを敷く手順は、以下の5つのステップで行います。
- 雑草や石を取り除く
- 土を平らにして固める
- 防草シートをカットする
- 防草シートを敷いて固定する
- 防草シートの上にアイテムを配置する
まずは、防草シートを敷くために準備するものをチェックしましょう。
防草シートを敷くために準備するもの
- 防草シート(敷きたい場所の広さよりも、少し大きめのもの)
- 防草シートを留める固定ピン
- 切れ味の良いハサミまたはカッター
- 金づち
- 防草シート用補修テープ
- メジャー
- チョーク
- 軍手やガーデニング手袋など、手を保護するもの
上記に加えて、防草シートの上に敷くアイテムも事前に準備しておきましょう。
1. 雑草や石を取り除く

防草シートを敷きたい場所に生えている雑草を、草刈り機か手作業で取り除きましょう。
「どうせ防草シートを敷くのであれば、草が生えたままでもいいのでは?」と思うかもしれませんが、思っている以上に雑草はたくましいものです。少しの隙間や穴からでも生えてきますので、可能な限り根ごと抜いてしまいましょう。雑草は可燃ごみとして処分します。
広い面積に防草シートを敷く場合は、除草剤で草を枯らしてから取り除くと作業が楽になります。また、根まで取り切るのが難しい場合も、除草剤を使って根までしっかり枯らしましょう。土の表面に飛び出している石や枝、枯れ葉などもこの段階で取り除いてください。
下地づくりは大変な作業ではありますが、防草シートの施工において大事なポイントです。ここをがんばることで、より効果的に雑草の生長を抑えられますよ。雑草が元気な春夏シーズンよりも、秋冬シーズンのほうが作業がしやすいです。
2. 土を平らにして固める

防草シートを敷く前に、下地となる土を平らに整えます。平らにせず防草シートを敷くと見た目が悪いだけでなく、凸凹に水や砂がたまりやすくなってしまいます。歩きにくさや雑草の繁殖に繋がるため、整地用のレーキ(トンボ)で地面をならして水平にしましょう。必要であれば、土や砂を足してください。
最後に足で踏み固め、地面が平らになったら完了です。もっとしっかり固めたい場合は、板を地面に置き、その上から体重をかけながら踏み固めてもOKです。
防草シートを敷く面積が広いときは、建設機械レンタル会社やホームセンターでレンタルできる「転圧機」の使用も検討しましょう。
3. 防草シートをカットする

整地できたら、防草シートをカットします。事前に切っておくよりも、敷きたい場所に合わせて仮置きしてカットすると失敗しにくいです。大きな石やレンガなどを重し代わりにしながら、防草シートを少しずつ広げてカットしていきましょう。
ポイントは、敷きたい場所ぴったりではなく10cmほど大きめにカットすること。余分にカットした防草シートを外壁や塀のキワに立てて沿わせることで、隙間から雑草が生えてくるのを防げます。
防草シートを並べて敷く場合も、幅を10cm大きめにカットしてください。端と端を重ねて、シートの間に隙間ができないよう配置します。
4. 防草シートを敷いて固定する

防草シートをカットしたら、メジャーとチョークを使って50cm間隔で印をつけ、ピンの頭で防草シートを押さえるように固定していきます。防草シートが重なる部分にもピンを打ちこみ、その上から防草シート用補修テープで2枚を貼り合わせて固定しましょう。
ピンを打ったわずかな穴からも雑草が生えてくる可能性があるため、ピンの上から防草シート用補修テープなどを貼ってふさいでおきましょう。ピンが抜けにくくなる効果もあります。
ここまでで、防草シート自体の施工は完了です。
5. 防草シートの上にアイテムを配置する

防草シートが固定できたら、いよいよお好みのアイテムを上に敷いていきましょう。
ただし、レンガやタイル、ロックガーデンの配置はなかなか時間がかかります。アレンジは作業当日でも後日でも問題ありませんので、体力と相談しながら施工を行ってくださいね。
防草シートの上に敷く素材の厚みや配置
防草シートの上に敷くアイテムの厚みは、防草シートが見えない程度でOKです。砂利とウッドチップは5cm以上の厚さで敷くことが推奨されていますので、定期的にならしたり、減ってきたら補充するなどして5cmの厚みを保ちましょう。
配置についても決まりはありませんが、砂利や人工芝、ウッドチップは防草シート全体に均一に敷きつめるのが一般的です。
レンガやタイル、ロックガーデンは規則正しく並べたり、ランダムに並べたり、大小異なる大きさを組み合わせたりとさまざまなパターンでデザインを楽しめます。2種類以上のアイテムを組み合わせて、表情豊かな庭をつくるのもおすすめです。
注意点
防草シートを敷く際には、以下の点に注意しましょう。
・下地づくりはしっかりと
防草シートを敷く前に草の根や石などが残っていると、防草シートに穴が開いたり、地面と防草シートの間に空洞ができたりする原因になります。地面が平らになっていない場合も、時間が経つにつれて見栄えが悪くなり、歩きにくい、排水しにいといった問題が起きてしまうことも。
下地が凸凹なのも防草シートの上にアイテムごと敷き直しという事態を防ぐためにも、下準備は丁寧に行いましょう。
・隙間ができないように敷く
防草シートにちょっとした隙間や穴があると、飛来した種や、土に残っていた地下茎が芽を出してしまいます。外壁や塀に接する防草シートは必ず大きめにカットして立ち上げ、外壁や塀との間に隙間ができないようにしましょう。
ピンを打ちこんだあと、上から防草シート用補修テープを張ると、ピンの小さな穴から雑草が生えてくるのを防げます。シートとシートのつなぎ目も、必ず重ねて防草シート用補修テープで貼り合わせましょう。
・配管の破損
宅地内には水道管やガス管などの配管が埋まっています。防草シートを敷きたい場所にも埋設されている可能性があるため、ピンを打ち込む際は十分注意してください。気づかずにピンを打つと、ピンの先端で傷や穴ができてしまう可能性があります。
ピンを打つ際は配管が埋まっている可能性を考え、力を加減して打ち込みましょう。また、何か硬いものに当たったと感じたら土の中を確認し、配管だった場合はピンを打つ場所をずらしてください。
・軍手やガーデニング手袋の着用
防草シートのDIYでは、金づちやハンマーを使う危険な作業があります。ケガ防止のため、必ず軍手やガーデニング手袋を着用して行いましょう。草やゴミを取り除くときも着用しておくと安心です。
まとめ:防草シートの上をおしゃれにして、雑草知らずの庭を作ろう

防草シートは雑草を防ぎ、お手入れの手間を減らしてくれる頼もしいアイテムです。ご紹介したアイテムを組み合わせれば、防草効果を高めつつ、おしゃれな庭が実現できます。
下地を丁寧につくる、隙間ができないように敷くといったポイントを押さえればDIYでの施工も可能。「DIYでオリジナルの庭づくりを楽しみたい」という方もぜひチャレンジしてみてくださいね!
DIYで防草シートを敷けるかどうか不安という方は、プロの造園業者への依頼も検討してみましょう。smileガーデンではお庭まわりのお手入れに幅広く対応しておりますので、防草シートの施工についてもお気軽にご相談ください。

愛知県稲沢市生まれ。稲沢市が「日本四大植木産地」であることもあり、幼少期から植木に囲まれて成長。
東京農業大学卒業後、名古屋市内の造園会社に就職。公園の整備工事から国交省事業の国道整備工事における土木及び街路樹等の植栽工事に現場代理人として携わる。
植物とコーヒーを愛するWebライター。園芸好きの一家に生まれ、幼いころから花と緑に囲まれて育ちました。現在の住まいでは、ナチュラルな雑木の庭を目指して試行錯誤中です。 趣味はガーデニング、家庭菜園、メディカルハーブ。子どもと一緒に植物のある暮らしを楽しんでいます。