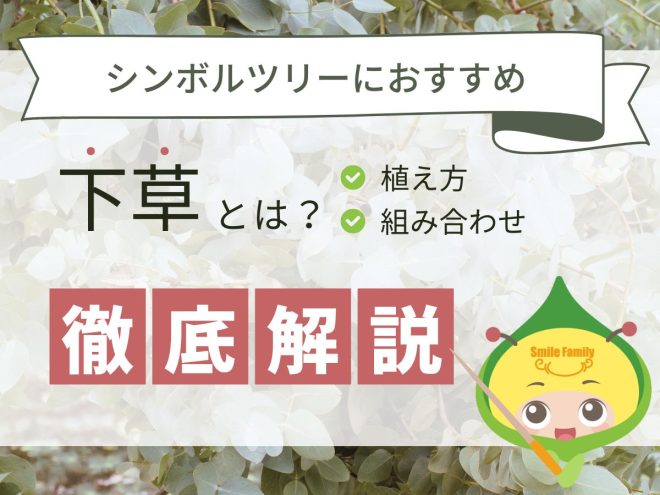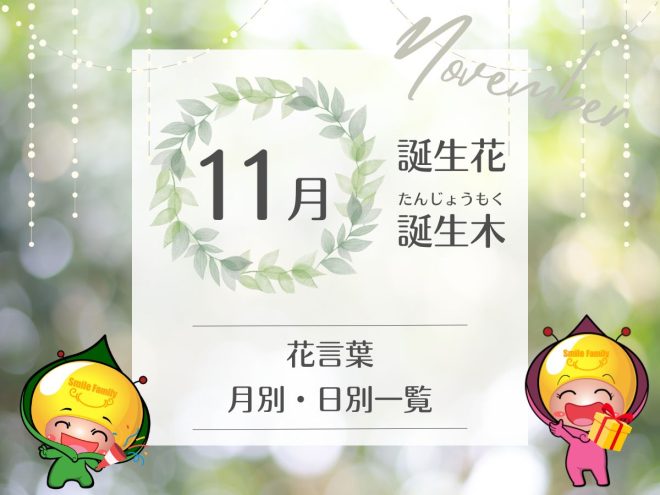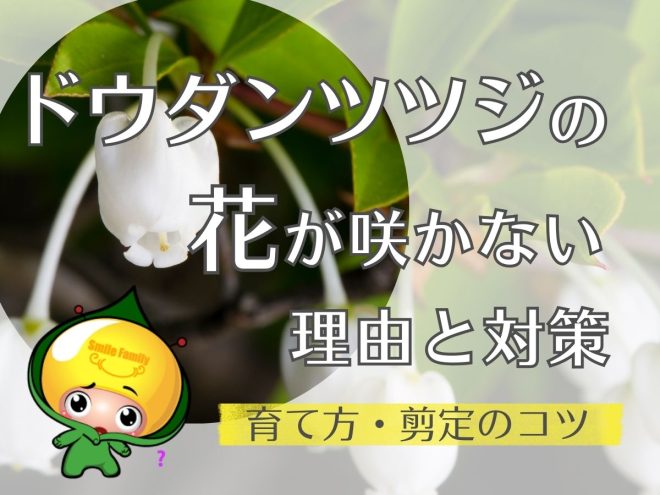サクラの咲いたあと、大きな花を枝先に咲かせるハナミズキ。記念樹などで庭に植えられることも多いです。しかし、育て方によってはハナミズキに花が咲かないこともあります。ハナミズキに花が咲かない原因とその対策についてご紹介します。
 目次
目次
ハナミズキに花が咲かないのはなぜ?

ハナミズキは、育て方によってはなかなか花が咲かないことがあります。
ハナミズキに花が咲かないのには、いくつかの原因が考えられます。手入れの仕方や育つ環境などによって、ハナミズキの生育の仕方も大きく変わるので、そのあたりに原因があることが多いです。
ハナミズキに花が咲かない原因と、その対策方法などについてご紹介します。
原因1:剪定のやり方

ハナミズキは、剪定の仕方によっては全く花が咲かなくなることもあります。人の髪の毛のように、庭木の枝が伸びてきたら切らなければいけないという意識がある方も多いかと思います。
もちろん庭木の剪定は、大きさの調整など人が木を育てるために必要な作業です。しかし、木からしてみれば、光合成に使う枝葉をいきなり大量に取り去られるので、害虫などによる攻撃とほとんど変わりません。
そのため、剪定のやり方が良くないと、ハナミズキにうまく花が咲かないこともあります。
剪定のしすぎ
時期ややり方に関わらず、剪定する量が多すぎるとハナミズキに花が咲きづらくなります。
木の枝葉は光合成して成長するために必要なものなので、剪定によって取り除かれる量があまりに多いと、そちらの回復に力を使いすぎてしまい、花を咲かせることがなかなかできなくなります。特に太枝をノコギリで切るようなやり方だと、樹形が崩れるだけでなく木の元気もなくなってしまうことが多いです。
強剪定のあとに勢いよく伸びてくる枝(徒長枝)は、剪定により失った枝葉を補うために出てくるものなので、そうした枝にはあまり花芽がつきません。
剪定を行う場合には、目的に応じて必要な量だけ剪定するようにしましょう。
花芽を落としている
剪定により、せっかくできた花芽を落としてしまっている可能性もあります。冬になってハナミズキの葉っぱが落ちると、枝先にぷっくり膨らんだ芽が見られることがあります。
これがハナミズキの花芽で、これをすべて落としてしまうと、次の春には花が咲きません。
そのため、冬などの時期に枝先をまんべんなく刈り込むような剪定をしている場合、花は咲かなくなります。
花が咲きやすくなる剪定の仕方

では、ハナミズキに花を咲かせるためには、どのような剪定方法をすれば良いのでしょうか。
ハナミズキは芽吹く力の弱くない木ではありますが、剪定はあまり好みません。そのため、剪定するのは目的に応じて必要最低限にとどめるのがおすすめです。
時期は晩秋から早春までの、葉っぱが落ちている間の時期か、花が咲き終わったあとの5~6月ごろに行います。
花芽ができていたらなるべく落とさないように気を付けながら、混み合っている枝や、他の枝と反対方向に伸びるなどして樹形を崩す枝を整理します。花芽がつきづらく、樹形も崩れる徒長枝も切ってしまいましょう。大きさを抑えたい場合は、枝先を切り戻して小さくします。
ハナミズキの花芽をつくる時期

ハナミズキは7月から9月くらいに翌年の花芽をつけるといわれています。枝先につく、肉まんのような形をしたぷっくりした形のものが花芽です。花芽をつくる時期以降に剪定を行う場合には、花芽をなるべく切り落とさないよう注意して剪定を行いましょう。
また、花芽をつくる時期によく光合成できると、それだけ多くの花が咲きやすくなります。
原因2:土の栄養が足りていない

土の中の栄養分が十分でないと、ハナミズキが花を咲かせない場合があります。肥料をあまり与えていないやせ地だと、花をつくるための栄養が足らずに開花できないという場合があるためです。その場合は、肥料を適切な時期に適切な量を与えることで、解決できる可能性があります。
ただし、肥料が足りないのはイメージがつきやすいからか、安易に改善策として挙げられることがあります。実際には剪定や生育環境などに原因がある場合も少なくないですし、肥料を与えすぎるとかえって逆効果になることもあります。
土の栄養不足以外の原因がないか十分検討してから、肥料を与える量を検討するのがおすすめです。
肥料のあげ方
植え付け時には、元肥として緩効性の肥料を与えます。その後は、花が咲いた後の6~7月ごろにお礼肥として化成肥料などを与えるようにしましょう。冬の間には、寒肥を与えます。
夏の終わりから秋ごろに肥料を与えると、紅葉の色づきが悪くなる場合があるので注意が必要です。
水のあげ方
ハナミズキを庭に地植えしている場合は、植え付け時以外の水やりはほとんど気にしなくても問題ありません。植え付け時には、まだ苗が地面に根付いていないため、土の表面が乾いたら下まで浸透するようにたっぷり水を与えます。
その後、新しい枝葉が旺盛に伸びてくるようになったらおそらく根付いているので、その後は基本的に水やりをしなくても問題ありません。ただし、真夏に長期間雨が降らない場合などに、ハナミズキの葉っぱが明らかにしおれているようなときには水をあげるようにしましょう。
庭で木を育てていると、つい水をあげたくなってしまいますが、街路樹として狭い範囲に植えられているハナミズキが水やりなしで生育して花を咲かせていることを考えると、水をあげなくても問題ないことがわかるかと思います。
逆に、常に水をあげていると、根っこが土の表面に集まってしまい、いざ乾いたときにかえって枯れやすくなってしまいます。植え付け時には適切に水を与え、それ以降は基本的にあげないようにしましょう。
ただし、鉢植えで育てている場合は、ハナミズキが根っこを広げられる範囲がかなり制限されるので、定期的な水やりが必要です。土の表面が乾いてきたら、鉢底から水が出てくるくらいたっぷり水を与えるようにしましょう。
原因3:うまく生育できていない

生育環境が悪いなどの理由でハナミズキがうまく生育できておらず、花を咲かせられないということも考えられます。樹木は光合成を行うことにより成長していくので、その光合成がうまくできていなければ生育できません。
生育環境がハナミズキにあっていなかったり、病害虫などにより葉っぱが失われたりしていると、その程度によっては生育が悪くなります。
そのため、街などでたくさん花を咲かせているハナミズキと比べ、庭のハナミズキの生育があまり良くないというような場合は、周囲の環境を見直してみるのがおすすめです。
ハナミズキの生育が悪くなる原因として考えられるものをご紹介します。
生育環境などの問題
ハナミズキの生育環境があまり良くないと、ハナミズキが花を咲かせられない場合があります。
なんとか光合成して自身が生き残ることに精一杯になってしまい、花を咲かせるほどの余裕ができないことなどが直接の理由として考えられるものです。
たとえば、日当たりが良くなかったり、土の環境が良くなかったり、水分条件が適切でなかったりなどの要因が考えられます。街中にもハナミズキがよく植えられているかと思いますが、それらの中で、生育が良く花をたくさん咲かせているものと庭のハナミズキを比べてみましょう。
土の環境など見えづらいものはありますが、どのあたりに違いがあるのかわかってくるかもしれません。
病害虫が多い
病気や害虫が多すぎると、ハナミズキがうまく生育できず、花を咲かせられない可能性があります。
病気も害虫は、樹木の葉っぱや根っこなどに寄生し、栄養を奪い取るものです。葉っぱに少し病気や害虫がつくくらいなら大した問題にはならないこともありますが、あまりにたくさん発生する場合は、その分ハナミズキの栄養が奪われているわけですから、花を咲かせられるほどの余裕ができなくなる可能性もあります。
葉っぱや幹などに、病気や害虫がついていないかよくチェックしてみましょう。
ハナミズキに見られる病気や害虫


ハナミズキには、いくつかの病害虫が発生することがあります。
病気としては、葉っぱの表面が白い粉を吹いたようになる「うどんこ病」が見られることが多いです。基本的には宿主を殺すことのない菌なので、これ単体で木が枯れることはありませんが、栄養は間違えなく取られてしまうし、見た目もあまり良くありません。
発病したらなるべく早い段階で適用のある殺菌剤を散布して対処するか、病気の出ている葉っぱを切って焼却処分するか地中深くに埋めることによって対処が可能です。
害虫は、キアシドクガという毛虫が春に発生して葉っぱをかじることがあります。ドクガとつきますが無毒なガの幼虫で、触っても問題ありませんが、大量に発生すると葉っぱを丸坊主にされてしまうこともあります。
数が少なければ直接捕殺するか、幼虫や卵の付いている枝葉を切って処分するなどして対処するか、幼虫の出ている時期に適用のある薬剤を散布して対処しましょう。
他にも、ツノロウムシやアオキシロカイガラムシなどのカイガラムシ類や、アオバハゴロモのような枝葉の汁を吸う害虫が発生することがあります。
これらも、数が少なければ発生時期に直接捕殺してしまうか、適用のある薬剤を散布することで対処が可能です。薬剤の種類によってはカイガラムシ類に効果が無い場合もあるので、カイガラムシ類に効果のあるものを選ぶようにしましょう。
花が咲くほど大きくなっていない

ハナミズキが、まだ花を咲かせられるほど成長できていない可能性もあります。まだ大人になれていないというようなことで、ハナミズキの苗が植え付けてから何年も経っていない小さなものだったり、ハナミズキの生育が悪く、年月が経っているのにあまり大きく成長できていなかったりすると、花を咲かせる段階まで到達できていない可能性があります。
樹木は人よりも長いスパンで生きているものが多いので、植えてすぐに花が咲くようにはならないことが多いということには留意しておきましょう。
ハナミズキの好む生育環境

庭の環境をハナミズキの好む生育環境に近づけてあげると、花が咲きやすくなります。ハナミズキの生育が悪く、庭の環境があまり良くないと感じる場合、改善を試みてみましょう。
ハナミズキの生育に関わる環境の要素は様々です。感覚でこれだと決めつけずに、「ハナミズキが今こういう状態だから、この環境を良くしたら花が咲くかもしれない」のように、一つ一つ仮説を立てながら検証してみるようにしましょう。
ハナミズキの好む生育環境についてご紹介します。
日当たり
ハナミズキは日当たりの良い環境を好みます。街路樹などで植えられているハナミズキも直射日光の当たるような明るい場所でよく生育していますが、それと同じくらいの明るさをイメージしていただければ良いと思います。
逆に日当たりが悪いと、成長が悪くなって花も咲きづらくなるので注意が必要です。多少の日陰でも育つには育ちますが、花の数が少なくなり、秋の紅葉もきれいに色づきにくくなります。
また、ある程度の乾燥には耐えられますが、日が地面に当たりすぎて周りの土が乾燥しすぎてしまうのも良くありません。強い西日が当たると葉焼けなどを起こすこともあり、そうした場合は西側に日を遮る木を植えたり寒冷紗を設置したりすることで対処できます。
土壌
ハナミズキは土をそれほど選びませんが、やや砂質で水はけの良い肥沃な土でよく育ちます。
逆に、常に湿っていたり水が溜まっていたりする土では育ちづらくなる場合があるので、注意しましょう。
また、乾燥には比較的強いですが、あまりに乾燥しすぎるのも良くないので、注意が必要です。
土の条件が良くなさそうと感じたら、ハナミズキの周囲の土を、なるべく根っこを切らないように注意しながら掘って穴をつくり、改良した土で埋め戻すということをしても良いかもしれません。
病害虫の防ぎ方
病気や害虫は、つかないように予防するか、ついてもなるべく早く対処するのが重要です。病気や害虫がたくさん発生してからでは対処が難しくなり、手に負えなくなることもあるためです。
まず一ついえるのは、ハナミズキを健康に生育させられれば、多くの病害虫を防ぐことができます(全てではありません)。その上で、病気や害虫が発生したらなるべく早いうちに対処を行いましょう。あまり目くじらを立てすぎても良くありませんが、病気や害虫は多くの場合、発生したてが最も数や量が少ないので、対処も楽です。
病気や害虫になるべく早く気づくためには、日ごろからハナミズキをよく観察しておくのが重要です。日ごろからよく見ておけば、病気や害虫が発生して様子が変わったときに、いち早くその違和感に気づくことができます。
ハナミズキに花が咲くまで

よく売られている接ぎ木苗の場合、3から5年くらい経たないと花が咲かないと言われています。種から育てた苗の場合はさらに数年かかると思っておいた方が良いでしょう。
ただし、この年数は順調に育った場合のものなので、若いうちから剪定しすぎていたり、あまり良くない生育環境で育っていたりすると、花が咲くまでにさらに長い年月がかかる可能性もあります。
また、若くて生育の良い苗だと、枝が旺盛に伸びて成長することがありますが、そうして勢いよく伸びた枝には花芽がつきづらいです。
まとめ

ハナミズキに花を咲かせるためには、なぜ花が咲かないのか推測し、それに合わせて改善していく必要があります。剪定のやり方などすぐに改善できるものなら良いですが、庭の環境を変えなければいけない場合や、原因がなかなか思い当たらない場合などは、試行錯誤しながら改善していく必要があるので、少し大変です。
場合によっては、smileガーデンのような業者にお願いしてみるのでも良いでしょう。もちろんお金はかかりますが、原因もわからないまま色々と試すことに比べたら、知識や経験のあるプロに一度任せた方がお金も労力も結果的に少なくなる場合もあります。一度プロの技を見て学んでから、自分でやってみるのも良いでしょう。ぜひご相談ください。