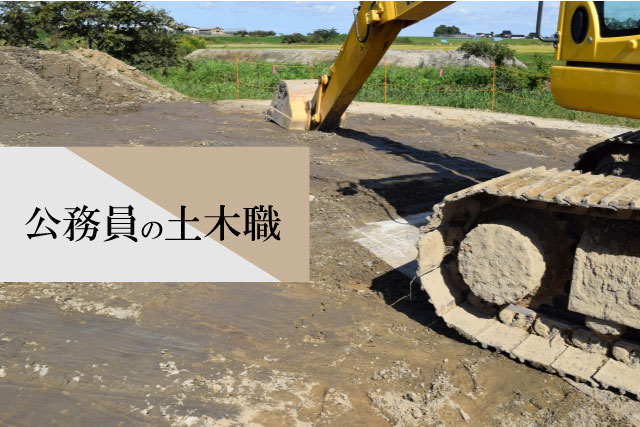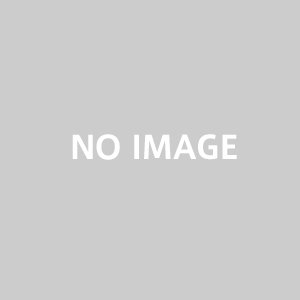トンネル工事の現場は、土木工事の中でもハードだという印象があります。
3Kで残業も多く、夜間工事もあります。工事は2~3年続くことが当たり前で、現場は過疎地がほとんどです。
しかし、給与や待遇は優遇されています。
一般土木作業員の平均年収は、約376万円です。それに対して、トンネル工事の仕事の平均年収は、約498万円です。
トンネル工事業界は、慢性的な人手不足なので、会社は福利厚生にも力を入れています。圧倒的な売り手市場であることは間違いありません。
トンネル工事の仕事内容と、必要となる資格について紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
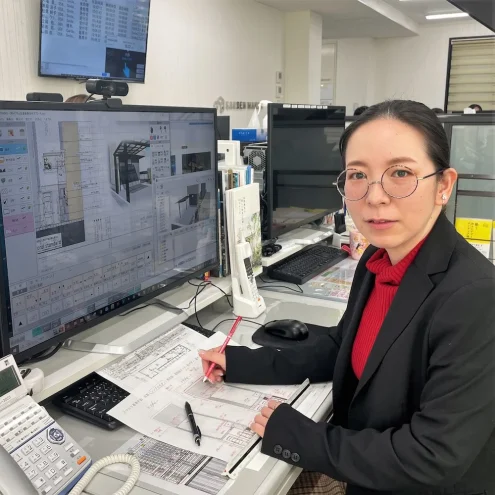
静岡県御殿場市の土建屋に生まれ、大型重機が大好きな子供時代を送る。
建築に憧れ、三重短大で住環境を学ぶ。新卒でハウスメーカーFC工務店の「インテリアプランナー」に応募するも、社長の勘違いで募集したかったのはなんと「エクステリアプランナー」!!
ハウスメーカーで個人住宅のエクステリアを担当。その後、ゼネコン住宅事業部のインテリアプランナー、植木屋の外構プランナーを経て、現在は(株)ガーデンメーカーで営業設計を務める。
 目次
目次
トンネル工事を3つの観点で分類してみる

トンネル工事はどんな仕事か理解しようとするとき、使用目的、設置場所、施工方法で分類して見ていくと分かりやすいです。
この3つの観点からトンネル工事の仕事内容を見ていくことで、トンネルが私たちの生活に欠かせないものであること、トンネル工事は高度な土木技術を必要とすることなどを理解できます。
トンネル工事を使用目的で分類
トンネルの使用目的は、大きく分けて、通行用と通水用があります。
通行用トンネル
通行用トンネルは、地山や岩盤を掘削して、鉄道や自動車道を通すためにつくられるトンネルです。
日本の地形は山や峠が多く、人や物の大量移動には時間がかかり、コストが割高になります。豪雪や暴風雨など自然災害の影響も受けやすく、安全面のリスクも高まります。
トンネルは、カーブや勾配を最小限に抑えるよう設計され、換気設備や非常用施設の設置も義務付けられているので、大量移動が簡単・安全にできるのです。
トンネル工事の技術は、地下街や地下駐車場をつくる際にも応用されています。
通水用トンネル
通水用トンネルとして主なものは、以下の3つです。
| 水力発電所トンネル | 圧力導水路(トンネル)によるダムからの取水 |
|---|---|
| 上下水道用トンネル | 都市部のトンネル内配管及び農業・工業用水の送水用トンネル |
| 地下河川トンネル | 慢性的な浸水地帯を改修するための放水路トンネル |
いずれも、普段目にすることがないトンネルですが、私たちの生活を守り快適にするために重要な働きをするトンネルです。
トンネル工事を設置場所で分類
トンネルは、様々な場所に設置されています。代表的な3つの設置場所を紹介します。
山岳トンネル
山岳トンネルは、山間部に設置され、山を貫通するように掘削してつくられるトンネルのことを言います。トンネルのイメージとして最初に思い浮かぶトンネルです。
最近の傾向として、山岳トンネルは、より大きなトンネルが求められるようになっています。3車線や歩道のある、いわゆるトンネルの大断面化です。
また、自然に配慮した環境対策も重要になっており、多様化したニーズに対応する技術力が求められています。
都市トンネル
都市トンネルとは、建物の地下を通るトンネル、首都高などの高速道路に設置されるトンネルのことです。その他、地下鉄のほとんどや、空港の滑走路などを避けてつくられる地下トンネルも都市トンネルに分類されます。
都市トンネルの施行方法には、開削工法やシールド工法など、他のトンネルの施工にも見られる工法の他、都市NATMがあります。
都市NATMは、高度な技術を用いることにより、地盤の柔らかい都市直下でも施工できる工法です。
海底トンネル
海底トンネルは、文字通り、海底を掘削してつくられるトンネルです。
日本には、海底トンネルが5つあります。
- 関門鉄道トンネル
- 関門国道トンネル
- 青函トンネル
- 東京湾アクアライン
- 川崎港海底トンネル
特に、関門鉄道トンネルは、世界初の海底鉄道トンネルとして有名です。
青函トンネルは、津軽海峡を縦断して本州と北海道を結んでいるトンネルで、新幹線も走行しており、世界で2番目に長い鉄道トンネルとなっています。
トンネル工事を施工方法で分類
現在のトンネル工事で代表的な施工方法を3つ紹介します。
山岳工法
山岳工法は、山間部にトンネルをつくる際に用いられる工法です。
トンネルをつくる地山が機械では掘れないほど硬い場合は発破を行います。機械で岩盤に穴を開け、そこにダイナマイトを仕かけ発破するのです。
細かくなった土砂(ズリ)を機械で積込み、機関車両で搬出し、トンネルから出たらトラックで運搬するのが一般的な手順です。
覆工(トンネルの壁をつくる)は、地山が崩れないようにセメントを吹付け、鉄筋棒(ロックボルト)を打ち込みます。そして、仕上げに、コンクリートを打設します。
シールド工法
シールド工法は、シールドマシンや各種機材を用いてトンネルをつくる工法です。
シールドマシンとは、地山を掘削するための機械で、回転するカッターヘッドに付いているカッタービットで岩盤や玉石を細かく砕きます。
細かくなった土砂は、開口部から中に入り、開口部に付随したスクリューコンベアでトンネル内に運ばれるのです。
シールドマシンは、トンネルの中や地上に設置された計測機器や制御装置で、きめ細かく制御されながら安全施工をしていきます。
TBM工法
TBM工法は、TBM(トンネル・ボーリング・マシン)という、シールドマシンをさらに巨大化させて高速化を可能にした機械を使用して岩盤を掘削していく工法です。
高速掘進が可能で、水路トンネルなどではTBMによる掘削面が完成断面となるため、掘削に無駄がありません。
高速施工のため、工期の短縮が可能で、コストの削減ができます。また、掘削後の地山の緩みが小さくなるため、作業の安全性も格段にアップします。
トンネル技能者の仕事内容と必要な資格とは

2019年4月より、「建設キャリアアップシステム」が本運用されています。
官民が一体となって構築された建設キャリアアップシステムは、「技能者の資格」「社会保険加入状況」「現場の就業履歴」などを蓄積し、技能者が能力や経験に応じた処遇を受けられる環境を整備するのに活用されています。
トンネル工事業界で主体となっているのは、「一般社団法人 日本トンネル専門工事業協会」です。
建設キャリアアップシステムでは、トンネル技能者を4つのレベルに分類しています。この4つのレベルごとの技能者像を見ることで、トンネル技能者に必要な資格が分かりますので参考にしてください。
レベル1 初級(見習い)技能者
トンネル工事を施工するための基礎知識や、工具・機械などの安全な使い方を身につけていて、上司の指示を受けながら作業の補佐ができる技能者です。
建設キャリアアップシステムに技能者登録はしているが、まだ、レベル2から4までの判定を受けていない技能者ということになります。
レベル2 中堅(一人前)技能者
トンネル工事に必要な作業内容を把握して、工程や工事の流れに沿って、一般的な早さや精度で作業ができるレベルとなります。
建設キャリアアップシステムに蓄積された就業日数が430日(2年)以上で、以下の資格を保有していなければなりません。
- 車両系建設機械(機体重量3t以上の整地・運搬・積込み・掘削用機械)の運転技能講習
- 小型移動式クレーン(5t未満)の運転技能講習
- 玉掛け作業技能講習
- 高所作業車の運転技能講習
- 車両系建設機械(解体用)の運転技能講習又はコンクリート打設用機械の作業装置の操作特別教育
- 高所作業車の運転特別教育
- 特定粉じん作業特別教育
- ずい道等の掘削・運搬・覆工等の内作業特別教育
レベル3 職長技能者
トンネル工事を施工するにあたって必要となる資材の発注や、段取りの検討、他の技能者への適切な指示、品質・工程・安全管理ができる技能者です。
建設キャリアアップシステムに蓄積された就業日数が1,505日(7年)以上で、レベル2に該当するすべての資格と以下の資格を保有していなければなりません。
- ずい道等の掘削等作業主任者又はずい道等の覆工作業主任者
- 発破技士又は火薬類取扱保安責任者(甲・乙種)
- 職長・安全衛生責任者教育
レベル4 登録トンネル基幹技能者など
トンネル工事において、高度な管理能力を持ち、全体工程を把握し管理することができるレベルの技能者です。元請管理者と協議したり、提案・調整をしたりすることも必要とされます。
レベル4は、職長としての就業日数が645日(3年)以上で、建設キャリアアップシステムに蓄積された就業日数が2,150日(10年)以上であることが必要です。
レベル2,3に必要とされる資格すべてと、以下の資格の取得、又は表彰を受けていることが
条件となっています。
- 登録トンネル基幹技能者(講習修了証の期限が切れている場合は除く)
- 優秀施工者国土交通大臣顕彰
トンネル工事 まとめ

トンネルは私たちの生活を支える重要な施設です。厳しいこともある分野ですが、働いている人たちは誇りをもって仕事をしています。
トンネル工事は、発破が多用されていたため、かつては危険な工事の代名詞のような扱いを受けていました。
現在では、シールドマシンやTBMの使用が主流になり、徹底した安全対策も功を奏してイメージは変わってきています。
トンネル工事は、一生の仕事として挑戦してみる価値は大いにある土木工事の一つです。