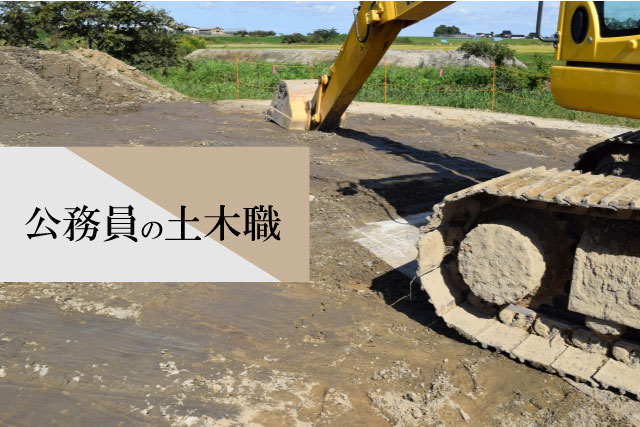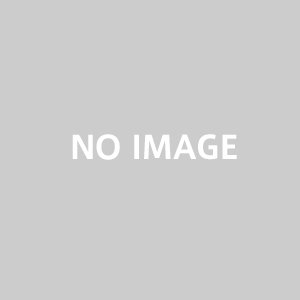整備された道路は、人や車の通行を快適にし、安全なものにしてくれます。
物流の生命線であり、ガスや上下水道、情報通信のための光ファイバーなども道路の下を通っています。
ただ、道路が、どのように造られ維持されているかを理解している一般の人は少ないでしょう。道路工事中の規制にひっかかり、その時だけ意識する程度のはずです。
しかし、土木工事に関わる仕事をしようとする人は、道路工事について理解しておく必要があります。
道路工事は、様々な土木工事に関わる、土木工事の基本ともいえる工事だからです。
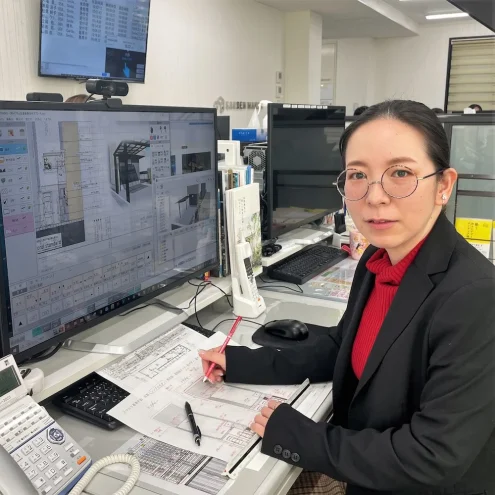
静岡県御殿場市の土建屋に生まれ、大型重機が大好きな子供時代を送る。
建築に憧れ、三重短大で住環境を学ぶ。新卒でハウスメーカーFC工務店の「インテリアプランナー」に応募するも、社長の勘違いで募集したかったのはなんと「エクステリアプランナー」!!
ハウスメーカーで個人住宅のエクステリアを担当。その後、ゼネコン住宅事業部のインテリアプランナー、植木屋の外構プランナーを経て、現在は(株)ガーデンメーカーで営業設計を務める。
 目次
目次
道路工事全般を理解するための基本事項とは

ここでは、道路工事全般を理解するために知っておいてほしいことを紹介します。
路上工事・舗装工事

道路上で行われる工事を、路上工事といいます。路上工事には、道路工事と占用工事の2種類あります。
道路工事は、道路本体の新設や、劣化した路面の補修などをする工事です。占用工事とは、電気やガス、通信網などの埋設物の工事です。
ちなみに、ガードレールは、とび・土木・コンクリート工事になります。
また、よく道路工事と混同されるのが、舗装工事です。
舗装工事は、道路だけでなく、建築物の外構や公園、庭園などでも行われる工事です。アスファルトやコンクリート、ブロックなどの舗装材を使って施工する工事全般のことをいいます。
道路の構造

道路は一般的に、アスファルト舗装のことが多いです。道路の構造について、アスファルト舗装を例に紹介します。
アスファルト舗装は、深い位置から、路床、下層路盤、上層路盤、基層、表層で構成されています。
それぞれについて、簡単にまとめました。
| 路床 | 原地盤のことで、整正や改良されて交通荷重を支える道路の基盤となる |
|---|---|
| 下層路盤 | 10~20cmの層で、比較的大きな粒度の砕石を転圧した路盤 |
| 上層路盤 | 5~20cmの層で、粒度調整砕石が用いられ複数回転圧される路盤 |
| 基層 | 上層路盤の不陸を整正する目的でアスファルト混合物を用いることが多い |
| 表層 | 路面としての機能性・快適性・安全性が確保されていなければならない |
最近の傾向として、使用材料などに、自然環境に配慮したものが求められるようになっています。また、工事全般において、デザイン性や静粛性の訴求が高まっているのが現状です。
道路管理者

公道には、必ず道路管理者がいます。以下に道路の種類ごとに道路管理者をまとめました。
| 道路の種類 | 管理者 |
|---|---|
| 高速自動車国道 | ・国土交通大臣 (代行者 高速道路株式会社など) |
| 国道 | ・指定区間内は、国土交通省 ・指定区間外は、原則、都道府県知事 ・道路法で定められた基準によっては指定市の市長 |
| 都道府県道 | ・原則、都道府県 ・道路法で定められた基準によっては指定市の市長 または当該町村の町村長 |
| 市町村道 | ・市町村 |
道路管理者は、道路法によって細かく規定されてます。
ただ、原則的には、国道は国、都道府県道や市町村道は各自治体が管理者だと覚えておいて間違いありません。
各道路に関わる工事は、その道路管理者から発注されるのが基本です。
道路工事の種類とそれぞれの仕事内容とは

道路工事を大きく分けると、新設、改良、維持・修繕の3つになります。
それぞれの仕事内容を、工事の概要と施工の流れから紹介します。
道路新設工事

道路の新設工事とは、未舗装の地面を道路にする工事です。
工事の概要
道路新設工事を企画・立案した道路管理者は、地元関係者と協議します。
道路管理者は、まず、基本設計で地元関係者に説明します。関係者の了解を得てから、本格的な現地測量や地質などの調査を開始するのです。
調査を基に出来上がった設計図面により、再度、地元関係者と詳細を詰めます。その後必要であれば、用地買収や家屋移転による補償などがなされます。
これらがすべて整ってから、道路新設工事は入札公告されるのです。
施工の流れ
道路新設工事を請け負った施工業者が行う施工の流れを見ていきます。
| ① 現場測量 | 発注者の設計図面と現地状況を照合する |
|---|---|
| ② 路床工事 | 地盤をブルドーザーやモーターグレーダで整地する |
| ③ 路盤工事 | 砕石をモーターグレーダで敷均しローラー重機で締固める |
| ④ 基層工事 | 加熱したアスファルト混合物をアスファルトフィニッシャーで敷き均す |
| ⑤ 表層工事 | 密度の高いアスファルト混合物をアスファルトフィニッシャーで仕上げる |
以上が一般的な道路新設工事の手順ですが、特に表層工事が最重要です。道路の顔であると同時に、外的要因で一番影響を受けやすい層だからです。
道路改良工事

道路改良工事とは、地域の現状に合わせて道路を改良する工事です。
工事の概要
地域住民や道路利用者など、市民生活の利便性を向上させる目的で施工されるのが、道路改良工事になります。
渋滞を解消するために、車道の拡幅や歩道の整備、交差点のボトルネック(交通容量の低下)の解消を目的として施工される場合が多いです。
最近特に留意されているのが、道路のバリアフリー化です。小さな子どもやお年寄り、体の不自由な方が通行しにくかったり、見通しが悪かったりする場所の改良が増えています。
施工の流れ
道路改良事工事は、地元からの要望書が道路管理者に提出されることで検討が始まります。その後、管理者による要望箇所の現地調査により、緊急性、安全性、地域バランスなどが判断されるのです。
一般的な道路改良工事の流れです。
| ① 道路側溝の設置 | 現況の未舗装道路の排水構造物の機能を維持するため |
|---|---|
| ② 擁壁の設置 | 現況の未舗装道路の土留め構造物の機能を維持するため |
| ③ 地下埋設物の移設及び延長 | 現況のライフラインの機能を維持するため |
| ④ 道路舗装工事 | 手順は新設工事に準ずる |
道路工事は、生活の利便性を向上させるために施工されますが、現況の機能の維持も重要になります。この接続性に不備があると、改良ではなく、改悪になりかねません。
道路維持・修繕工事

道路の構造を保全して、円滑な交通を確保するために、道路の不良箇所を適切に処理するのが、道路維持・修繕工事です。
工事の概要
道路管理者は、管轄する道路の実際の維持業務を専門業者(主に土木会社)に業務委託しています。管理者は、業務の遂行状況を監督する立場です。
この維持業者は、年間契約で発注されることが多く、細かい管理基準を基に業務を遂行します。
維持業務は工事と違って、日常業務の継続性と緊急時の対応力が重要なため、常にしっかりとした社内体制が必要です。その体制の構築は、1年程度では難しいです。
そのため維持業者は、多年度に渡って同一会社というのが現状となっています。
施工の流れ
道路維持・修繕工事の施工(業務)の流れのなかで、最重要なのが道路パトロールです。日に何回かの定期的な道路パトロールによる情報収集が業務の基本です。
- 道路の路面・路側帯・構造物・付属物の損傷や損傷を誘引する事象の発見
- 緊急を要する事象に対する応急措置と管理者や各担当官庁への連絡
- 損傷が発見された事象を復旧するための応急工事の実施
- 応急的な道路維持工事・作業の監督(管理者への報告)
特に災害対策では、道路管理者や各協力会社と連携しながら、速やかで確実な対応が求められます。
道路工事|まとめ

この記事では、道路工事の基本事項と、道路工事の種類について紹介しました。
まず基本事項については、道路工事という用語と判別がつきにくい、路上工事や舗装工事について違いを説明しました。その次に、道路の構造や道路管理者についておさらいしました。
道路工事の種類については、新設工事、改良工事、維持・修繕工事の3つの違いが比較できるように概要を見てきました。
これから道路工事を目指す方はもちろん、現在道路工事に携わっている方にも参考になっていれば幸いです。